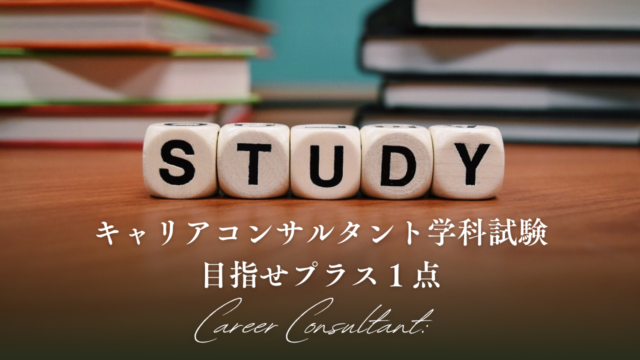ハヴィガースト

この記事について
キャリアコンサルタント試験の理論家対策として書いています。
参考書などで、ちょこちょこ出てくるハビィガーストですが、どこの説明もすごいあっさりしていて、記憶から抜け落ちてしまうので、記憶定着のため記事にしました。
ハビィガーストで覚えるべきは「発達課題」という概念を提唱した人ということ。
その後にその概念を使ってスーパーが理論展開しています。
スーパーが偉大すぎて、影に隠れがちですが、キャリア発達という概念において、重要な「発達課題」を最初に考えた実はすごい人です。
ハヴィガーストの理論について
教育心理学者ロバート・J・ハヴィガースト(Robert James Havighurst)
は、人間が生涯を通じてさまざまな発達段階で達成しなければならない「発達課題」を中心に据えています。
発達課題という概念を最初に提唱しました。
各発達段階でこれらの課題を達成することで、個人は幸福になり、次の発達段階での課題も成功しやすくなるとされています。
一方、課題を達成しないと、社会的に認められず、次の課題を成し遂げることも困難になります。
発達段階と課題
ハヴィガーストの理論では、人生を以下の6つの段階に分け、それぞれの段階で特定の発達課題が設定されています。
- 乳幼児期(誕生から6歳)
- 歩行の学習
- 固形の食べ物を食べることの学習
- 話すことの学習
- 排泄をコントロールすることの学習
- 性の違いと性的な慎みの学習
- 善悪の区別と良心の発達。
- 児童期(6歳から12歳)
- 普通のゲームに必要な身体的スキルの学習
- 自己に対する健全な態度の養成
- 友人と仲良くすることの学習
- 男女としての社会的役割の学習
- 読み・書き・計算の基礎的スキルの発達。
- 青年期(12歳から18歳)
- 同性・異性との新しい関係の構築
- 自分の身体構造を理解し、性別役割を理解する
- 大人からの情緒的独立
- 経済的独立の準備
- 職業の選択と準備。
- 成人前期(18歳から30歳)
- 配偶者の選択
- 結婚生活の学習
- 家族の形成
- 子どもの育て方
- 職業生活のスタート。
- 中年期(30歳から60歳)
- 子どもが幸福な大人になるよう支援する
- 社会的責任の果たし方
- 職業生活での業績の維持
- 余暇活動の充実。
- 成熟期(60歳以降)
- 体力や健康の衰えに対応する
- 退職と収入の減少に対応する
- 配偶者の死に対応する
- 社会的役割の柔軟な受け入れ。
理論の特徴と影響
ハヴィガーストの理論は、発達課題を達成することで個人が幸福になり、次の課題も成功しやすくなることを強調しています。
ただし、すべての人生に当てはまるわけではなく、多様な幸福観を考慮する必要があります。
この理論は、教育や心理学の分野で広く影響を与えています。
まとめ
試験では「発達課題」とハヴィガーストを結びつける問題が多く、ハヴィガーストの発達段階と課題については、あまり出題されていない感じです。
余裕があれば、発達段階と課題を覚えておきましょう。
少なくとも発達段階が6段階という位は覚えておくといいかもしれません。
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いします。ブログ運営の励みになります。