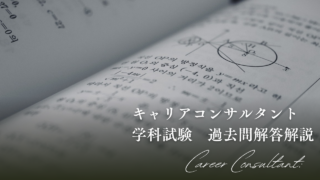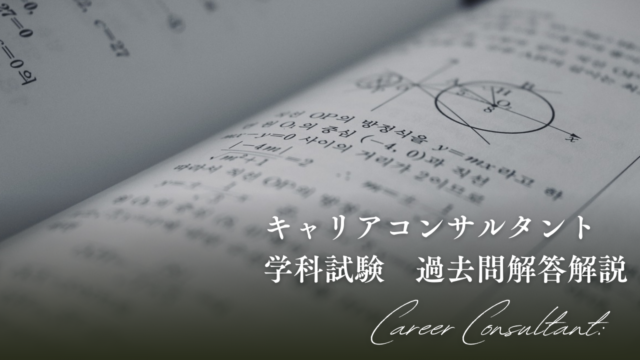第28回 国家資格キャリアコンルタント試験 学科試験 解答解説(問21〜25)
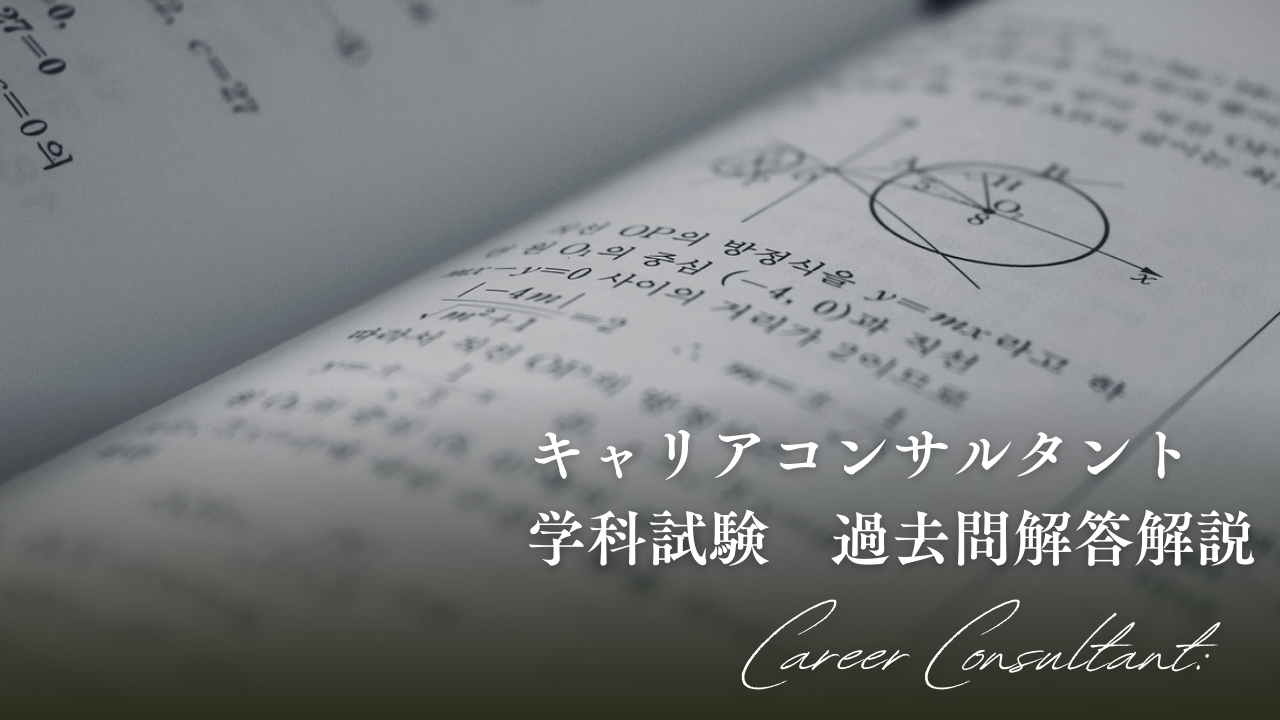
この記事について
令和6年3月実施
第28回 国家資格キャリアコンサルタント試験 解説を作成しました。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしています。
問21
正解:3
選択肢1:不適切
- 年次有給休暇の取得率については、2016年調査以降、働き方改革の取組の進展
- その結果、取得率は男女計では8年連続で上昇しており、2023年調査は、1984年の調査開始以降初めて6割を超えた。
- 男女別にみると、2016年調査以降、男女ともに上昇傾向となっている。
選択肢2:不適切
- 賃金については、現金給与総額が3年連続で増加する一方、実質賃金は物価の上昇に追い付かないことにより減少した。
選択肢3:適切
- 労働分配率とは、企業が生み出した付加価値に対する人件費の割合
- 労働分配率(%) = 人件費 ÷ 付加価値 × 100
- 企業の資本金規模別の労働分配率をみると、2014年以降 の景気拡大局面では、全ての資本金規模において労働分配率は低下傾向にある。
- 2020年の感染拡大による景気後退の影響により企業収益が悪化し、労働分配率は大幅に上昇したが、翌年以降は、経済社会活動の活発化に伴い、企業収益が増加したことで、低下がみられる。
- ⇒景気が上がって、人件費の上昇が、企業付加価値の上昇を上回れば、労働分配率は下がる。
選択肢4:不適切
- 労働組合員数及び推定組織率の推移をみると、2023年は、労働組合員数994万人と2年連続で1,000万人を割り、推定組織率は16.3%となり、ともに3年連続で低下した。
- 一方、2023年は、パートタイム労働者の労働組合員数は過去 最高の141万人、推定組織率は8.4%となった。
- ⇒正社員の組合員数は減っているが、パートタイム労働者の加入は増えている。
問22
正解:4
選択肢1:不適切
- 就業者に占める女性の割合は、日本は令和5(2023)年は45.2%であり、諸外国と比較して大きな差はない。
- 一方、管理的職業従事者に占める女性の割合は、諸外国ではおおむね30%以上となっているが、日本は令和5(2023)年は14.6%となっており、諸外国と比べて低い水準となっている。
選択肢2:不適切
- 女性の年齢階級別正規雇用比率は25~29歳の59.1%をピークに低下(L字カーブ)。
- M字カーブは、女性の年齢階級別の就業率を示すグラフです。
選択肢3:不適切
- 第1子出産前に就業していた女性の就業継続率(第1子出産後)は上昇傾向にあり、平成27(2015)年から令和元(2019)年に第1子を出産した女性では69.5%
選択肢4:適切
- 一般労働者における男女の所定内給与の格差は、長期的にみると縮小傾向にあるが、依然と して大きい。
- 令和5(2023)年の男性一般労働者の給与水準を100としたときの女性一般労働者の給与 水準は74.8で、前年に比べ0.9ポイント減少。
- また、一般労働者のうち、正社員・正職員の男女の所定内給与額をみると、男性の給与水準 を100としたときの女性の給与水準は77.5となり、前年に比べ0.7ポイント減少。
問23
正解:2
選択肢1:不適切
2025年4月からは雇用保険の適用範囲が拡大され、週の所定労働時間が10時間以上の労働者も加入できるようになります。これにより、より多くの労働者が雇用保険の対象となりますが、暫定任意適用事業の制度自体は継続されます。
暫定任意適用事業とは、雇用保険の強制適用ではなく、事業主の判断で任意に加入できる事業のことを指します。具体的には以下の事業が該当します。
・農林水産業に属する個人経営の事業
・常時5人未満の労働者を使用する事業
選択肢2:適切
この説明は2025年3月現在では正確ですが、近い将来変更される予定です。
現行の雇用保険制度
現在の雇用保険制度では、以下の2つの条件を満たす労働者が被保険者となります。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
これらの条件は、労働者の雇用形態(正社員、パート、アルバイトなど)に関わらず適用されます。
2025年4月からの変更
2025年4月から雇用保険の適用範囲が拡大されます。
- 週の所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更されます。
この改正により、週10時間以上20時間未満の労働者(約506万人)が新たに雇用保険の被保険者となる見込みです。
選択肢3:不適切
雇用保険二事業は、雇用安定事業と能力開発事業から構成され、雇用の安定や労働者の能力開発・向上を目的としています。
したがって、雇用保険二事業と雇用継続給付(高年齢雇用継続給付および介護休業給付)は別個の制度であり、同一のものではありません。
選択肢4:不適切
雇用保険料率は、労働者負担と事業主負担で異なる率が設定されています。
雇用保険料率の構成
- 失業等給付・育児休業給付の保険料率(労働者と事業主が負担)
- 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみが負担)
- 2025年4月1日から適用される雇用保険料率
一般の事業の場合
- 労働者負担: 5.5/1000 (0.55%)
- 事業主負担: 9/1000 (0.9%)
(失業等給付・育児休業給付: 5.5/1000、雇用保険二事業: 3.5/1000)
- 合計: 14.5/1000 (1.45%)
問24
正解:2
選択肢1:適切
週1日勤務の非正規労働者についても、6か月継続勤務し、出勤率が8割以上であれば、年次有給休暇の権利が与えられます。
選択肢2:不適切
育児休業取得期間は、年次有給休暇の出勤率計算において出勤したものとみなされます。
育児休業と年次有給休暇の関係
- 1. 出勤率の計算方法
年次有給休暇の付与要件である「全労働日の8割以上出勤」の計算において、育児休業期間は特別な扱いを受けます。 - 2. 育児休業の取り扱い
育児休業法に基づく育児休業期間は、出勤したものとして取り扱われます。これは、労働基準法第39条第10項に規定されています。 - 3. 出勤率への影響
育児休業を取得した期間は、出勤日数および全労働日数の両方に含まれます。例えば、算定期間中にすべて育児休業を取得していた場合、出勤率は100%となります。 - 4. 目的
この規定は、育児休業取得を理由に年次有給休暇の付与が妨げられることを防ぐためのものです。 - その他の注意点
育児休業中に年次有給休暇を付与する必要はありますが、育児休業期間中は労働義務がないため、実際に取得することはできません。
育児休業以外にも、産前産後休業、介護休業、業務上の傷病による療養休業なども同様に出勤したものとみなされます。
選択肢3:適切
会社が有給休暇の使途を尋ねること自体は違法ではないものの、労働者が有給を自由に利用する権利を侵害しないよう対応しなければなりません。行き過ぎた使途の追求や取得妨害は違法にあたります。
選択肢4:適切
時間単位で年次有給休暇を制度化するためには、労使協定を締結する必要があります。
- 時間単位年休制度の導入手続き
1. 就業規則への記載
2. 労使協定の締結 - 労使協定の内容
労使協定では、以下の事項を定める必要があります。
1. 時間単位年休の対象労働者の範囲
2. 時間単位年休の日数(年5日以内)
3. 時間単位年休1日分の時間数
4. 1時間以外の時間を単位とする場合の時間数
労使協定は、労働者の過半数で組織された労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面によって締結する必要があります。
注意点
- 労使協定書を労働基準監督署へ届け出る必要はありません。
- 労使協定を締結せずに時間単位で有給休暇を付与すると、労働基準法違反となります。
- 時間単位年休は年5日を上限としており、これを超えて取得することはできません。
問25
正解:3
選択肢1:不適切
労働基準法上、労働時間に該当するか否かは、労働契約や就業規則等の定めに関わらず、客観的に判断されます。
労働時間とは、「労働者が企業の指揮命令下にある状態」を指し、会社の仕事や会社からの指示によって作業をしている時間は労働時間として扱われます。
例えば、休憩時間中に電話対応をしている場合、就業規則上は休憩時間であっても、実際には労働時間として扱われることになります。
選択肢2:不適切
所定労働時間外に行われる企業外の研修・教育活動等であっても、状況によっては労働基準法上の労働時間に該当する場合があります。
労働時間の定義は、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされています。
研修・教育活動等が労働時間に該当するかどうかは、以下の要素を考慮して判断されます:
- 参加の義務性:会社から参加を強制されているか、不参加に対して不利益な取り扱いがあるか。
- 業務との関連性:研修内容が業務遂行に必要不可欠であるか。
- 会社からの指示:会社が指定した研修であるか、レポート提出などが求められているか。
- 人事評価への影響:研修参加が昇給や人事査定に影響を与えるか。
選択肢3:適切
警備業務に従事する労働者の仮眠時間は、実際の作業を行っていなくても、警報が鳴った場合に対応する義務がある場合、労働基準法上の労働時間に該当します。
- 労働時間の定義
労働時間とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされています。警報対応の義務がある仮眠時間中は、労働者が使用者の指揮命令下にあると判断されます。 - 判例による解釈
千葉地裁の平成29年5月17日判決では、警備員の仮眠時間について、「労働からの解放が保証されていない仮眠時間・休憩時間」は労働時間に該当すると判断されました。 - 手待ち時間の考え方
仮眠時間中に警報対応の義務がある状態は、「手待ち時間」(使用者の指示があれば直ちに作業に従事しなければならない状態にある時間)と考えられ、労働時間と判断されます。
選択肢4:不適切
飲食店等で、客の来店時の即時対応が義務付けられている場合、客がいない時間であっても、それは労働基準法上の労働時間に該当します。
- 労働時間の定義
労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。客がいない時間でも、従業員は使用者の指示に従って待機している状態にあるため、これは労働時間に該当します。 - 手待時間の概念
客がいない時間は「手待時間」に該当します。 - 判例の解釈
すし処「杉」事件の大阪地裁判決では、客が途切れた時に適宜休憩してもよいという約定であっても、客が来店した際に即時業務に従事しなければならない場合、それは単なる手待時間であり、労働基準法上の休憩時間とは認められないとしています。 - 指揮命令下の状態
客がいない時間でも、従業員は店舗を離れることができず、業務に従事できる状態にあることから、使用者の指揮命令下にあると判断されます。 - 労働時間の客観的判断
労働時間に該当するか否かは、労働契約や就業規則の定めではなく、客観的に労働者が使用者の指揮命令下に置かれているかどうかで判断されます。
国家試験 第28回 解説リンク集
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。