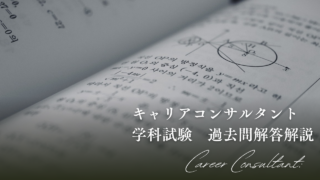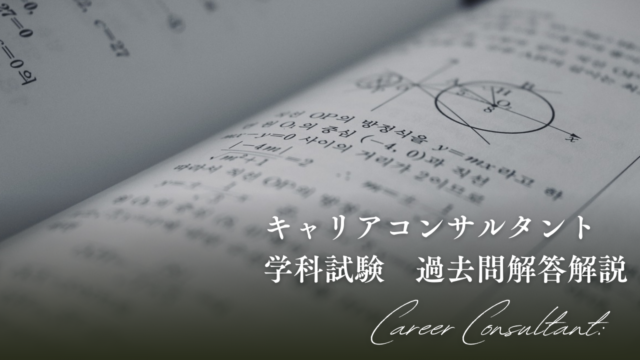第28回 国家資格キャリアコンルタント試験 学科試験 解答解説(問16〜20)
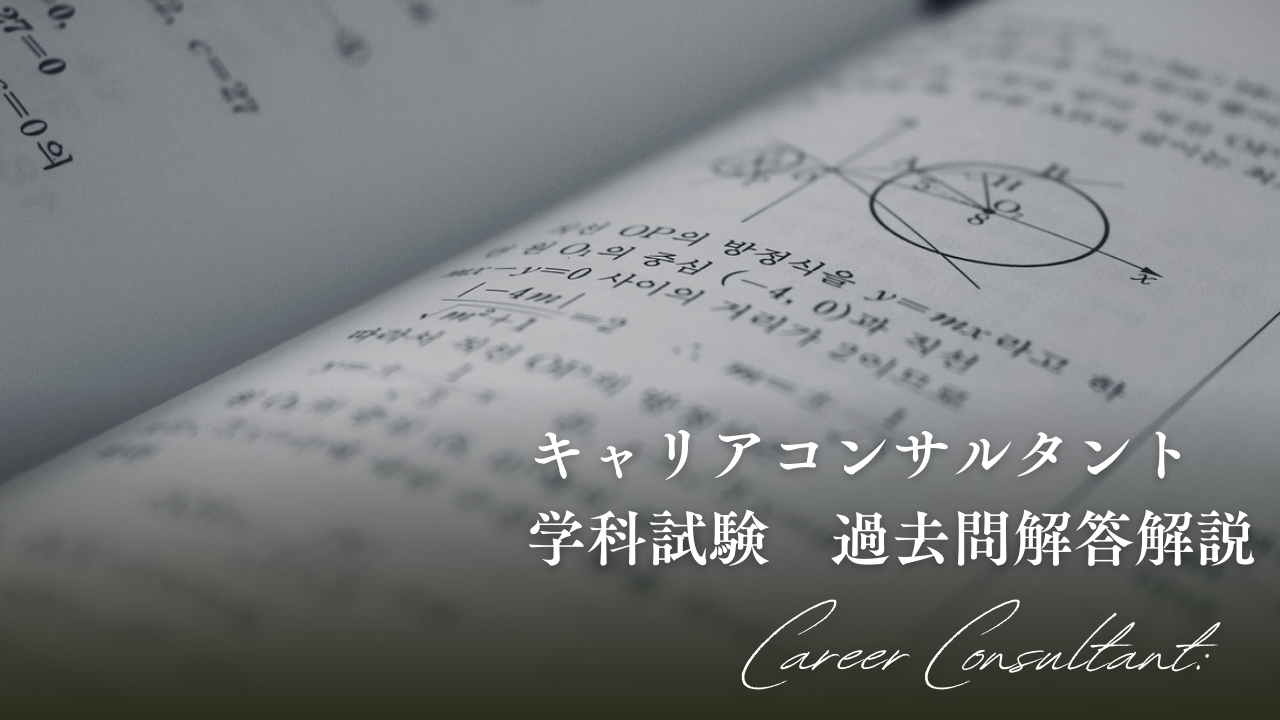
この記事について
令和6年3月実施
第28回 国家資格キャリアコンサルタント試験 解説を作成しました。
過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしています。
問16
正解:4
選択肢1:不適切
求職者訓練の説明となっています。
選択肢2:不適切
離職者訓練の説明となっています。
選択肢3:不適切
求職者支援訓練の実施機関は主に民間教育訓練機関です。
求職者支援訓練の特徴は以下の通りです。
- 実施機関:民間教育訓練機関が厚生労働大臣の認定を受けて実施します。
- 対象者:主に雇用保険を受給できない求職者が対象です。
- 訓練内容:就職に必要な技能及び知識を習得するための職業訓練を提供します。
- 訓練期間:基礎コースは2~4か月、実践コースは3~6か月(一部の特定コースは2か月)です。
- 費用:受講料は原則無料ですが、テキスト代などは自己負担となります。
- 支援内容:訓練期間中および終了後もハローワークが積極的に就職支援を行います。
- 給付金:一定の要件を満たせば、訓練期間中に月10万円の職業訓練受講給付金が支給されます。
なお、国(ポリテクセンター)や都道府県(職業能力開発校)が実施するのは主に公共職業訓練(離職者訓練)であり、求職者支援訓練とは異なります。
高齢・障害・求職者雇用支援機構は、求職者支援訓練の審査・認定や実施機関への指導・助言を行う役割を担っています。
選択肢4:適切
受講料・入学料は原則無料です。ただし訓練期間1年以上の科目では有料のものがあります。
問17
正解:4
<a.本人に責任のない事項の把握>
- 本籍・出生地に関すること (注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します)
- 家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)
- 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)
- 生活環境・家庭環境などに関すること
<b.本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)の把握>
- 宗教に関すること
- 支持政党に関すること
- 人生観、生活信条などに関すること
- 尊敬する人物に関すること
- 思想に関すること
- 労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関すること
- 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
<c.採用選考の方法>
- 身元調査などの実施 (注:「現住所の略図等を提出させること」は生活環境などを把握したり身元調査につながる可能性があります)
- 本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用
- 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
選択肢1:不適切
選択肢2:不適切
選択肢3:不適切
選択肢4:適切
問18
正解:1
選択肢1:適切
人材開発は単なるスキル向上だけでなく、企業の経営戦略を実現し、達成することを目的としています。従って、企業が求める能力と既存の人材が持つ能力のギャップを埋めることは、人材開発の中核的な役割であると言えます。
選択肢2:不適切
OJTの成果は、指導役の能力や経験によって大きく異なります。
選択肢3:不適切
キャリア開発とは、従業員一人ひとりの職務や能力・スキルを中長期的に計画し、継続的に磨いていく取り組みを指します。これは経営幹部、管理職、専門職に限定されるものではなく、全従業員を対象とした包括的なアプローチです。
選択肢4:不適切
CDP(キャリア・ディベロップメント・プログラム)は、Off-JTによる研修等のメニューを含むものの、それだけに限定されるものではありません。
CDPの正確な定義は以下の通り。
1. 中長期的な視点:CDPは従業員のキャリアや能力を開発するための中長期的な計画です。
2. 包括的なアプローチ:CDPには以下のような要素が含まれます。
教育研修(Off-JTを含む)
OJT(職場内訓練)
人事異動やジョブローテーション
キャリアビジョンの策定
社内外の自己啓発支援
3. 個人と組織のニーズの調和:CDPは従業員の希望や適性と、企業が期待する人材イメージの両方を考慮して策定されます。
4. 多様な施策:研修だけでなく、キャリア面談、FA制度、社内公募制度など、様々な人事施策が含まれます。
5. 継続的な見直し:定期的なフィードバックと評価を通じて、CDPは必要に応じて修正や見直しが行われます。
問19
正解:4
選択肢1:適切
正しい
選択肢2:適切
正しい
選択肢3:適切
正しい
選択肢4:不適切
副業・兼業に関する裁判例においては、就業規則において労働者が副業・兼業を行う際に許可等の手続を求め、これへの違反を懲戒事由としている場合において、形式的に就業規則の規定に抵触したとしても、職場秩序に影響せず、使用者に対する労務提供に支障を生ぜしめない程度・態様のものは、禁止違反に当たらないとし、懲戒処分を認めていない。
このため、労働者の副業・兼業が形式的に就業規則の規定に抵触する場合であっても、懲戒処分を行うか否かについては、職場秩序に影響が及んだか否か等の実質的な要素を考慮した上で、あくまでも慎重に判断することが考えられる。
問20
正解:2
選択肢1:不適切
- 2013年729万人 2023年639万人
- 2013年以降、自営業主・家族従業者数は全体的に減少傾向にあります。
選択肢2:適切
- 2013年55.8%、2023年53.2%
- 2013年以降、女性の非正規雇用割合は全体的に減少傾向にあります。
- 2023年時点でも、女性の非正規雇用労働者の割合は53.2%と、依然として5割を超えています。
選択肢3:不適切
高齢者の就業率の推移
- 2013年20.1%、2023年25.2%
- 2013年以降、65歳以上の高齢者の就業率は上昇傾向にあります。
- 2023年の65歳以上の就業率は25.2%となり、前年と同率でした。
- 2013年から2023年の10年間で、65歳以上の就業率は約5.1ポイント上昇しています。
年齢階級別の就業率
- 65~69歳の就業率は特に顕著な上昇を示しており、2023年には52.0%と過去最高を記録しました。
- 70~74歳の就業率も34.0%、75歳以上は11.4%と、いずれも過去最高となっています。
選択肢4:不適切
- 役員を除く雇用者を雇用契約期間別にみると、無期の契約は 2023 年平均で 3784 万人と、13万人の増加、有期の契約は 1443 万人と 14 万人の増加となった。
- 男女別にみると、男性は、無期の契約が 2195 万人と8万人の減少、有期の契約が 615 万人と12 万人の増加、女性は、無期の契約が 1589 万人と 22 万人の増加、有期の契約が 827 万人と前年と同数となった。
国家試験 第28回 解説リンク集
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。