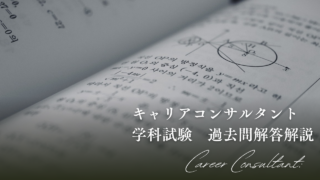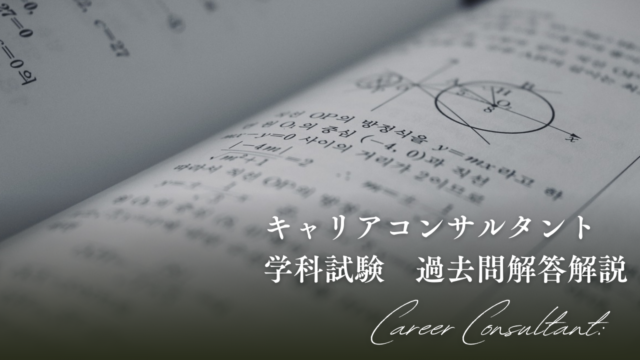第29回 国家資格キャリアコンルタント試験 学科試験 解答(問16〜20)
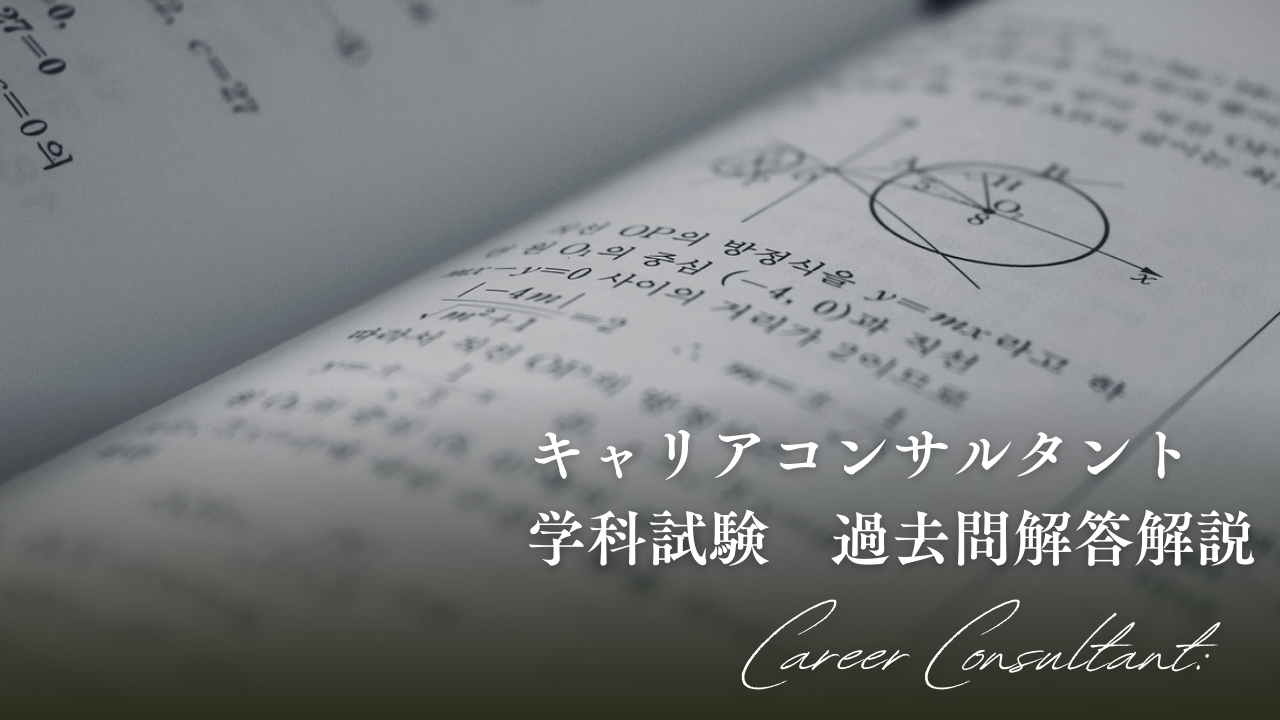
この記事について
第29回 国家資格キャリアコンサルタント試験 解説を作成しました。
過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしていこうと思います。
問16
正解:2
選択肢1:不適切
キャリアアップ助成金は、主に「非正規雇用労働者(有期契約、短時間、派遣等)」の「正社員化」や「処遇改善(賃金アップ、福利厚生の向上等)」を促進するため、これらの取組みをした事業主に助成する制度です。「正社員の処遇改善」だけを対象とするものではありません。
選択肢2:適切
このコースの中には海外大学院等でIT・デジタル・経営(一定条件あり)に関する高度人材育成プログラムも助成対象となる場合があります(講座やプログラムの個別要件による)。
成長分野等人材訓練の場合、次のいずれかの訓練であること
①大学院の正規課程、科目等履修制度、履修証明制度による訓練
※ 修士・博士課程問わず対象となります。 ※ 国内の大学院の場合、分野は問いません。
②海外の大学院により実施される訓練
※ 「デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革に関連する分野(情報科学・情報工学およびそれに関連する分野)」や 「クリーンエネルギー、バイオ、宇宙等の先端技術やイノベーションに関わる分野(理工学)」、 「経営の分野であって支給要領の別紙に定めるもの」のいずれかに関連するものであることが必要です。
選択肢3:不適切
トライアル雇用助成金と他の助成金(例:キャリアアップ助成金等)は、要件を満たせば併用できる場合があります。
選択肢4:不適切
育児休業を取得しやすい雇用環境整備などを行い、男性労働者が育児休業を取得した場合に 受給できる助成金です。
女性の取得のみでは助成の対象になりません。
問17
正解:1
選択肢1:適切
「セルフ・キャリアドック導入の方針と展開」には、キャリアコンサルタントが相談を通じて法令違反やハラスメント等の組織的な課題を把握した場合、「原則として相談者本人の同意を得て企業側(人事部門など)へ伝える」と明記されています。個人情報の守秘義務と組織的安全確保のバランスを取る姿勢が求められます。
選択肢2:不適切
責任者は「人材育成に関して社内に影響力のある者」が望ましいものの、「人事部門から選定しなければならない」とはされていません。「人事部門に限らず幅広いポストから適任者を選ぶことも検討すべき」とされています。
選択肢3:不適切
キャリア研修の属性混在にはメリットもありますが、混在で実施「すべき」とはされていません。役割や年齢の節目ごと、あるいは選抜型など状況に応じて対象者を絞る方法も有効であり、必ずしも「混在」前提ではありません。
選択肢4:不適切
公式ガイドラインでは「45~60分程度」かけて実施するのが標準的とされており、30分未満に短縮すべきとはされていません。短すぎる面談は十分な効果が得られません。
問18
正解:4
選択肢1:適切
令和5年度調査で男性の育児休業取得率は30.1%と初めて3割を超え、前年(17.13%)から約13ポイントの大きな上昇で、過去最高の伸び幅でした。
選択肢2:適切
最新調査では有期契約労働者の男性の育児休業取得率は26.9%で、前年(8.6%前後)からも大きく向上しており、長期的に見て全体として増加傾向にあることが確認できます。
選択肢3:適切
平成30年度には「2週間未満」は70%以上を占めていましたが、令和5年度は約37.7%に減少しており、およそ半減しています。
令和5年度雇用均等基本調査 (P21)
選択肢4:不適切
最新の調査では、「1ヶ月~3ヶ月未満」が28.0%で最も多く、「3ヶ月~6ヶ月未満」が最多ではありません。
育児休業の取得期間 令和4年4月1日から令和5年3月 31 日までの1年間に育児休業(産後パパ育休を含 む。)を終了し、復職した女性の育児休業期間は
「12 か月~18 か月未満」が 32.7% (令和3年度 34.0%)と最も高く、
次いで「10 か月~12 か月未満」が 30.9%(同 30.0%)、「8 か月~10 か月未満」11.4%(同 8.7%)の順となっている。
一方、男性は
「1 か月~3か月未満」が 28.0%(令和3年度 24.5%)と最も高く、
次いで「5日~2週間未満」が 22.0%(同 26.5%)、「2週間~1か月未満」が 20.4% (同 13.2%)となっており、2週間以上取得する割合が上昇している。
問19
正解:1
選択肢1:適切
2022年の日本の失業率は2.6%であり、アメリカ(3.6%)、イギリス(約3.7%)、カナダ(5.3%)、フランス(約7.3%)と比べても最も低い水準でした。
選択肢2:不適切
通常、日本でも他の国と同様、若年層ほど失業率が高くなる傾向があります。2022年も15~24歳の失業率が25~34歳より明らかに高いです。
選択肢3:不適切
2005年以降、日本の長期失業者割合はアメリカよりも高い時期が続いています。
各国ごとに統計上の失業者の定義が異なるため厳密な比較はできないが、失業期間が1年以上の長期
失業者の割合をみると、2023年はイタリアが56.0%と半数超となっているほか、日本が33.5%、ドイツが
30.5%、フランスが24.5%、イギリス21.5%などとなっている。
背景には、コロナ禍の影響、各国の経済成長率の差異等の景気動向のほか、雇用慣行や政策制度面で
の差異など構造的な要因も影響していると考えられる。
データブック国際労働比較2025|労働政策研究・研修機構 (JILPT)
選択肢4:不適切
2021年の日本の完全失業率は約2.8%で4%を超えたことはありません。また、2023年以降も2.5〜2.6%台で推移しており2%を下回ってはいません。(令和5年は2.6%、令和6年は2.5%)
問20
正解:1
選択肢1:適切
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」等によれば、2010年代以降、日本の男女間賃金格差は長期的に縮小傾向にあります。例として2022年は、男性の賃金を100とした場合の女性の賃金が75.7と、過去最少を記録し、年々差が縮まっています。
選択肢2:不適切
2022年の実データでは、「正社員・正職員=100」としたときの「正社員・正職員以外」の賃金水準は、男性で68.8、女性で71.5と女性の方が格差が小さいです。つまり、男性の方が雇用形態間格差は「大きい」。
選択肢3:不適切
2021年の日本のフルタイム労働者の男女賃金格差は約22.1%(女性は男性の77.9%)、アメリカは16.9%(女性は男性の83.1%)であり、日本の方が「格差が大きい」です。
選択肢4:不適切
2022年統計では、女性の月額賃金は大企業278,200円、中企業257,000円、小企業241,300円とはっきり企業規模の差異が存在します。
国家試験 第29回 解説リンク集
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。