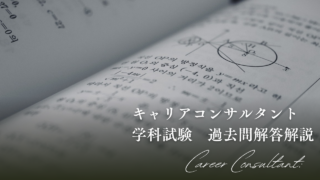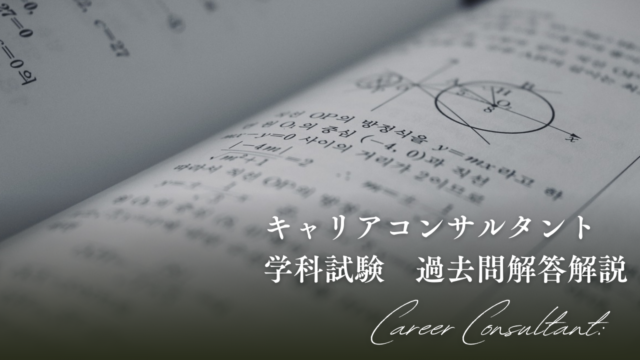第29回 国家資格キャリアコンルタント試験 学科試験 解答(問21〜25)
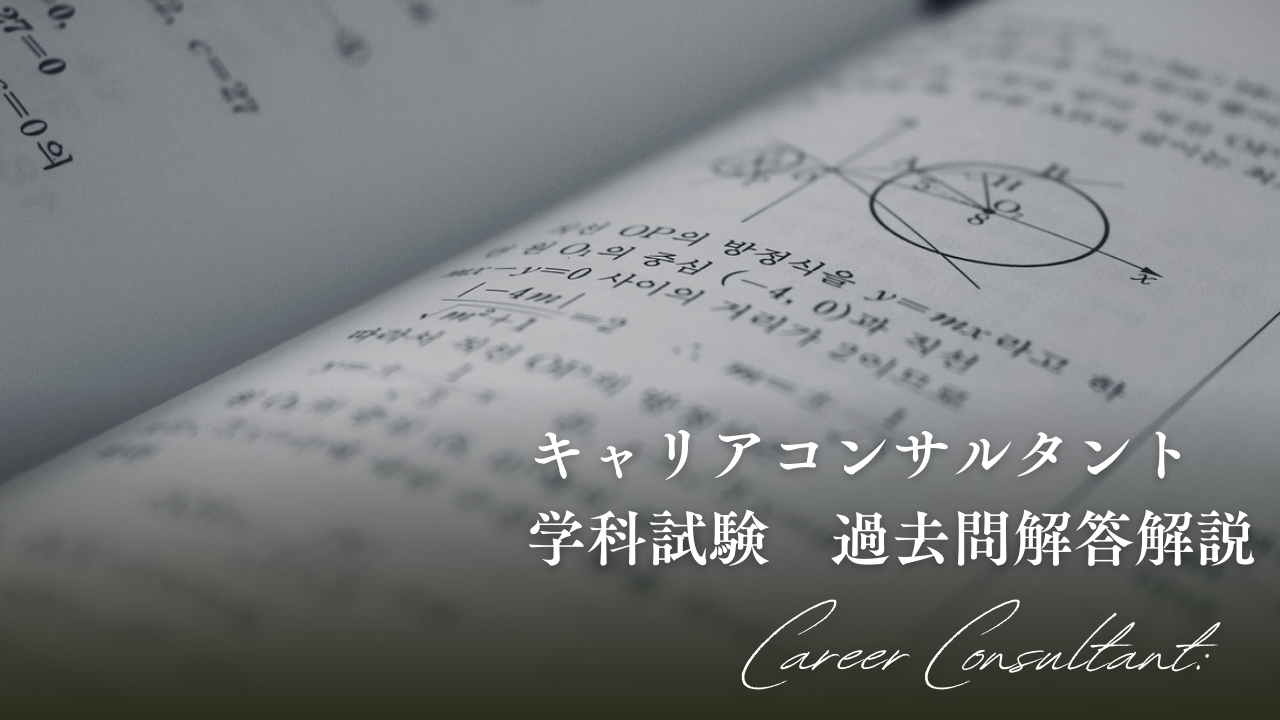
この記事について
第29回 国家資格キャリアコンサルタント試験 解説を作成しました。
過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしていこうと思います。
問21
正解:1
選択肢1:適切
就業希望のない無業者は約3,000万人と非常に多く、就業希望はあるが求職活動をしていない無業者は約460万人であるため、人数は就業希望のない無業者の方が多い。
最も人数の多い①就業希望のない無業者(在学者を除く。)についてみてみる2022年時点で約3,000万人近くが無業者であり、年齢に限らず総じて女性が多い。
年齢別にみると、男女合わせて、60~69歳が440万人、70歳以上が2,100万人と大半を占めているが、59歳以下でも350万人ほどとなっている。
就業を希望しない理由としては、「病気・けが・高齢のため」が、男女ともに60~69歳の5割弱、70歳以上の8割強と最も多い。
無業者が就業を希望しない理由は、病気・けがや年齢が多いが、単に高齢であるからといって就業の希望をあきらめることとなっているのであれば、高齢化が進む我が国社会においては大きな損失である。
作業内容の工夫や機器の活用を促す10など、年齢にかかわ らず働くことができる社会づくりを進めていく必要がある。
選択肢2:不適切
59歳以下で「出産・育児・介護・看護・家事のため」に就業希望のない無業者は女性の約4割(約100万人)であり、男女ともにではない。
59歳以下の女性の約4割に当たる約100万人が、「出産・育児・介護・看護・家事 のため」に無業かつ就業希望なしとなっているが、同年代の男性は僅かにとどまる。
育児や家事、介護の負担が女性に偏っていることが、女性の就労への希望を失わせている可能性が示唆される。
育児・介護などの負担の軽減に向けた社会的支援を進めるとともに、男性が家庭内での責任を果たせるよう、柔軟な労働時間や休暇の取得促進など職場における環境づくりも重要となる。
選択肢3:不適切
最も多い理由は「病気・けが・高齢のため」であり、「希望する仕事がありそうにない」はそれよりも少数。
就業希望はあるが求職活動を行っていない無業者についてみてみる。
就業希望があるものの求職活動を行っていない無業者は約460万人となっている。
年齢別にみると、59歳以下が多く、女性は200万人近くに及ぶ。
求職活動を行っていない理由をみると、「病気・けが・高齢のため」が、高年齢層を中心に多く、男性では60万人程度、 女性では70万人程度である。
「出産・育児・介護・看護のため」は59歳以下の女性が60万人程度と最も多い。
また、これらに比べると数は少ないものの、「仕事を探したが見つからなかった」「希望する仕事がありそうにない」「知識・能力に自信がない」と回答した者も男女・年齢階級別にそれぞれ数万人程度となっている。
ハローワークでのマッチングにおける丁寧な相談支援、公的職業訓練などのリ・スキリングの支援を通じて、就業希望を求職活動につなげていくことが重要となるだろう
選択肢4:不適切
就業希望はあるが求職活動をしていない無業者は年齢別には59歳以下の人数が多い。
問22
正解:2
選択肢1:適切
2022年4月の法改正により、妊娠・出産の申し出をした労働者に対して事業主は育児休業制度等の個別周知と取得意向の確認を必ず行う義務があります。
選択肢2:不適切
2022年4月の法改正により、有期雇用労働者の取得要件としてあった「引き続き1年以上の雇用期間」が削除され、契約期間の要件は「子が1歳6ヶ月または2歳まで育児休業を取得する場合に、労働契約の期間が満了する日が明らかでないこと」など条件が変更されました。
選択肢3:適切
出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に最大4週間まで取得可能で、2回まで分割取得も認められています。
選択肢4:適切
2022年10月の法改正により、育児休業は子が1歳になるまでに2回まで分割して取得可能となりました。
問23
正解:2
選択肢1:不適切
公正な採用選考では、応募者の基本的人権を尊重し、職務に関係のない思想・信条に関わる質問(特定政党の支持など)は差別や不当な選考につながるため禁止されています。
選択肢2:適切
面接で職務に直接関係する適性や能力を評価するための質問は、公正な採用選考の範囲内です。問題解決能力を問う質問は職務適性の評価に資するため適切です。
選択肢3:不適切
男女雇用機会均等法は、募集や採用時の情報提供を男女で異なる扱いをすることを禁止しています。男女平等に同じ情報を提供することが求められます。
選択肢4:不適切
合理的な理由がない限り、身長・体重・体力要件を採用基準に含めることは、性別などに基づく間接差別となる可能性があります。これらの要件は必要性と合理性を慎重に判断しなければなりません。
問24
正解:1
選択肢1:適切
労働基準法第38条及び行政解釈では、労働者が複数の事業主のもとで働く場合でも、法定労働時間や時間外労働時間の取扱いのために労働時間は通算して計算される必要があります。複数の会社で働く兼業・副業者の労働時間も合算して管理されなければならず、労働時間が長くなり過ぎることを防止する目的があります。
選択肢2:不適切
労働基準法第34条により、休憩時間は労働時間が6時間を超える場合に45分以上、8時間を超える場合に1時間以上と定められています。12時間労働の場合に2時間の休憩を義務付ける規定はありません。
選択肢3:不適切
36協定は労働組合との締結・届出によって成立しますが、その効力は組合員に限定されず、事業場の全労働者に及びます。非組合員であっても時間外労働の管理は36協定の適用範囲内です。
選択肢4:不適切
労働基準法第35条は「毎週少なくとも1日の休日を与える」か「4週間を通じて4日以上の休日を与える」ことを義務付けています。4週間単位で4日以上休日を与える変形休日制は認められています。
問25
正解:4
選択肢1:適切
派遣労働者の待遇確保のため、派遣元事業主は派遣先の比較対象労働者との均等・均衡待遇方式か、派遣元における労使協定方式のいずれかにより待遇を確保することが法律で義務付けられています。
選択肢2:適切
グループ企業内派遣は、派遣元事業主のグループ企業への派遣割合が総労働時間ベースで8割以下と制限されており、不当な労働条件の切り下げ等の防止が図られています。
選択肢3:適切
離職後1年以内の同一企業への派遣労働者としての受け入れは禁止されており、ただし60歳以上の定年退職者など一定の例外は認められています。
選択肢4:不適切
紹介予定派遣の場合は、派遣就業開始前に派遣先による事前面接や履歴書提出が認められています。事前面接禁止の規定は一般の派遣労働者受け入れの場合であり、紹介予定派遣は例外として扱われます。
※紹介予定派遣の場合は、派遣先が派遣労働者を直接雇用する可能性があるので、特別に「事前に面接したり履歴書を見せてもらったりすること」が認められています。これは、将来その人を社員として採用するために、仲良く仕事ができるか、スキルが合っているかをちゃんと確かめるためです。
普通の派遣だと、派遣先が面接をしたり履歴書を求めたりすることは法律で原則禁止されています。なぜなら、派遣労働者は派遣会社と雇用契約を結んでいて、派遣先が選んだり決めたりする立場ではないからです。
でも紹介予定派遣は、派遣期間の後に派遣先と働く人が「このまま正式に雇ってほしい」「ここで働きたい」と合意すれば、直にその会社の社員になれる仕組みです。そのため、派遣先は事前に面接や履歴書を使って、その人が合いそうかどうかを調べることが法律で許されています。
簡単に言うと、
- 普通の派遣は、派遣先が「面接するのは禁止」だけど、
- 紹介予定派遣は、「将来社員にするか決めるための面接や履歴書提出はOK」
という違いがある、ということです。
だから「紹介予定派遣は例外で、事前面接や履歴書提出が認められている」と覚えればわかりやすいです。
国家試験 第29回 解説リンク集
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。