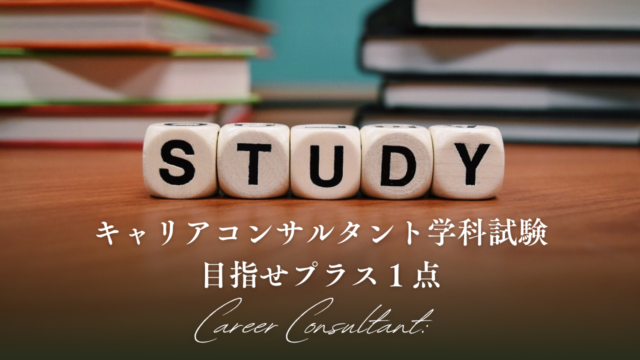現実療法
shasha
/

この記事について
現実療法について知識が足らなかったので調べてみました。
現実療法の概要
現実療法(リアリティ・セラピー、Reality Therapy)は、アメリカの精神科医ウィリアム・グラッサー(William Glasser, 1925–2013)によって1960年代に提唱された心理療法・カウンセリングのアプローチです。
従来の精神分析や医療モデルと異なり、「過去」や「無意識」ではなく「現在」に焦点を当て、クライエントが現実的で責任ある行動を選択できるよう支援する点が特徴です。
理論的基盤:選択理論
現実療法の基盤となるのが「選択理論(Choice Theory)」です。選択理論では、人間の行動は外部から動機づけられるのではなく、生存・愛と所属・力・自由・楽しみという5つの基本的欲求を満たすために「内側から動機づけられている」と考えます。
5つの基本的欲求
| 欲求 | 内容例 |
|---|---|
| 生存 | 飲食、睡眠、安全、健康 |
| 愛・所属 | 愛されたい、仲間とつながりたい |
| 力 | 認められたい、達成したい、貢献したい |
| 自由 | 自分らしくありたい、選択したい、変化を求めたい |
| 楽しみ | 新しい体験、学び、ユーモア、好奇心 |
これらの欲求を満たすために、人は「上質世界(Quality World)」という自分にとって大切な人・物・信条のイメージを持ち、その実現を目指して行動します。
現実療法の特徴と進め方
- 現在の問題や人間関係に焦点を当てる
過去の出来事や原因探しではなく、「今、何が問題か」「どうしたいのか」に注目します。 - 自己評価と行動の選択
クライエントが「自分が本当に望んでいること」「今の行動がその実現に役立っているか」を自己評価し、より良い行動を自ら選択できるように支援します。 - 責任と現実的な計画
クライエントが自分の行動に責任を持ち、現実的で実行可能な計画を立てて実践することを重視します。 - 温かく信頼できるカウンセリング関係
カウンセラーは非難や批判をせず、ラポール(信頼関係)を築きながら、クライエントの自己決定を尊重します。
カウンセリングの主な流れ
- ラポールの確立(信頼関係の構築)
- 願望・欲求の明確化(何を望んでいるか、どんな人間関係を築きたいか)
- 現在の行動の評価(今の行動が欲求充足に役立っているか)
- 計画の立案と実行(より良い行動の選択と実行)
- フォローアップ(実行の確認と継続的な支援)
適用範囲・効果
- 精神科治療、犯罪矯正、薬物依存、家族・夫婦関係、教育現場、職場のマネジメントなど幅広い領域で活用されています。
- 年齢や知的レベル、症状の有無にかかわらず、多様な人に適用可能です。
他の療法との違い
- 過去より現在重視:精神分析などが過去や無意識に焦点を当てるのに対し、現実療法は「今ここ」に焦点を当てます。
- 自己決定・責任:クライエント自身が行動を選択し、その結果に責任を持つことを重視します。
- 内発的動機づけ:外的な報酬や罰ではなく、内側からの動機づけによる行動変容を目指します。
まとめ
現実療法は、「今ここ」の現実的な問題や人間関係に焦点を当て、クライエントが自分の欲求を満たすために責任ある行動を自ら選択できるよう支援する心理療法です。
その理論的基盤である選択理論は、教育・企業・家庭など多様な分野で応用されています。
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いします。ブログ運営の励みになります。