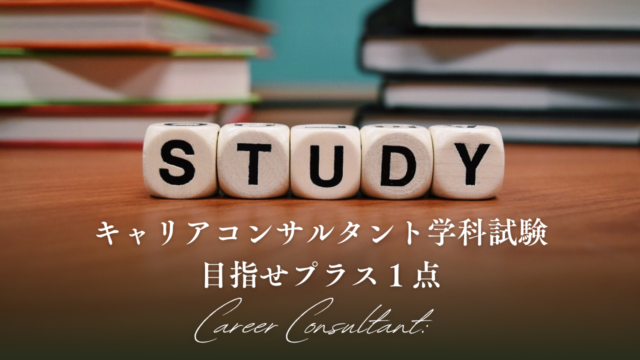内観療法

この記事について
たまに出てくる内観療法について詳しく調べてみました。
内観療法とは
内観療法(ないかんりょうほう)は、日本独自の精神療法であり、1940年代に吉本伊信(よしもと いしん)によって開発されました。
もともとは浄土真宗の修行法「身調べ」を基にした自己洞察法「内観」を、1960年代から医療や心理療法として応用したものです。
基本的な考え方と特徴
- 自己洞察を深めることを目的とし、症状や問題行動そのものには直接焦点を当てず、患者の固定化した視点を転換させることで、認知や行動、生き方に変化をもたらします。
- 治療の結果、精神症状や身体症状の改善だけでなく、行動や生活全体の質的転換が期待できます。
- 宗教色を排除し、心理療法としての有効性を重視して体系化されています。
集中内観
内観療法の中心は「集中内観」と呼ばれる1週間の合宿形式です。
参加者は和室を屏風で区切った個別スペースにこもり、外部刺激を遮断した静かな環境で朝6時から夜9時まで内観作業を続けます。
内観の3項目に沿って、過去を3~5年ごとに区切りながら、身近な人(母、父、配偶者、兄弟姉妹、恩師、友人など)について振り返ります。
- していただいたこと(自分が相手から受けた恩恵)
- して返したこと(自分が相手に返したこと)
- ご迷惑をかけたこと(自分が相手に迷惑をかけたこと)
1~2時間ごとに面接者(指導者)が訪れ、3~5分間の面接で内観内容を報告し、次のテーマを与えられます。
日常内観
集中内観終了後は、日常生活の中で短時間「日常内観」を行い、内観の効果を持続・深化させます。
治療効果・適用範囲
アルコール依存、薬物依存、神経症、心身症、不登校、摂食障害、非行、家庭内暴力、社交不安障害、愛着障害など、人間関係に起因する幅広い問題に効果があるとされています。
内観療法の効果は「反省→懺悔→感謝→報恩」という内的変化にあり、自己中心性からの脱却や他者への信頼感の回復、肯定的な自他認知の促進が期待されます。
再犯率の低下や心の健康度向上など、社会的にも高い効果が報告されています。
他の心理療法との違い
内観療法は「症状不問」で、症状そのものよりも自己洞察と人間関係の再認識を重視します。
治療構造が堅固であり、礼節を重んじた距離感のある治療関係が特徴です。
マインドフルネス療法との類似性も指摘されますが、内観療法はより「他者との関係性」に焦点を当てています。
歴史と普及
- 1937年:吉本伊信が「身調べ」の普及を開始
- 1953年:内観道場を開設
- 1957年:奈良少年刑務所で矯正プログラムに採用
- 1968年:内観3項目が確立
- 1978年:内観学会(現・日本内観学会)発足
- 1991年:第1回国際内観会議開催
- 現在は医療、矯正、教育、企業など多分野で活用され、国際的にも評価されています。
まとめ
内観療法は、日本発の自己洞察を深める心理療法であり、特に人間関係に悩む人や自己中心性から脱却したい人に有効です。
集中内観や日常内観を通じて、過去の自分の行動を見つめ直し、感謝や報恩の気持ちを育むことで、心の安定や行動変容を促します。
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いします。ブログ運営の励みになります。