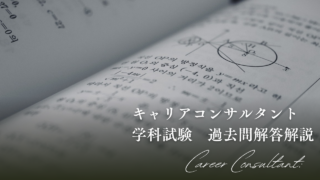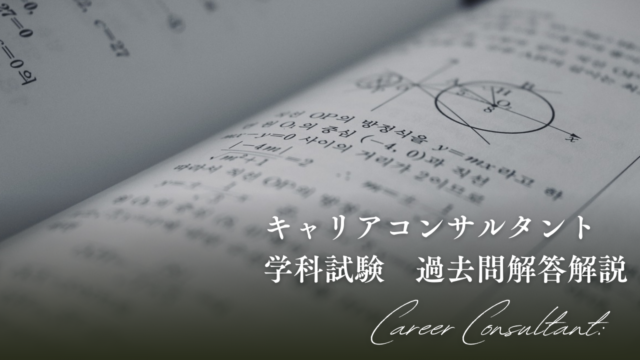第25回 国家資格キャリアコンルタント試験 学科試験 解答解説(問6〜10)
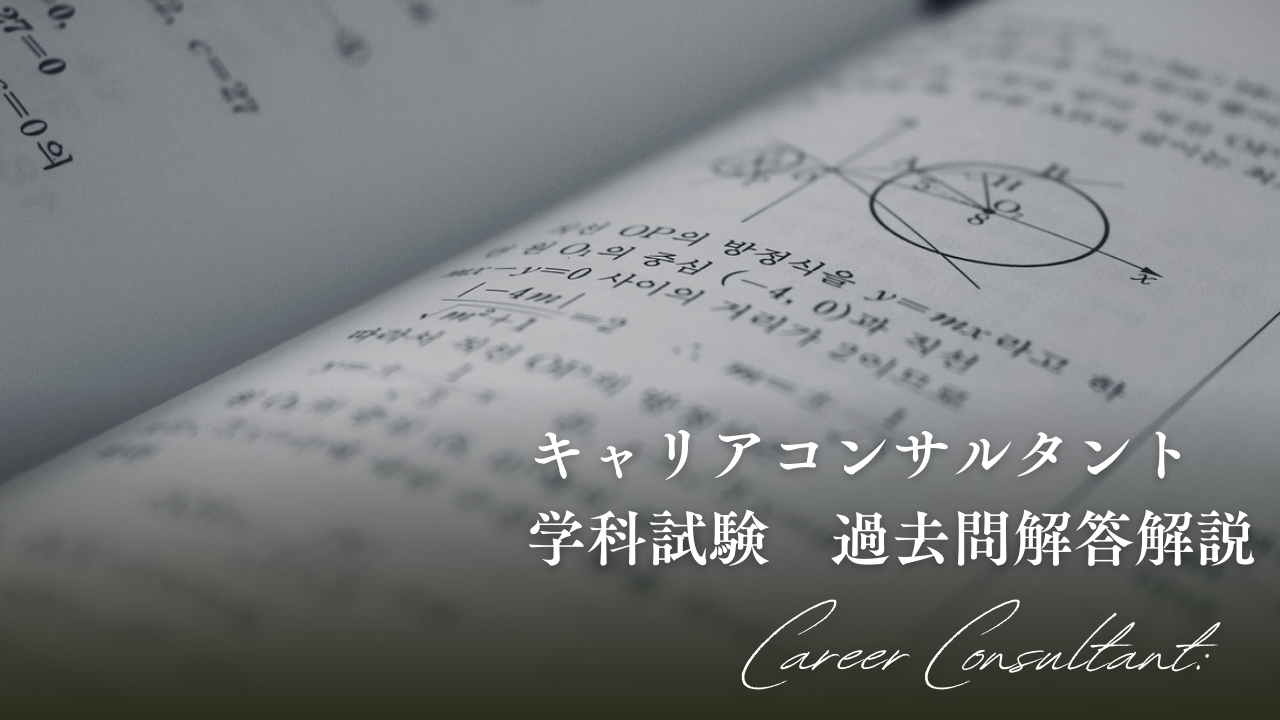
この記事について
第25回 国家資格キャリアコンサルタント試験解説を作成しました。
過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしています。
問6
正解:2
選択肢1:適切
ジェラットは、教育現場におけるガイダンスの際の枠組み構築を目的として、意思決定論的アプローチの立場からキャリア発達における意思決定の仕方を提供するための理論を展開しました
選択肢2:不適切。
ジェラットの連続的意思決定プロセスは、「予測システム」、「価値システム」、「決定システム」の3段階から構成されています。「経験システム」という概念は無い。
選択肢3:適切
探索的意思決定は、環境の不確実性を減らすために新しい選択肢を試みるプロセスであり、特に変化が激しい状況では、常に新しい情報が得られるため、固定的な最終決定を下すことが難しい場合があります。
選択肢4:適切
不確実性を前向きに捉え、新たな意思決定を行うための重要な考え方です。
問7
正解:4
選択肢1:不適切
個人の状況、自己、周囲の援助、戦略は、シュロスバーグの4Sの概念
選択肢2:不適切
シュロスバーグの転機理論では、転機とは「何らかの出来事または非出来事によって関係、日常、仮定、役割が変化すること」と定義されています。
彼女は転機を、予期した出来事(anticipated transitions)と予期していなかった出来事(unanticipated transitions)、非出来事(non-events)の3つに分類しました。
予期した出来事(Anticipated Transitions):予測可能な出来事
- 例えば、大学卒業や結婚。
予期していなかった出来事(Unanticipated Transitions):予測できない出来事
- 例えば、突然の離婚や病気。
非出来事(Non-Events):予期していた出来事が起こらなかった場合
- 例えば、結婚が実現しなかったこと。
選択肢3:不適切
ジェラット(Gelatt, H. B.)は、「連続的意思決定理論」ではなく、「積極的不確実性」という概念を中心に、変化の激しい環境下での意思決定の枠組みを提示しました。
選択肢4:適切
サビカスは、安定性から機動性へと働き方が変わりつつある状況を考察し、キャリア・アダプタビリティを提唱しました。
彼は、キャリア・アダプタビリティを、個人が予測可能なタスクや予測不可能な変化に対応するための準備状態や資源として定義しています。
キャリア・アダプタビリティは、関心(concern)、統制(control)、好奇心(curiosity)、自信(confidence)の4つの次元から成り立っています。
問8
正解:1
選択肢1:適切
合理化は、個人が自分の行動や決定を正当化するために、もっともらしい理由を創作する心理的防御機構です。これにより、個人は自分の行動が正しいと信じることで、罪悪感や不安を軽減しようとします。
選択肢2:不適切
抑圧された欲求や衝動が、社会的、文化的に承認される価値のある好ましい活動となって発現することを、昇華というのが正しいです。
補償は、個人が自分の弱さや不満を他の分野での成果や行動で補う心理的防御機構です。
選択肢3:不適切
同一視(同一化)とは、自分にない優れた能力や名声を持つ他者を真似て自分を近づけることで、自己評価を高めたり、劣等感やコンプレックスから逃れようとする心理的防衛機構です。
一方、自分の社会的に望ましくない感情を相手に押し付けることを投影(投射)と呼びます。これは、受け入れがたい自分の感情を他人に押し付ける防衛機構です
選択肢4:不適切
反動形成とは、受け入れがたい感情や欲求に対して、本心とは反対の行動や態度を取る防衛機構です。これにより、個人は受け入れがたい感情を意識化しないようにします。
一方、ある対象の考え方や感情、行動を無意識に取り入れ、その対象と同じような傾向を示すことを同一視(同一化)と呼びます。これは、他者に自分を重ね合わせることで、自己評価を高めたり、安心感を得る心理的防衛機構です。
問9
正解:3
選択肢1:適切
自由連想法は、クライエントが頭に浮かんだことをありのままに話させる方法で、カウンセラーは非指示的に援助します。
選択肢2:適切
抵抗分析は、抑圧された欲求を意識化する過程で示される抵抗の原因を分析し、抑圧や防衛機制を明らかにすることを指します。
選択肢3:不適切
転移とは、クライエントが過去の重要な人物に対して抱いた感情や態度を、カウンセラーに対して投影することを指します。
一方、逆転移とは、治療者や援助者がクライアントや患者に対して無意識的に自分の感情や過去の経験を向けてしまう現象を指します。
選択肢4:適切
カタルシス効果は、抑圧されていた感情体験が解放されることを指します
問10
正解:1
選択肢1:適正
スキナーは、行動を形成する要因として環境や社会的条件を重視し、行動修正や行動療法の基礎を築きました。
選択肢2:不適切
森田療法は、森田正馬によって開発され、主に日本の精神療法に根ざしています。
内観療法は吉本伊信によって開発されました。彼は浄土真宗の修行法「見調べ」を基に、自己の内面を探求する方法を現代化しました。
選択肢3:不適切
ゲーム分析はエリック・バーンによって提唱されました。彼は交流分析を通じて、人間関係における「ゲーム」の概念を理論化しました。
選択肢4:不適切
エンプティーチェアテクニックは、ジェイコブ・レヴィ・モレノによって最初に開発され、後にゲシュタルト療法で広く用いられるようになりました。
ゲシュタルト療法ではフリッツ・パールズがこの技法を普及させました。
国家試験 第25回 問1〜50解説リンク集
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。