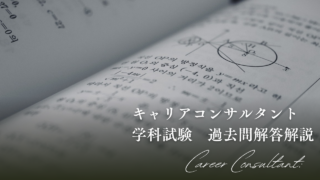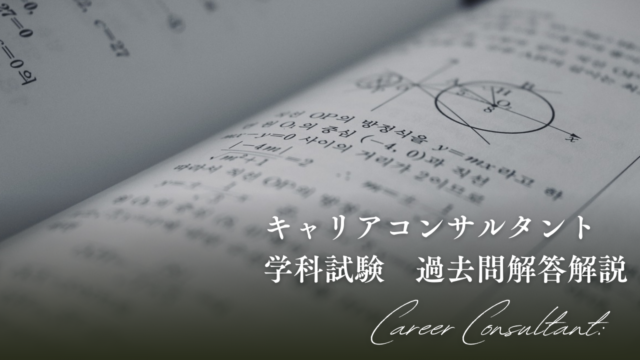第29回 国家資格キャリアコンルタント試験 学科試験 解答(問41〜45)
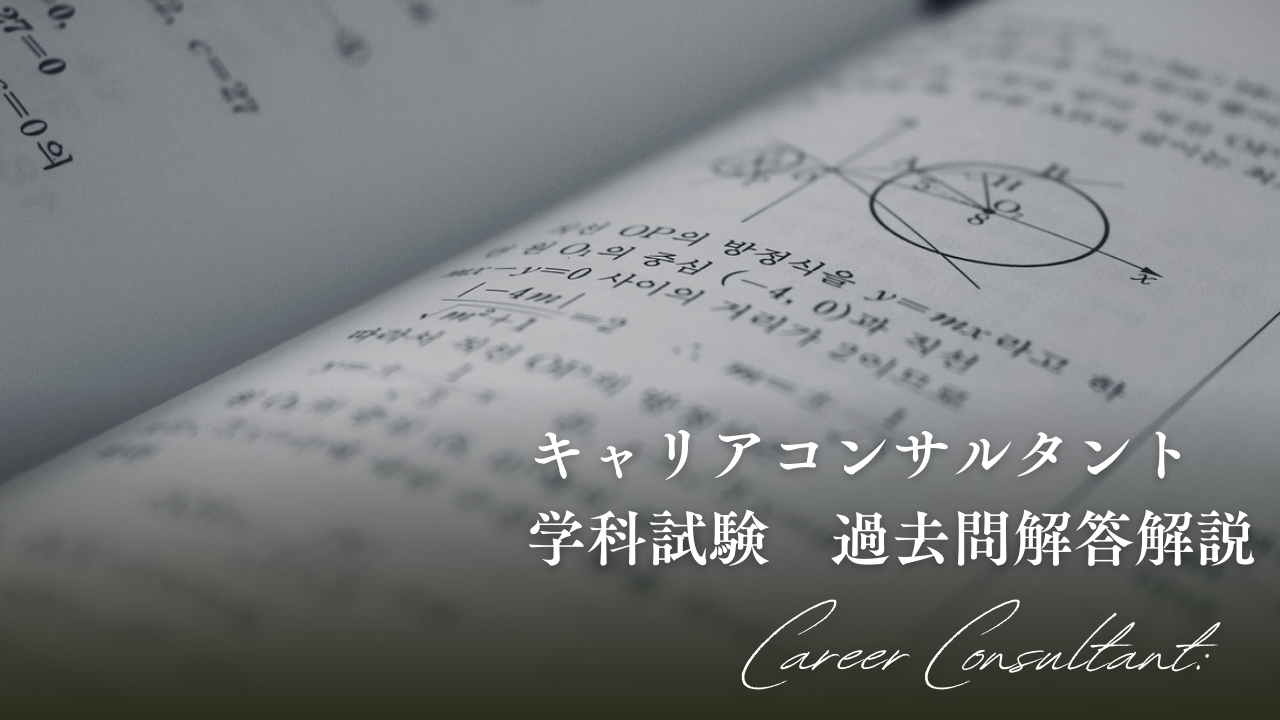
この記事について
第29回 国家資格キャリアコンサルタント試験 解説を作成しました。
過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしていこうと思います。
問41
正解:2
選択肢1:不適切
job tagには職業情報だけでなく、相談者の適性や興味を把握するための自己診断ツール(職業興味検査、価値観検査、職業適性テストなど)も複数無料で掲載されています。
選択肢2:適切
job tagは500を超える職業情報を詳細に掲載し、仕事内容、必要なスキル、労働条件などが文章と動画で分かりやすく解説されています。相談者が自分で主体的に職業理解を深め、職業選択の支援に役立つツールです。
選択肢3:不適切
job tag自体には求人情報は掲載されていませんが、連携しているハローワークインターネットサービスの求人情報を検索できる機能はあります。しかし、求人への直接連絡機能はありません。
選択肢4:不適切
job tagは職業経験の有無を問わず、多くの職業情報や診断ツールが利用可能であり、大学生のキャリア教育やキャリア支援にも十分活用できます。
問42
| 職場体験の教育的意義 |
| 望ましい勤労観、職業観の育成学ぶこと、働くことの意義の理解、及びその関連性の把握啓発的経験と進路意識の伸長職業生活、社会生活に必要な知識、技術・技能の習得への理解や関心社会の構成員として共に生きる心を養い、社会奉仕の精神の涵養 等 |
正解:4
選択肢1:適切
選択肢2:適切
選択肢3:適切
選択肢4:不適切
「自律的・主体的かつ継続的な学び・学び直し」という表現は、主に労働者の生涯学習やキャリア形成の文脈で使われています。特に厚生労働省が策定した「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」などの公的文書で頻繁に用いられており、企業や労働者双方が持続的成長のために、個人が自ら学び続ける姿勢や意欲を重要視する際のキーワードです。
問43
正解:2
選択肢1:不適切
比較評価表による検討は、意思決定において選択肢の整理や客観的比較に役立ちます。しかし「選択肢を広げたい場合」は、比較評価表をすぐに使用するよりも、まず広い視野で多様な可能性を探索するプロセス(ブレインストーミング等)が重視されます。比較は選択肢が絞られて実際に決定段階で用いる手法なので、「広げたい」タイミングで最も効果的な方法とは言えません。
選択肢2:適切
「軽い対決」とは、それぞれの選択肢の長所・短所、現実的可能性などを冷静に比較検討し合うことを指します。システマティックアプローチでは、複数の選択肢の実現性・妥当性を相談者とともに吟味する過程が強調されており、現実的に何が可能か、どういう障壁があるかを検討していくことは意思決定支援の重要なステップに含まれます。
選択肢3:不適切
キャリアコンサルタントは相談者の自己理解を深める支援を行い、相談者が自ら情報を取捨選択・絞り込みできるよう促すことが意思決定支援である。
選択肢4:不適切
インターネットや生成AIの情報は便利ですが、そのまま鵜呑みにして意思決定の根拠とすることは適切ではありません。情報の真偽や信頼性を判断しないまま活用すると、誤った選択につながる恐れがあります。キャリアコンサルタントは必ず相談者に情報の精査・吟味を促し、事実確認や根拠の検討を一緒に行うべきです。
問44
正解:1
選択肢1:適切
行動計画(Action Plan)は、方策の実行に移すために不可欠です。
- 実施項目(何をするか)
- 期間(いつまでに行うか)
- 達成レベル(どの状態になれば達成とみなすのか)
を明確にすることで、相談者は具体的な行動に移しやすくなります。さらに、キャリアコンサルタントは相談者と一緒に計画を確認・調整しながら作ることで、現実性と実行可能性が高まります。これはSMARTの原則(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)にも沿った考え方です。
選択肢2:不適切
相談者ごとに状況・価値観・資源・制約条件は異なります。そのため、画一的な「標準対応」ではなく、相談者に合わせた個別化・カスタマイズが必要です。標準化は教育マニュアルとしては便利ですが、実際の支援では柔軟な対応が求められます。
選択肢3:不適切
計画は固定的なものではなく、実行の過程で相談者の状況や価値観が変われば、柔軟に修正しながら進めることが大切です。外部環境の変化や相談者自身の内的変化に応じて調整しなければ、現実に即さない計画になり、モチベーションも低下します。
選択肢4:不適切
相談者が主体的に進捗を把握することは重要ですが、キャリアコンサルタントとの進捗共有は不可欠です。共有することで、課題が早めに発見でき、支援や調整を適切に行えます。進捗確認はモニタリングの一環であり、伴走支援にもつながります。
問45
正解:2
選択肢1:不適切
フォローアップの目的は「職場への適応支援」であり、そのためには相談者本人の主観的な感情・意識・満足度と、仕事や人間関係への適応感を把握することが非常に重要です。客観的な事実の把握も必要ですが、「より重視すべきは相談者本人の感じ方」です。本人がどう受け止め、どう適応しているかを把握せずに進めると、支援が形骸化します。
選択肢2:適切
職場適応の確認では、相談者本人へのインタビューだけでなく、上司・同僚・人事担当など事業主側の評価や観察も参考にします。特に障害者雇用や若年者支援の場合、第三者からの評価は職場側の適応状況や課題を把握する貴重な情報源となります。
ただし、この際は個人情報やプライバシーに配慮し、本人の同意を得て行うことが原則です。
選択肢3:不適切
フォローアップで得た情報は、次の支援計画や面談内容の改善に活かすべきです。面談の質を高めることは、相談者の適応や成長を支援するために重要な要素であり、この二つは排他的な関係ではありません。むしろ、情報を活用し面談をより効果的にすることは、定着支援の質を高めます。
選択肢4:不適切
不適応が明らかになった場合は、相談者との再面談に加えて、職場との調整や改善提案などの積極的な橋渡し支援を行うことが望まれます。特に障害者雇用や若年者支援では、職場環境の改善や配置変更など、事業主との連携が定着支援の一環となります。「何もしない」姿勢は不適合を放置することになり、不適切です。
国家試験 第29回 解説リンク集
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。