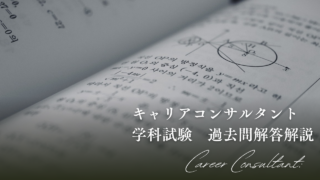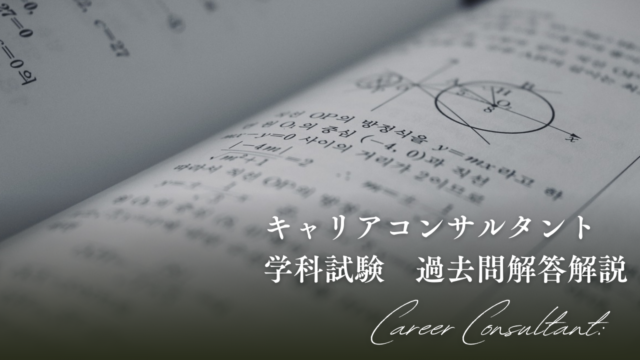第29回 国家資格キャリアコンルタント試験 学科試験 解答(問46〜50)
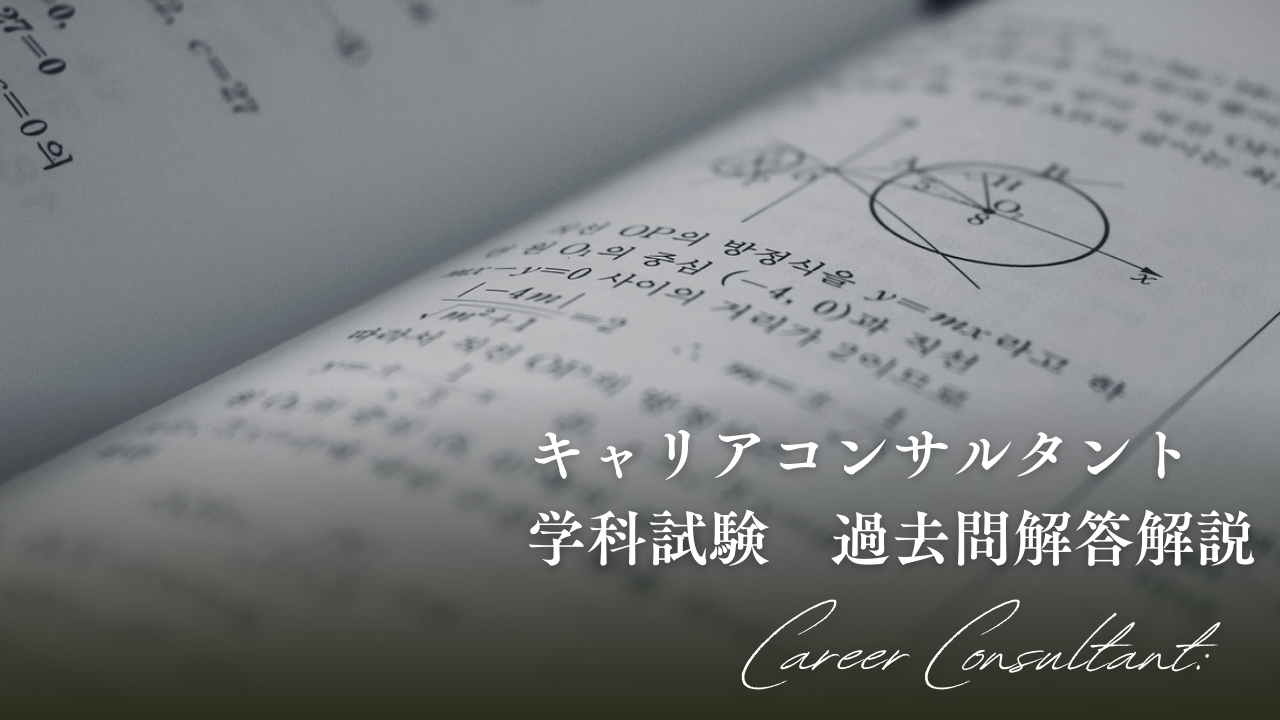
この記事について
第29回 国家資格キャリアコンサルタント試験 解説を作成しました。
過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしていこうと思います。
問46
正解:4
選択肢1:不適切
カウンセリングは一度終結しても、クライエントが新しい課題や支援ニーズを感じた場合は再開可能です。終結=永久終了ではなく、その時点での支援の一区切りを意味します。
むしろ終結後も「必要な時には戻ってきて良い」という安心感を与えることが望まれます。
選択肢2:不適切
開始時の目標は重要ですが、外部環境やクライエントの状況変化などにより、目標を変更したり、早めに終結することもあります。
支援は柔軟に見直しを行うべきで、「必ず設定目標を100%達成するまで続けなければならない」という考え方は現実的ではありません。
選択肢3:不適切
終結はカウンセリングの自然なプロセスの一部であり、むしろクライエントが自立し、支援が不要になったサインでもあります。
終結=失敗ではなく、達成や状況改善によって適切な時期に終えることが成功の証です。
選択肢4:適切
終結時には、クライエントがこれまでのプロセスで得た気づき・スキル・行動パターンなどを確認し、それらを日常生活や仕事でどう活かすのかを話し合うことが重要です。
これにより、カウンセリング後もクライエントが自立的に成長を続ける準備が整います。
問47
正解:2
選択肢1:適切
報告書でも、キャリアについて相談の意義が理解されていない層に対しては、キャリアコンサルタントの役割や支援内容を丁寧に分かりやすく周知することが重要だと指摘されています。労働者の理解促進は利用推進に欠かせません。
選択肢2:不適切
キャリアコンサルティングの普及にあたって、事例を示すことは有効ですが、相談者本人の同意なく実例を用いることは個人情報保護や倫理的観点から問題です。報告書でも相談者のプライバシー保護を重視しており、同意なく実例公開は避けるべきとされています。
選択肢3:適切
報告書では、働き方多様化に伴う新たな課題(リスキリング、転職支援など)に対する有効な支援効果を示すことが活用促進につながると明記されています。具体的な効果提示は信頼獲得につながります。
選択肢4:適切
報告書は生涯にわたるキャリア形成の重要性を強調しており、労働者・企業が日常的にキャリア形成を意識することが必要だとしています。リスキリングを含む継続的な学びが社会実現の鍵です。
問48
正解:3
選択肢1:適切
傾聴スキルの中には「要約(パラフレーズ)」が含まれます。相手の言葉を整理し、核心部分を捉える訓練を日常生活で行うことは、キャリアコンサルティングの面接で非常に役立ちます。日常的な練習によって、面談の精度や理解力が向上します。
選択肢2:適切
クライエント役を自ら経験することで、相手の立場や感情、受け取り方を実感でき、支援スキルや共感性が高まります。これは自己研鑽の有効な方法として研修や養成講座でも推奨されます。
選択肢3:不適切
ロールプレイの本来の目的は、型の暗記や固定化ではなく、状況に応じた柔軟な対応力やコミュニケーションの質を高めることです。「この順番」「この言葉」というマニュアル依存は、実際のクライエント対応では不自然さや臨機応変さの欠如につながります。
したがって「主眼が型の習得」という記述は誤りであり、不適切です。
選択肢4:適切
事例記録を外に持ち出す場合、情報漏えいのリスクに備えて、個人が特定できる情報(氏名、企業名、日時など)を匿名化・記号化することは必須です。これは職業倫理と個人情報保護の観点からも重要です。
問49
正解:3
選択肢1:適切
企業内キャリアコンサルタントには、人事部門など組織内の関係者と協力し、支援制度を効果的に運用する知識と実務能力が求められます。この協業と報告の仕組みを理解していることは、キャリア形成支援を円滑に進めるうえで必要な能力です。
選択肢2:適切
人生の転機における心理的・社会的な変化や対応方法は、キャリアコンサルティングの重要な領域です。これらを理解し、相談者への適切な支援ができることは必須の能力要件です。
選択肢3:不適切
精神疾患については、キャリアコンサルタントは専門治療者ではないため、不調を察知した場合は適切に専門機関にリファー(紹介)する必要があります。ただし「その後いかなる場合でも支援できない」とするのは誤りです。病気の有無にかかわらず、支援の範囲や内容は柔軟であり、状況に応じて支援を続けることもあります。完全に支援を断つわけではなく、専門家と連携しながら関わる場合も多いです。
選択肢4:適切
キャリアコンサルタントは青少年期の発達課題や教育制度の理解を持つことが基本能力の一つであり、学校段階に応じたキャリア教育への関わり方の理解は必要です。これにより青少年のキャリア支援の質が向上します。
問50
正解:3
選択肢1:不適切
キャリアコンサルタントは相談者個人を尊重し、その人生全般や多様な背景を踏まえた支援を行うべきであり、組織環境だけに注目するのは偏った視点です。また、相談者の要請も尊重しつつ、自身の専門性と倫理観に基づいて正しい支援を提供する責任があります。単に要請に無条件に応じるとは限りません。
選択肢2:不適切
倫理綱領では、誇示や自己顕示は慎むべきとされており、身分や業績を「過大にアピール」することは禁じられています。また、能力を超える業務に無理に取り組むことは安全性や相談者の利益を損なう可能性があり、専門性の範囲を自覚し適切に対応することが求められます。
選択肢3:適切
倫理綱領の基本理念において、「相談者の利益を第一義とする」ことが明確に示されています。相談者の人生に大きく影響を与えることを十分に自覚し、誠実かつ責任を持って職務にあたる姿勢が求められています。これはキャリアコンサルタントの根幹の態度です。
選択肢4:不適切
守秘義務は極めて重要ですが、倫理綱領では「例外なくどのような場合でも守る」とはせず、相談者の身体・生命の危険が察知される場合や法律に定められた場合など、守秘義務の例外が認められています。絶対的な無条件守秘ではありません。橋渡し支援を行うことが望まれます。特に障害者雇用や若年者支援では、職場環境の改善や配置変更など、事業主との連携が定着支援の一環となります。「何もしない」姿勢は不適合を放置することになり、不適切です。
国家試験 第29回 解説リンク集
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。