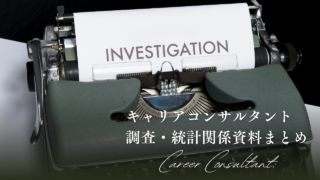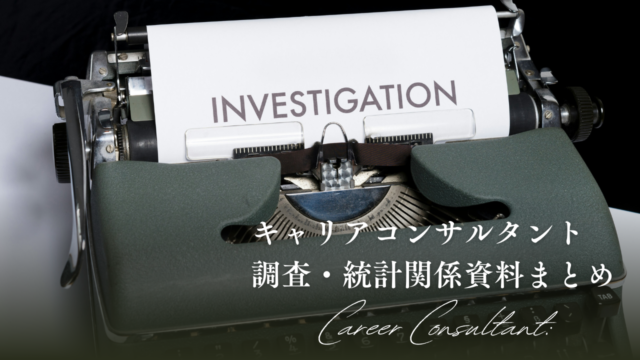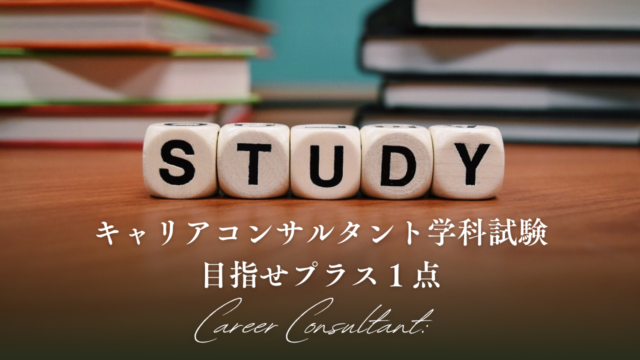欠員率と求人の充足率
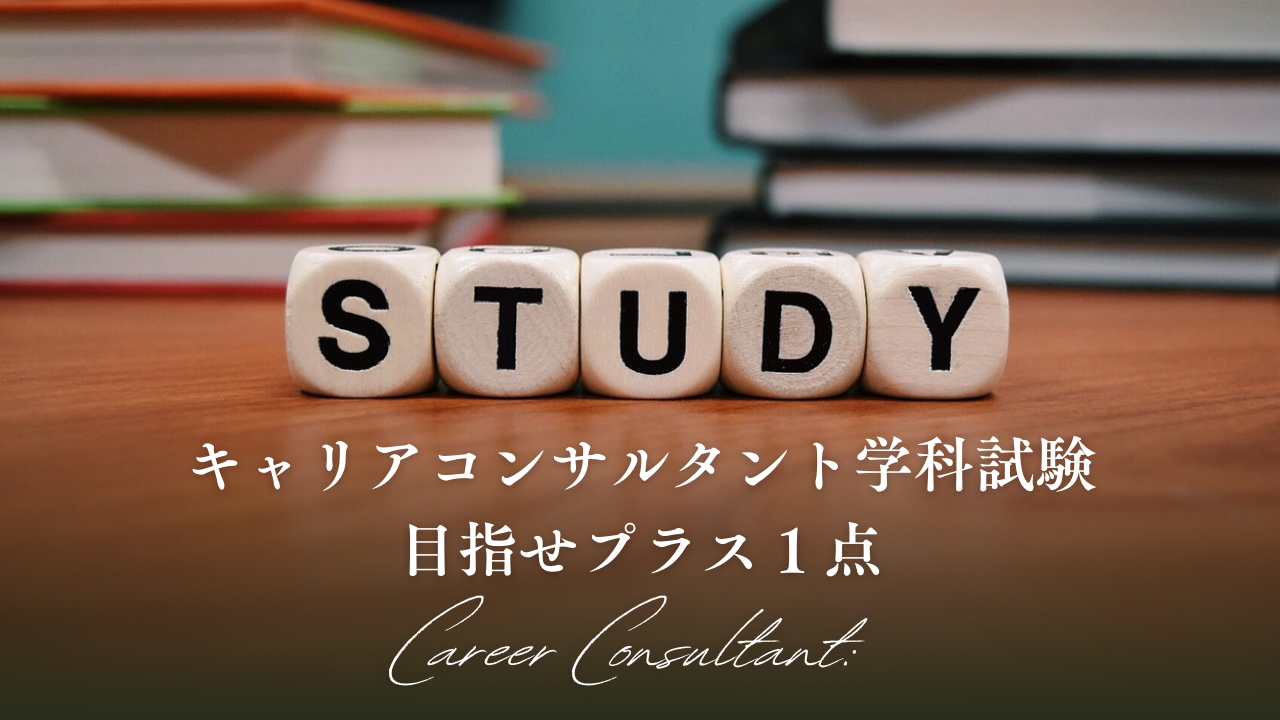
この記事について
頻出資料の1つの令和6年の「労働経済の分析」について、欠員率と充足率について出てきます。
ここで、
2010年の欠員率の水準はバブル期に及ばないとしている一方、求人の充足率は半世紀の中で最低水準
と書かれていて、あれ?矛盾してない?と思ってしまいました。
欠員率は最低レベルではないのに、充足率は最低レベルなの?
気になったので、調べてみました。
企業の欠員率と求人の充足率
矛盾しているように見えますが、実際には次のような背景があるため両方が成立しています。
2010年代以降の欠員率はバブル期に比べて水準がやや低いか、それに及ばない程度です。
つまり、企業が感じる「足りない人の割合」はバブル期ほど高くはない。
また、欠員率の上昇幅も過去より穏やかで、全体の不足人数の割合自体はそれほど激増していません。
一方で求人の充足率は、この半世紀で最低水準にまで低下しています。
これは、「出された求人に対して実際にどれだけ早く人が集まるか」の指標で、特にフルタイム求人で低下が目立ちます。
そのため、企業は欠員率としてはそれほど高くないにもかかわらず、求人がなかなか埋まらず、採用難を感じているのです。
つまり、欠員率は「必要な人に対して足りていない割合」で「全体の不足感」を表す指標であり、求人の充足率は「求人に対して人が集まるスピードや充足のしやすさ」を示す指標です。
人手不足が「長期的かつ粘着的」で短期的に求人が埋まりにくい状況が続いているため、充足率は低いですが欠員率としての不足感はそれほど激しく増えていない、という状態です。
まとめ
欠員率と求人充足率は異なる角度から人手不足を示しており、「欠員率はバブル期に及ばず、求人充足率は最低水準」という現象はむしろ人手不足の性質の変化を表していると言えます。
2010年以降は、バブル期のように需要が増えている訳ではないから、欠員率はそこまで大きく増えていかない。
一方で充足率の低下により、入職者が減り、充足率が一向に増えていかないという状況のようです。
おまけ
欠員率と充足率の違い
- 欠員率とは、必要な人員のうち実際に充足されていない人員の割合を示す指標で、計算式は「欠員率=(必要充足数−実員)÷必要充足数」で表される。
つまり、どれだけ人手不足があるかを表す割合である。厚生労働省の定義でも、欠員率は「常用労働者に対する未充足求人数の割合」とされている。 - 充足率とは、必要な人員に対して実際に充足されている人員の割合を示し、計算式は「充足率=実員÷必要充足数」で表される。
つまり、どの程度人手が満たされているかを示す指標である。
欠員率と充足率の違いをもっと簡単に言うと
- 欠員率は「必要な人数のうち、どれだけ人が足りていないか」の割合
- 充足率は「必要な人数のうち、どれだけ人がちゃんといるか」の割合
たとえば、100人必要なところに今80人しかいなければ、
欠員率は20%(20人足りない)、
充足率は80%(80人いる)となります。
つまり、欠員率は「人が足りない割合」、充足率は「人がいる割合」を示す数字の違いです。簡単に言うと、足りない方と足りている方の違いですね。