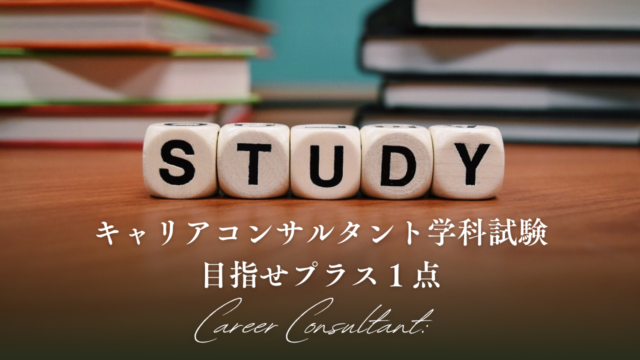【ラジオ&要約】「労働力調査(基本集計)「2024年(令和6年)平均結果」
shasha
/
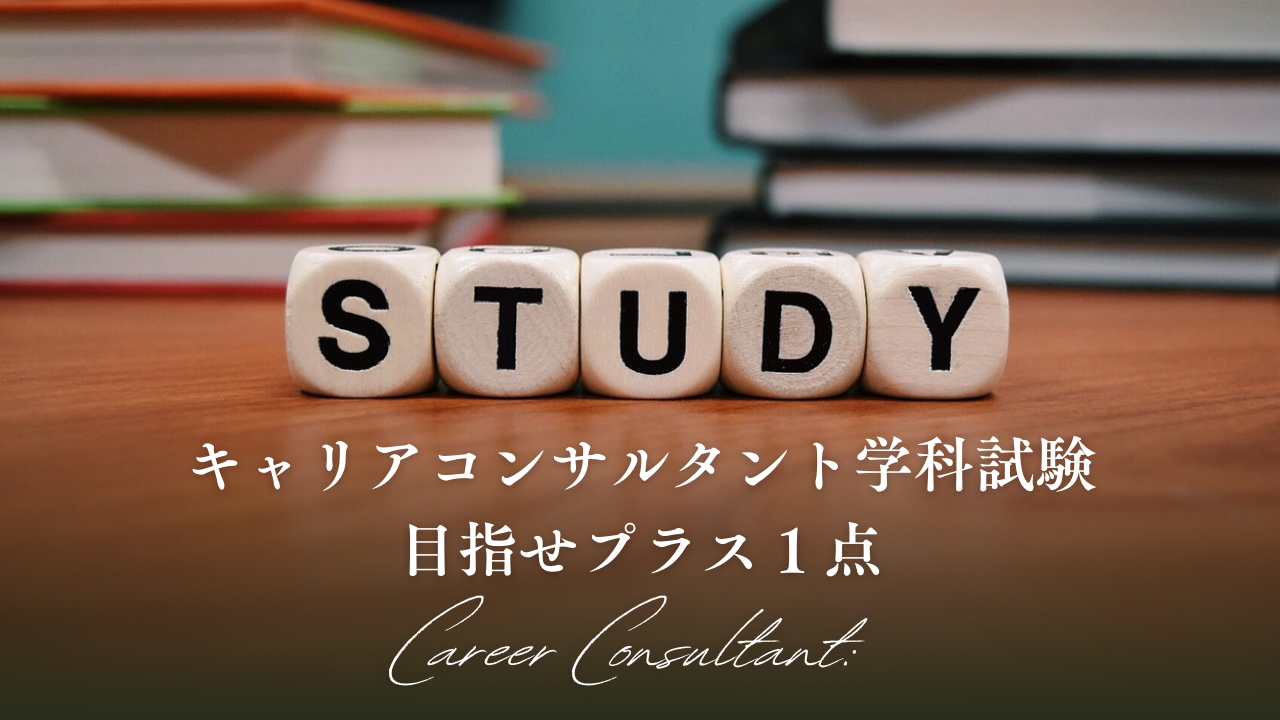
この記事について
GoogleのNotebookLM を使って、「労働力調査(基本集計)「2024年(令和6年)平均結果」の要点をラジオっぽく音声にしてまとめてみました。
これを聞くだけで、この資料の大筋を理解できますので、まず、これを聴いてから資料に目を通すと理解が深まると思います。
是非活用してみてください。
音声要約
要約
ご提示いただいた資料は、2024年の日本の労働力人口に関する詳細な動向と、それに付随する就業状況、雇用形態、失業状況、非労働力人口、そして地域別の傾向について包括的に報告しています。これらの情報から、日本の労働市場が全体としてどのような変化を遂げているのか、またその背景にある要因の一部を読み解くことができます。
労働力人口の全体的な動向
- 労働力人口の増加: 労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、2024年平均で6957万人となり、前年に比べて32万人の増加を記録しました。これは2年連続の増加です。
- 女性労働力人口の顕著な増加: 男女別にみると、男性は3800万人と1万人の減少であったのに対し、女性は3157万人と33万人の大幅な増加となりました。15~64歳の年齢層でも同様の傾向が見られ、男性が4万人の減少に対し、女性は21万人の増加となっています。
- 労働力人口比率の上昇: 15歳以上人口に占める労働力人口の割合である労働力人口比率は、2024年平均で63.3%と、前年に比べ0.4ポイントの上昇となりました。これは4年連続の上昇です。特に女性が0.8ポイント上昇して55.6%、15~64歳女性では0.9ポイント上昇して76.1%となるなど、女性の労働参加が進んでいることが示されています。
就業者数の動向
- 就業者数の増加と女性の貢献: 就業者数は2024年平均で6781万人となり、前年に比べ34万人の増加となりました。これは4年連続の増加です。労働力人口と同様に、男性が3万人の増加に留まったのに対し、女性は31万人の増加と大きく貢献しています。
- 就業率の上昇: 15歳以上人口に占める就業者の割合である就業率は、2024年平均で61.7%と、前年に比べ0.5ポイントの上昇を記録し、これも4年連続の上昇です。女性の就業率が0.6ポイント上昇して54.2%に達しています。
- 年齢階級別の就業率: 15~64歳の就業率を10歳階級別に見ると、男性は15~24歳が1.1ポイント、25~34歳が0.3ポイントの上昇となりました。女性は35~44歳が1.2ポイント、25~34歳が1.0ポイントの上昇となるなど、特に若い世代から中年層にかけて女性の就業が進んでいます。
雇用形態と労働時間の変化
- 雇用者の増加と自営業者の減少: 就業者を従業上の地位別に見ると、雇用者数は6123万人と前年に比べ47万人の増加となりました。一方、自営業主・家族従業者数は624万人と15万人の減少を記録しており、雇用労働への移行が進んでいることが示唆されます。
- 正規雇用と非正規雇用の動向:
- 正規の職員・従業員数は3654万人と39万人の増加(10年連続の増加)となりました。特に女性が31万人の増加と大きく伸びています。
- 非正規の職員・従業員数は2126万人と2万人の増加(3年連続の増加)となりましたが、15~64歳では15万人の減少となっています。一方で、65歳以上では16万人の増加となっており、高齢層における非正規雇用の増加が目立ちます。
- 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は36.8%と0.2ポイントの低下となりました。
- 雇用契約期間の傾向: 無期の契約を持つ雇用者が3820万人と36万人の増加である一方、有期の契約を持つ雇用者は1438万人と5万人の減少となりました。特に女性では、無期の契約が31万人の増加、有期の契約が4万人の減少と、女性の正規雇用・無期雇用へのシフトが進んでいることが分かります。
- 週間就業時間の変化: 休業者を除く雇用者について、週49~59時間の区分が0.6ポイント低下した一方で、週30~34時間の区分は1.1ポイント上昇しました。これは、労働時間の短縮化や多様化の傾向を示唆しています。正規の職員・従業員では、週30~34時間の区分が1.6ポイント上昇しています。
産業別の動向
- 成長産業と減少産業: 就業者が最も増加した産業は「情報通信業」で14万人の増加でした。次いで「医療,福祉」が12万人の増加、「宿泊業,飲食サービス業」が9万人の増加となっています。これらのサービス業や情報通信分野が労働市場の成長を牽引していることが分かります。
- 一方、「製造業」が9万人の減少、「農業,林業」が7万人の減少、「建設業」が6万人の減少となりました。
休業者と完全失業者の動向
- 休業者の増加: 就業者に占める休業者数は195万人と、前年に比べ6万人の増加となりました。これは2年ぶりの増加です。産業別では「製造業」と「卸売業,小売業」でそれぞれ2万人の増加が見られました。
- 完全失業者の減少: 完全失業者数は176万人と、前年に比べ2万人の減少となりました。これは3年連続の減少です。
- 男女別では、男性が4万人の減少、女性は3万人の増加となりました。
- 完全失業率の低下: 労働力人口に占める完全失業者の割合である完全失業率は、2024年平均で2.5%と、前年に比べ0.1ポイントの低下となりました。これは2年ぶりの低下です。男女差は0.3ポイントとなっています。
- 失業理由の多様化: 「勤め先や事業の都合」による非自発的な離職者は3万人の減少となった一方、「定年又は雇用契約の満了」による離職者は1万人の増加となりました。また、「新たに求職」する者、特に「収入を得る必要が生じたから」という理由での求職者が1万人の増加を見せています。
非労働力人口の動向
- 非労働力人口の減少: 非労働力人口は2024年平均で4031万人と、前年に比べ53万人の減少となりました。これは4年連続の減少です。
- 女性の非労働力人口の顕著な減少: 男女別では、男性が6万人の減少であったのに対し、女性は47万人の大幅な減少となりました。また、65歳以上でも13万人の減少が見られ、高齢者や女性の労働参加の進展がこの減少の背景にあると考えられます。
地域別の就業状況
- 就業者数の増加地域: 2024年平均の就業者数は、11地域中8地域で増加が見られました。特に南関東が23万人の増加、近畿が7万人の増加と、大都市圏での増加が目立ちます。
- 就業率の上昇地域: 就業率は11地域中9地域で上昇しました。就業率が最も高いのは南関東(64.2%)で、次いで東海(63.0%)、沖縄(62.2%)と続きます。
- 完全失業率の低下地域: 完全失業率は6地域で低下し、北陸(2.0%)が最も低い率となりました。一方で東北と中国では上昇しています。
- 休業者の増加地域: 休業者数は6地域で増加し、南関東と東海でそれぞれ2万人の増加が見られました。
まとめ
これらのソース全体を通して、日本の労働市場は2024年において、労働力人口と就業者数が増加傾向にあり、特に女性の労働参加が顕著に進んでいることが示されています。雇用形態では、正規雇用・無期雇用への移行が進む一方で、高齢層では非正規雇用も増加しています。労働時間については、短時間労働へのシフトも見られます。産業別では情報通信業や医療・福祉、宿泊・飲食サービス業が成長を牽引していますが、製造業や農業、建設業では就業者の減少が見られます。完全失業者は減少し、失業率も低下していますが、休業者は増加しており、労働市場の複雑な変化を示唆しています。地域別に見ると、大都市圏を中心に就業者数や就業率の増加が見られる一方で、地域間のばらつきも存在します。
総じて、これらのソースは、日本の労働市場が人口構造の変化(特に女性と高齢者の労働参加)に適応し、サービス業を中心とした経済構造への転換を進めている状況を詳細なデータで示していると言えるでしょう。