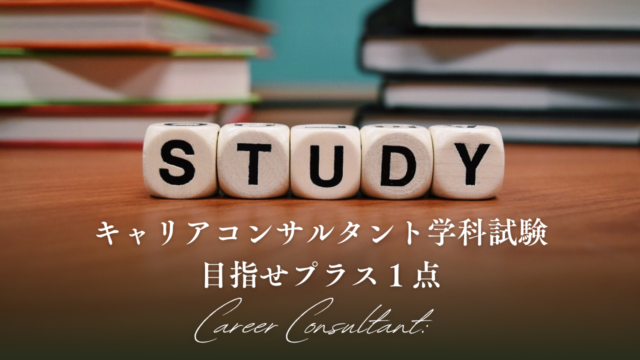森田療法

この記事について
ニッチな領域ですが、たびたび試験で出てくる理論家を紹介していきます。
概要と特徴
森田療法は、日本の精神科医・森田正馬(もりたまさたけ、1874-1938)によって1919年に創始された、日本独自の精神療法です。
主に強迫症(強迫性障害)、社交不安症、パニック症、広場恐怖症、全般不安症、心気症、身体症状症など、かつて神経症と呼ばれていた不安障害を対象としています。
森田療法の最大の特徴は、「不安や症状をなくそうとせず、そのまま受け入れる(あるがまま)」という姿勢を重視する点です。
欧米の精神療法が「考え方を変えてネガティブをポジティブにする」ことを目指すのに対し、森田療法は「症状や感情を排除しようとせず、自然なものとしてそのままにしておく」ことを基本とします。
理論的背景
森田療法では、神経症の根底に「神経質性格」(内向的・自己内省的・心配性・完全主義など)があり、この性格傾向を背景に「とらわれの機制」と呼ばれる心理的悪循環が生じると考えます。
- 精神交互作用:症状や不安に過度に注意を向けることで、さらに症状が強まる悪循環。
- 思想の矛盾:「こうあるべき」「こうあってはならない」といった思考が、現実の感情や症状と葛藤し、苦しみを増幅させる。
この悪循環を断ち切るため、症状や不安を無理に排除しようとせず、「あるがまま」に受け入れる姿勢を養います。
治療の進め方
森田療法には「入院療法」と「外来療法」があり、重度の症状には入院療法が用いられることがあります。
入院療法の4段階
- 臥褥期(がじょくき)
1週間程度、個室で安静に過ごし、症状や不安に直面し受け入れる態度を養います。 - 軽作業期
軽い作業(掃除や散歩など)を行い、活動意欲を刺激します。 - 重作業期
共同作業(園芸や料理など)を通じて、症状があっても目的本位に行動する姿勢を身につけます。 - 生活訓練期
外出や外泊などを通じて社会復帰の準備をします。
外来療法
近年は外来療法が主流で、日常生活の中で「あるがまま」の姿勢を実践し、症状や不安を受け入れつつ、建設的な行動に取り組むことを目指します。
「あるがまま」とは
森田療法でいう「あるがまま」とは、不安や症状を排除しようとせず、自然な感情や身体反応をそのまま受け入れる態度を指します。
不安や恐怖の裏には「よりよく生きたい」という生の欲望があるとし、その欲望を建設的な行動に向けることが治療の目標です。
適応範囲と現代での応用
もともとは神経症が主な対象でしたが、現在ではうつ病、統合失調症、アルコール依存症、慢性疼痛、PTSD、がん患者のメンタルヘルスなど、幅広い疾患に応用されています。
まとめ
- 森田療法は「症状や不安をなくす」ことを目標とせず、「あるがまま」に受け入れることで悪循環を断ち切り、本来の生き方を取り戻すことを目指す日本独自の精神療法です。
- 「とらわれ」から脱し、不安や症状と共に生きながら、建設的な行動を重視します。
- 入院・外来・自助グループなど多様な実践形態があり、現代でも幅広く活用されています。
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いします。ブログ運営の励みになります。