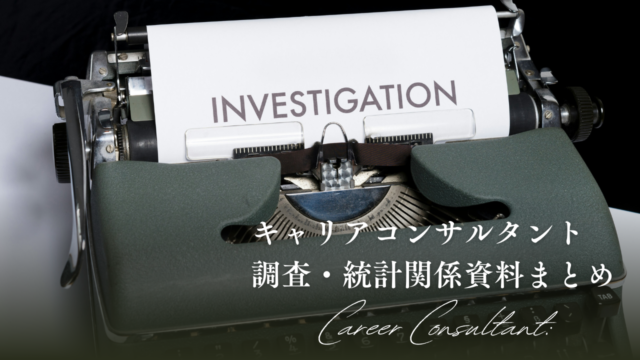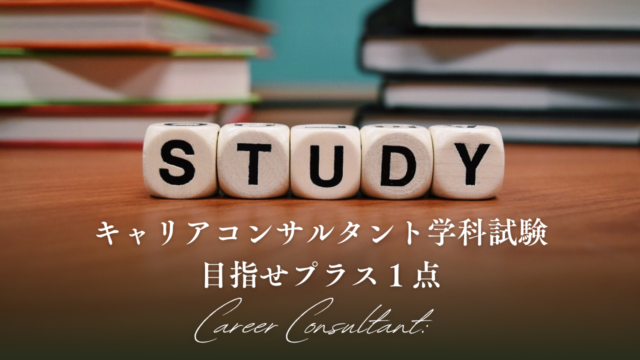日本標準職業分類と厚生労働省編職業分類
shasha
/
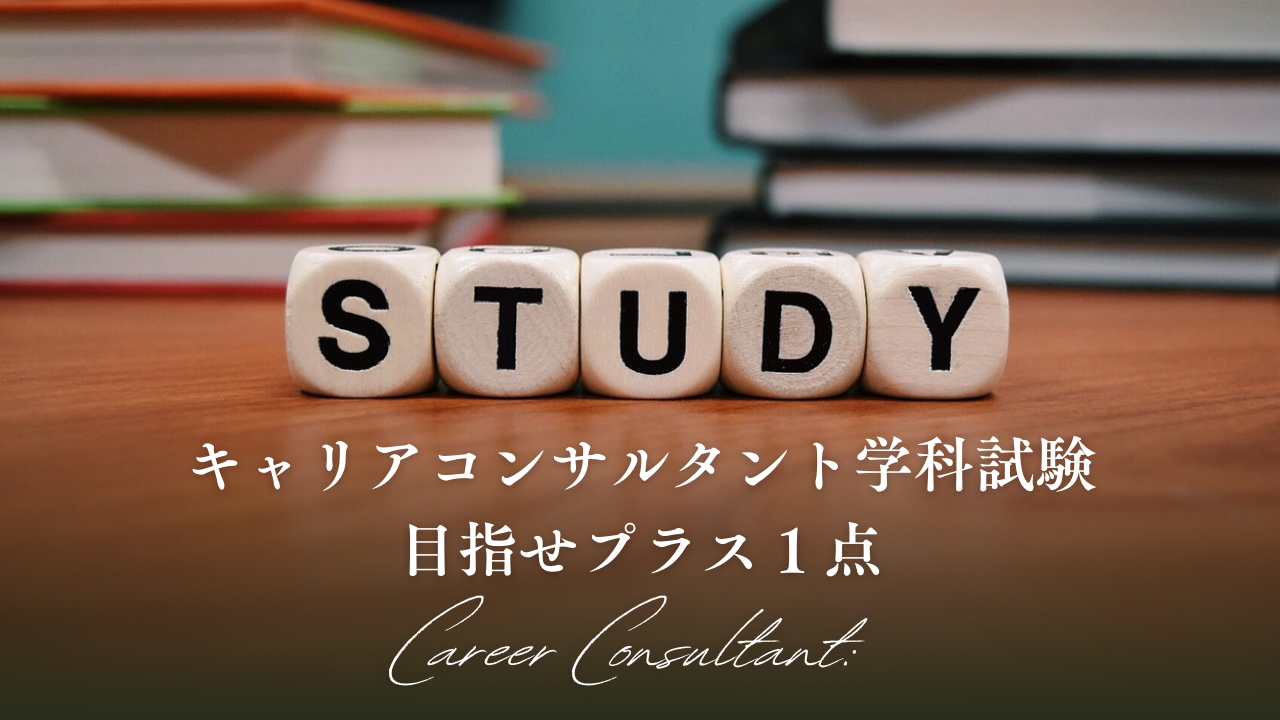
この記事について
日本標準職業分類と厚生労働省編職業分類は、いずれも日本国内で職業を体系的に分類するための基準ですが、それぞれ目的や特徴が異なります。以下にその概要をまとめます。
日本標準職業分類
- 作成機関:
総務省 - 目的:
統計調査において、職業別にデータを整理・表示するための基準。 - 分類基準:
個人が従事する仕事の類似性に着目し、体系的に分類。 - 構成:
・大分類12
・中分類74
・小分類329 - 特徴:
職業の定義は「報酬を伴う、または報酬を目的とする個人の行う仕事」。
主に統計用途で使用され、客観性や統計データの相互比較性を重視。
厚生労働省編職業分類
- 作成機関:
厚生労働省 - 目的:
公共職業安定所(ハローワーク)などでの求人・求職マッチングや職業紹介事業で使用される基準。 - 分類基準:
職務の類似性
求人・求職の取扱件数などに基づき、社会的な需給状況を考慮して分類。 - 構成:
大分類15
中分類99
小分類440 - 特徴:
・日本標準職業分類との整合性を保ちながら独自の目的に合わせて設計。
・ハローワークでの利用を前提としており、実務的な側面が強い。
・職業構造の変化に対応するため、1953年から5回改定が行われており、最新は令和
5年改定版。
両者の比較
| 項目 | 日本標準職業分類 | 厚生労働省編職業分類 |
|---|---|---|
| 作成機関 | 総務省 | 厚生労働省 |
| 主な目的 | 統計調査用 | 求人・求職マッチング |
| 分類基準 | 職務の類似性 | 職務の類似性+需給状況 |
| 構成 | 大分類12、中分類74、小分類329 | 大分類15、中分類99、小分類440 |
| 使用場面 | 統計データ整理・比較 | ハローワーク等での実務 |
| 改定頻度 | 必要に応じて改定 | 社会経済変化に応じて改定 |
日本標準職業分類の改訂経緯
| 改訂回 | 改訂日 | 改訂内容 |
|---|---|---|
| 初版 | 1952年(昭和27年) | 初めて職業分類を設定。統計調査における職業分類の基礎を構築。 |
| 第1回改訂 | 1968年(昭和43年) | 国際労働統計会議の基準に対応し、職業構造の変化を反映した分類項目の見直しを実施。 |
| 第2回改訂 | 1979年(昭和54年) | 社会経済情勢の変化に対応し、分類項目を拡充。新しい職業の台頭を反映。 |
| 第3回改訂 | 1986年(昭和61年) | コンピュータ処理の導入や分類精度向上を目的とし、職業項目を細分化。 |
| 第4回改訂 | 1997年(平成9年) | 情報技術の進展や新しい産業構造に対応するため、分類項目をさらに細分化。 |
| 第5回改訂 | 2009年(平成21年) | 職業構造の変化や国際基準への適合を目的とした大規模な見直し。 |
| 最新改訂 | 2022年(令和4年) | 細分類を廃止し、小分類までの3階層に変更。求人数・求職者数が多い場合は小分類項目に格上げ[1][4][6]。 |
最新の2022年改訂では、細分類が廃止されるなど、柔軟性と実用性を重視した大幅な変更が行われました。この変更は、社会構造や労働市場の変化に対応するためです。
2009年の日本標準職業分類の改訂
2009年の日本標準職業分類の改訂は、統計基準としての精度向上と社会経済情勢の変化に対応するために行われました。この改訂の詳細を以下にまとめます。
| 改訂内容 | 詳細 |
|---|---|
| 分類体系の見直し | 大分類を10項目、中分類を56項目、小分類を370項目に再構成。- 農林業作業者と漁業作業者を統合し「農林漁業作業者」を新設。- 運輸・通信従事者の一部を移動し、新たに「技能工、生産工程作業者及び労務作業者」を設定。 |
| 新たな分類基準の導入 | 「個人が従事する仕事の形態」を基準に追加し、職務内容の類似性をより正確に反映。 |
| 新設・廃止項目 | 中分類では新設項目が廃止・統合項目を上回り、全体で4項目増加。- 小分類では7項目が新設される一方で、多くの項目が廃止・統合され、全体で22項目減少。 |
| 管理的職業従事者の定義変更 | 「専ら経営管理に従事する」という文言を削除し、実務と管理を兼務するプレイングマネージャーも含めるよう定義を緩和。 |
| 情報技術関連職種の細分化 | 「情報処理技術者」を「システムエンジニア」と「プログラマー」に分割し、さらに「通信ネットワーク技術者」を追加して「情報処理・通信技術者」に変更。 |
| 介護職種の新設 | サービス職業従事者に「介護職員(治療施設、福祉施設)」を新設し、介護関連職種を明確化。 |
| 産業分類的視点の排除 | 職務内容とその類似性に基づいて分類項目を設定し、産業分類的な視点を排除(職業分類の純化)。 |
| 統計利用可能性と利便性向上 | – 統計結果表示時の利便性向上のため、大分類と中分類間に亜大分類を導入(例:技能工、生産工程作業者等)。 |
この改訂は、急速な技術進歩や産業構造の変化に対応するため、職業構造全般にわたる抜本的な見直しが行われた点が特徴です。また、管理職や情報技術関連職種など、現代的な労働環境に即した定義や細分化が進められました。
2022年の日本標準職業分類の改訂
2022年の日本標準職業分類の改訂は、11年ぶりの大幅な見直しであり、社会経済情勢や労働市場の変化に対応するために行われました。以下に、その改訂内容を詳細にまとめます。
| 改訂内容 | 詳細 |
|---|---|
| 細分類の廃止 | 細分類を廃止し、大分類・中分類・小分類の3階層に統一。- 細分類から小分類へ格上げされた項目もあり、求人数や求職者数が多い職業については小分類で対応。 |
| 大分類の見直し | 「専門的・技術的職業」を分割し、「研究・技術の職業」と「法務・経営・文化芸術等の専門的職業」を新設。- 「医療・看護・保健の職業」「保育・教育の職業」「福祉・介護の職業」など、社会的需要が高い分野を新設。 |
| 中分類の再編成 | 職業マッチングを円滑化するため、中分類項目名や分け方を見直し。例: 「保健師、助産師、看護師」を「保健師、助産師」と「看護師、准看護師」に分割。- 「一般事務の職業」を細分化し、「総務・人事・企画事務」や「医療・介護事務」などを新設。 |
| 小分類項目の整理と新設 | 労働市場で使用される名称を踏まえ、小分類項目名を見直し。- 例: 「介護サービスの職業」を「施設介護」と「訪問介護」に分割。 |
| 項目名の分かりやすさ向上 | 職業名を具体的かつ分かりやすいものに変更。例: 「建設・採掘の職業」→「建設・土木・電気工事の職業」、「生産工程の職業」→「製造・修理・塗装・製図等の職業」。 |
| 労働市場との整合性強化 | 日本標準職業分類との整合性を確保しつつ、求人・求職マッチングに必要な柔軟性を導入。 |
| 統計利用と実務利用の両立 | 統計データ収集に加え、ハローワークなどで実際に活用できるような実務的視点を強化。 |
この改訂では、「細分類」の廃止が最大の特徴であり、小分類までに統一することで簡潔さと実用性を向上させました。また、大分類や中分類では、新たな社会的ニーズに対応した項目が追加され、労働市場で理解されやすい名称への変更が行われました。この改訂は、日本標準職業分類と整合性を保ちながらも、求人と求職者間のマッチング効率を高めることを目的としています。
まとめ
日本標準職業分類は統計調査向けであり、客観性と比較可能性を重視した体系です。一方、厚生労働省編職業分類は実務的な用途(求人・求職マッチング)を重視し、日本標準職業分類との整合性を保ちながら独自に設計されています。
それぞれの特性を理解し、適切な場面で使い分けることが重要です。