ブリッジスと岡本裕子の理論の共通点
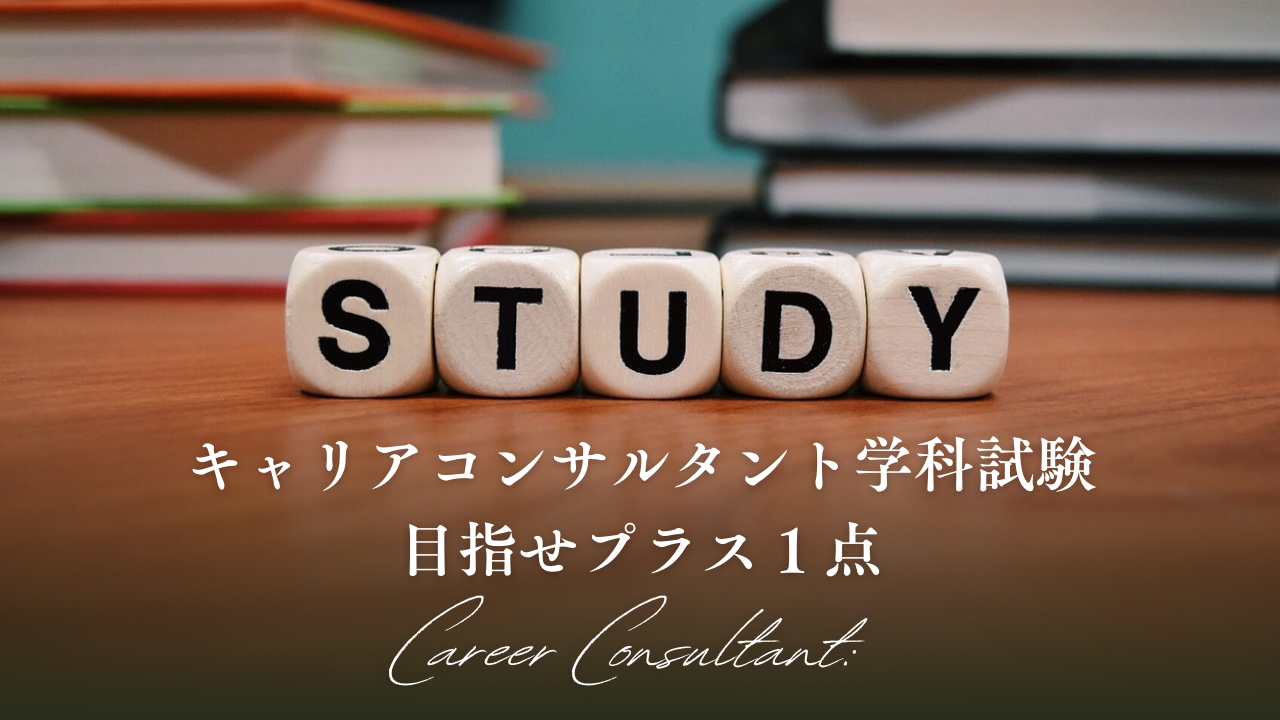
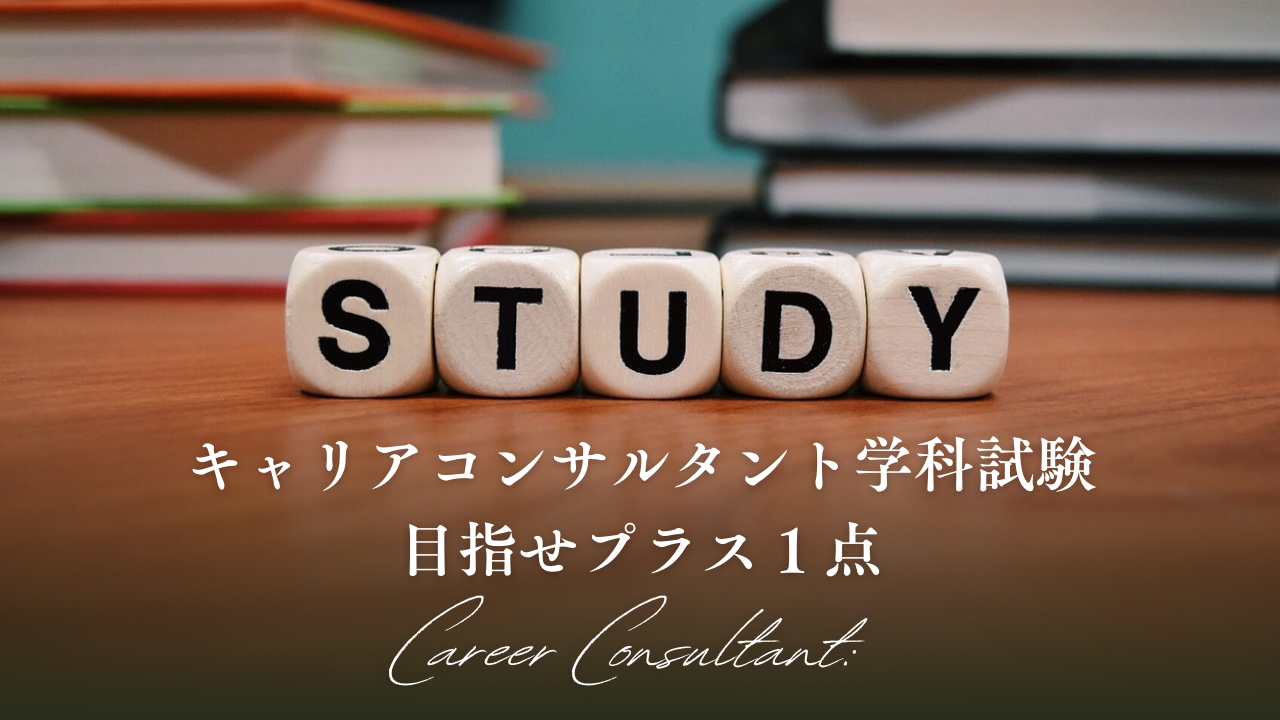
岡本裕子の「アイデンティティ再体制化のプロセス」は第26回国キャリ試験に選択肢として登場しています。
個人的に、ブリッジスの終焉から始まる理論と似ているなと思ったので、調べてみました。
岡本祐子の「危機→再体制化→再生」と、ウィリアム・ブリッジスの「終焉→中立圏→開始」は、異なる理論でありながら、共通する要素もあります。以下にその違いと類似点を説明します。
岡本祐子の理論は、アイデンティティの生涯発達を中心に展開されています。彼女は、人生の危機を乗り越えることで、自己の再体制化が起こり、最終的に再生につながると考えています。具体的には、危機はアイデンティティを揺さぶるものであり、その危機から回復するプロセスが再体制化であり、そこから新たな自己が生まれる再生が起こるとされています。
ウィリアム・ブリッジスの理論は、人生の変化を乗り越えるプロセスに焦点を当てています。彼は、変化のプロセスを「終焉(何かが終わる)」、「中立圏(ニュートラル・ゾーン)」、「開始(何かが始まる)」の3つの段階に分けます。終焉は過去との決別を意味し、中立圏は新たな方向を見出すための空虚感を伴う段階であり、開始は新たな一歩を踏み出す段階です。
岡本祐子とブリッジスの理論は、変化や危機を通じて新たな成長や再生が起こるという点で共通していますが、焦点や段階の定義において異なる側面があります。岡本はアイデンティティの発達に重点を置き、危機を通じて自己が再構築されるプロセスを強調しています。一方、ブリッジスは人生の変化全体を捉え、終焉から新たな開始までのプロセスを3つの段階に分けて説明しています。
「人が危機を乗り越えて、新しいステージに行く」という考え方は、共通しているように思いました。
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。
↑この記事が良いと思ったら
❤️クリックをお願いします。ブログ運営の励みになります。