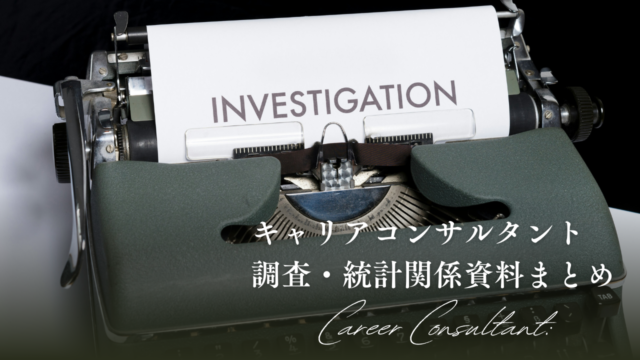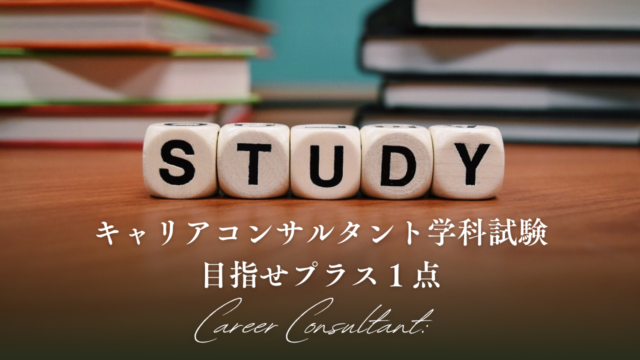行政関係調査 まとめ
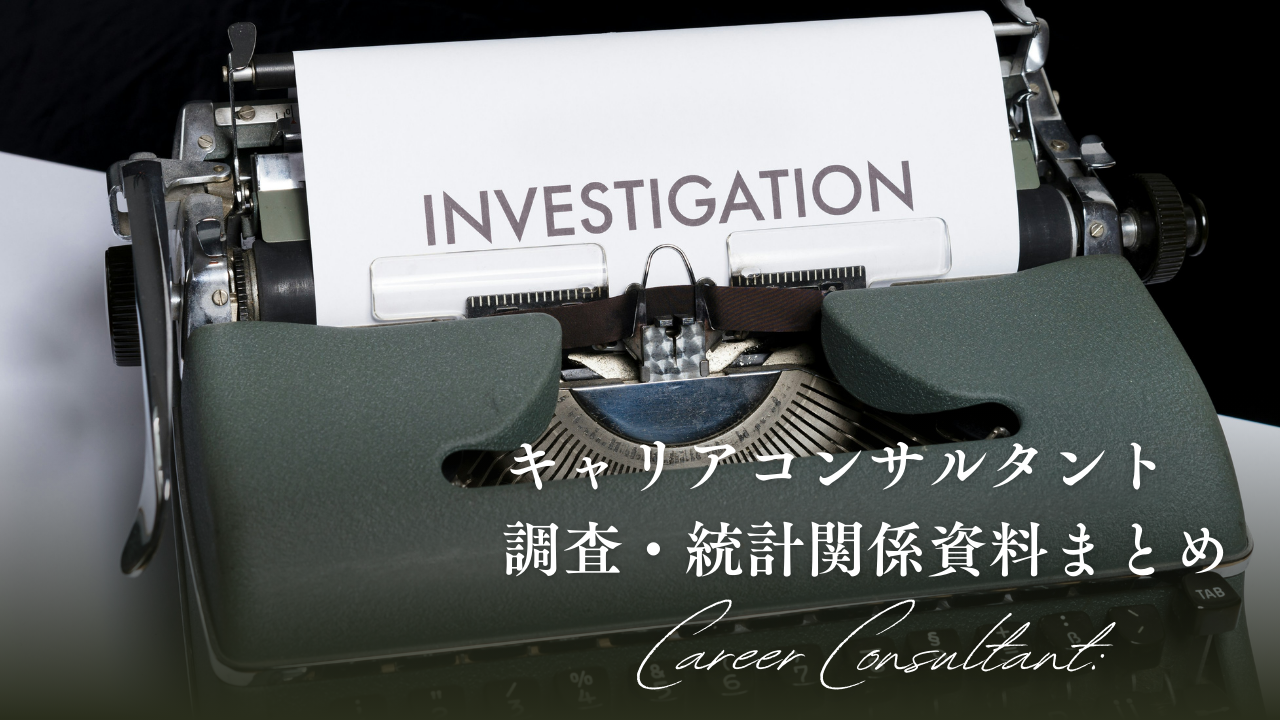
Contents
賃金構造基本調査
厚生労働省が主要産業に雇用される労働者の賃金実態を明らかにすることを目的に毎年実施している統計調査です。
この調査結果は、日本の労働市場における賃金の実態を詳細に示すものであり、政策立案や労使交渉の基礎資料として広く活用されています
賃金構造基本統計調査(厚生労働省HP)
調査の目的と概要
- 主要産業に雇用される労働者の賃金実態を明らかにすることが目的
- 労働者の属性別に賃金を調査
(雇用形態、就業形態、職種、性別、年齢、学歴、勤続年数、経験年数など) - 統計法に基づく基幹統計として位置付けられている
調査の実施方法
- 毎年6月分の賃金について7月に調査を実施
- 全国の事業所から無作為に抽出された約7万8千事業所を対象
- 10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所のデータを集計
最新の調査結果(令和5年)
一般労働者(フルタイム労働者)の賃金
- 男女計:318,300円(前年比2.1%増)
- 男性:350,900円(同2.6%増)
- 女性:262,600円(同1.4%増)
短時間労働者の時給
- 男女計:1,412円(前年比3.3%増)
- 男性:1,657円(同2.0%増)
- 女性:1,312円(同3.3%増)
調査の意義
- 最低賃金の決定や労災保険の算定資料などに活用される
- 日本の賃金動向を把握する上で重要な指標となっている
就業構造基本調査
総務省統計局が5年ごとに実施する重要な基幹統計調査です。
就業構造基本調査は、日本の労働市場の詳細な実態を把握するための重要な統計調査として、幅広く活用されています。
就業構造基本調査(厚生労働省HP)
調査の目的と概要
- 国民の就業及び不就業の実態を明らかにし、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることが目的
- 統計法に基づく基幹統計「就業構造基本統計」を作成するための調査
- 5年ごとに実施され、2022年調査は18回目
調査の実施方法
- 調査対象:全国の約54万世帯、15歳以上の世帯員約108万人
- 調査時期:調査実施年の10月1日現在
- 調査方法:調査員が調査票を配布し、インターネット回答、郵送提出、または調査員への提出により回答
調査内容
- 基本的属性(性別、年齢、学歴など)
- 就業状態
- 就業日数・時間
- 就業に対する希望意識
- 訓練・自己啓発の状況
調査結果の活用
- 政府の労働関連施策の基礎資料
- 地方公共団体の政策立案
- 学術研究
- 国民経済計算における就業者数や雇用者数の算出
就労条件総合調査
就労条件総合調査(厚生労働省HP)
厚生労働省が実施する重要な統計調査です。この調査の主な特徴は以下の通りです:
目的と対象
- 民間企業における就労条件の現状を明らかにすることが目的
- 常用労働者30人以上の民営企業から約6,400社を無作為抽出して調査
調査内容
- 労働時間制度、賃金制度、定年制度などを総合的に調査
- 主な調査項目:
- 年間休日数
- 年次有給休暇の取得状況
- 変形労働時間制の適用状況
- 時間外労働の割増賃金率
- 特別休暇制度
調査方法と時期
- 毎年1月1日現在の状況を調査
- オンライン回答も可能
最近の調査結果(令和6年調査)
- 年間休日総数: 1企業平均112.1日(過去最多)
- 年次有給休暇の平均取得率: 65.3%(過去最高)
- 時間外労働の割増賃金率を25%とする企業: 94.2%
毎月勤労統計調査
日本の労働経済の動向を把握するための重要な基幹統計調査です。
毎月勤労統計調査は、90年以上の歴史を持つ日本の重要な統計調査の一つであり、労働経済政策の立案や企業の労務管理など、幅広い分野で活用されています。
毎月勤労統計調査(厚生労働省HP)
調査の概要
- 目的: 雇用、給与(賃金)、労働時間の変動を明らかにすること
- 実施主体: 厚生労働省
- 調査対象: 常用労働者5人以上を雇用する事業所
- 調査頻度: 全国調査と地方調査は毎月、特別調査は年1回
調査の種類
- 全国調査: 全国的な変動を毎月把握
- 地方調査: 都道府県別の変動を毎月把握
- 特別調査: 常用労働者1〜4人の小規模事業所を対象に年1回実施
調査内容
- 常用労働者数
- 出勤日数
- 労働時間(所定内・所定外)
- 現金給与額(きまって支給する給与、超過労働給与、特別に支払われた給与)
調査結果の活用
- 景気動向判断の経済指標
- 雇用保険や労災保険の給付額改定の資料
- 国民所得や県民所得の推計資料
- 公共料金改定の際の資料
- 企業の賃金改定や人件費算定の参考
- 日本の労働事情の海外への紹介
最新の調査結果(令和6年分)
- 現金給与総額: 348,182円(前年比2.9%増)
- 一般労働者: 453,445円(3.2%増)
- パートタイム労働者: 111,842円(3.8%増)
- 所定外労働時間: 10.0時間(2.8%減)
- 常用雇用: 1.2%増
労働経済動向調査
厚生労働省が実施する一般統計調査で、景気の変動が雇用や労働時間などに及ぼす影響や今後の見通しを調査し、労働経済の変化や問題を迅速に把握することを目的としています
労働経済動向調査(厚生労働省HP)
調査の特徴
- 四半期ごとに実施される
- 主要産業の30人以上の民営事業所から抽出して調査
- 雇用、労働時間、今後の見通し、対応策などを調査
最近の調査結果(2023年5月)
- 正社員等の労働者過不足判断D.I.:+44ポイント
- パートタイム労働者の労働者過不足判断D.I.:+28ポイント
- すべての産業で労働者不足が継続
産業別の特徴
- 正社員等労働者の不足が最も顕著な業種:
- 運輸業、郵便業(+58ポイント)
- 建設業(+55ポイント)
- 医療、福祉(+54ポイント)
- パートタイム労働者の不足が最も顕著な業種:
- 宿泊業、飲食サービス業(+56ポイント)
- 生活関連サービス業、娯楽業(+46ポイント)
- サービス業(他に分類されないもの)(+43ポイント)
賃金事情等総合調査
中央労働委員会が実施する一般統計調査で、主に大企業の賃金や労働条件に関する情報を収集することを目的としています。
賃金事情等総合調査(厚生労働省HP)
調査の概要
- 目的:中央労働委員会が取り扱う労働争議の調整の参考資料とするため
- 対象:原則として資本金5億円以上、労働者1,000人以上の企業から独自に選定
- 実施機関:中央労働委員会事務局総務課広報調査室
- 周期:年1回(一部の調査は2年に1回)
主な調査内容
- 賃金事情調査
- 賃金体系、諸手当の内容
- 賃金改定額と配分状況
- 年齢ポイント別の所定内賃金水準
- 春闘の賃金妥結状況
- 一時金(賞与)の支給実績
- 労働時間、休日・休暇調査(2年に1回)
- 所定労働時間
- 年間休日日数
- 時間外労働・休日労働の割増賃金率
- 特別休業・休暇制度
- 年次有給休暇の取得状況
- 退職金、年金及び定年制事情調査(2年に1回)
- 退職一時金制度
- 退職年金制度
- 定年制度
- 継続雇用制度
特徴と留意点
- 調査対象が大企業に限定されているため、日本の全企業の実態を反映したものではない
- 労働争議調整の参考資料として使用されることが主目的
- 通常の統計調査とは異なる目的、対象選定、集計手法を用いている
景気動向指数
景気の現状把握や将来予測に資するために作成された経済指標です。毎月、内閣府で作成されます。
生産、雇用など様々な経済活動での重要かつ景気に敏感に反応する指標の動きを統合することで作成されます。
景気動向指数(内閣府HP)
主な指数
景気動向指数には主に2種類の指数があります。
- コンポジット・インデックス(CI)
- 景気変動の大きさやテンポ(量感)を測定
- 2015年を100として算出
- ディフュージョン・インデックス(DI)
- 景気の各経済部門への波及の度合い(波及度)を測定
- 改善している指標の割合を算出
3つの系列
それぞれの指数は、以下の3つの系列に分類されます。
- 先行指数:景気に先行して動く傾向がある
- 一致指数:景気とほぼ一致して動く傾向がある
- 遅行指数:景気に遅れて動く傾向がある
利用方法
- 一致指数:景気の現状把握に利用 → 有効求人倍率
- 先行指数:数カ月先の景気動向予測に利用 → 新規求人倍率
- 遅行指数:事後的な確認に利用 → 完全失業率
まとめ
これ以外にも、選択肢の1つとして、行政関係の資料からの出題がありますが、主要なものをまとめました。
賃金関係の調査資料が多く、混同しがちですので特徴を捉えて覚えましょう。
実際に調査概要に目を通すとイメージが湧きやすいと思います。
試験勉強頑張りましょう!!
この記事が良いと思ったら
↓❤️のクリックお願いします。ブログ運営の励みになります。