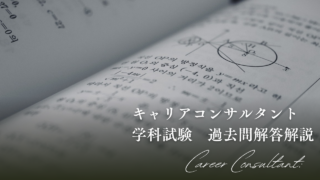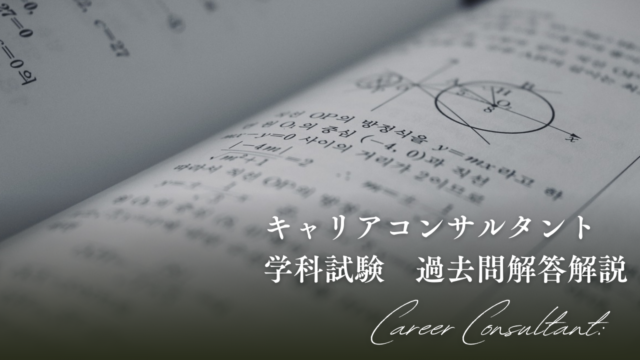第31回 キャリアコンサルティング技能検定 2級学科試験 解答(問31〜35)
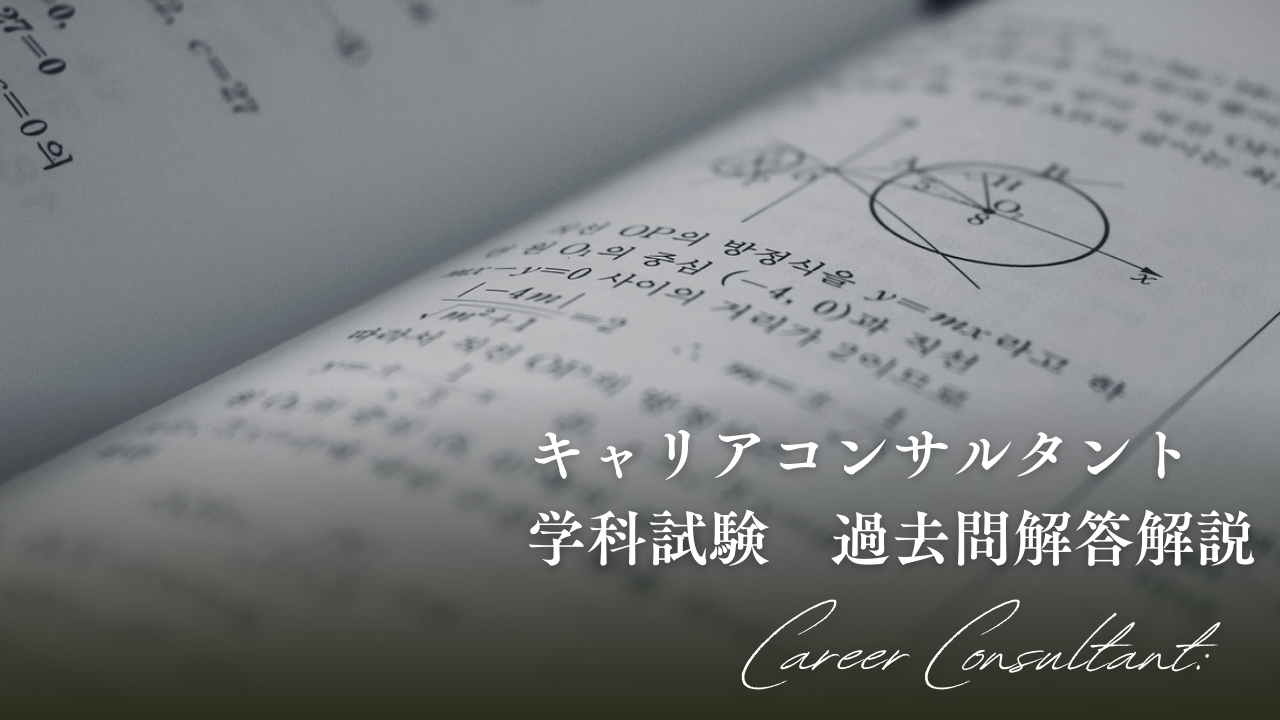
この記事について
第31回 キャリアコンサルティング技能検定 2級学科試験 回答解説を作成しました。
解答は出ていますが、解説がなかったので自分で解答解説作成しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしていこうと思います。
問31
正解:2
選択肢1:不適切
国立がん研究センターの推計(2015年)では、新たにがんと診断されている者のうち、約3割が就労世代(20~64歳)である。(P27)
選択肢2:適切
脳卒中を発症し、手足の麻痺といった後遺症を有する労働者の中には、職場復帰後、発症前の自身とのギャップに悩み、メンタルヘルス不調に陥る場合があることが指摘されている。
選択肢3:不適切
心疾患は、治療後も継続的な配慮が必要ですが、職場復帰できるケースも多くあります。ガイドラインでは、心疾患の治療と仕事の両立支援についても言及されています。
選択肢4:不適切
難病患者の就労状況について、「実際に就労しているのは難病患者の1割にも満たない」という記述は正確ではありません。難病患者の多くが就労可能であり、治療技術の進歩に伴い、難病を抱えていても、症状をコントロールしながら就労することが可能な場合があり、難病患者の56%が就労しているとの報告もあります。(P41)
問32
正解:4
選択肢1:不適切
キャリアコンサルティングの基本的な流れは、4ステップではなく、以下6ステップで進みます。
- 自己理解
- 仕事理解
- 啓発的経験
- 意思決定
- 方策の実行
- 新たな仕事への適応
選択肢2:不適切
指示、論理的帰結、解釈、自己開示、助言、情報の提供、説明、教示などは「積極技法」に分類されます。この技法は、クライエントを行動に導くために使われます。
マイクロカウンセリングにおけるかかわり技法は、クライエントの話を丁寧に聴き、理解を深めるために用いられ、以下のようなものを指します。
クライエント観察技法、質問技法、はげまし、いいかえ技法、要約技法、感情の反映、意味の反映。
選択肢3:不適切
この記述は共感的理解ではなく、自己一致(純粋性)の説明に近いものです。共感的理解とは、クライエントの内的な枠組みを理解し、その感情や経験を自分のことのように感じ取ることを指します。
選択肢4:適切
傾聴の意義として、クライエントとキャリアコンサルタントの間に信頼関係が築かれ、クライエントが安心して自分の本音を語り、内面を探ることができるようになります。
傾聴はキャリアコンサルティングにおいて非常に重要な技術であり、クライエントの自己探求と成長を促進する上で不可欠な要素です。
問33
正解:2
選択肢1:適切
単純な受容の正確な説明です。聴き手は話し手の感情に焦点を当て、最小限の言葉で応答します。これにより、話し手は自分の話を聞いてもらっていると感じ、さらに話を続けやすくなります。
選択肢2:不適切
正しくは、話し手の感情を聴き手が理解し、それを言葉で返すことを指します。
聴き手自身の感情を表明することは、「自己開示(セルフディスクロージャー)」と呼ばれます。自己開示は、聴き手が自分の感情や考えを率直に伝えることで、相手との信頼関係(ラポール)を深め、相互理解を促進するコミュニケーション技法です。
選択肢3:適切
繰り返し(リフレクション)の正確な説明です。話し手の言葉をそのまま、または要約して繰り返すことで、理解を確認し、さらなる探求を促します。
選択肢4:適切
感情の明確化の正確な説明です。話し手の感情や意図を、より明確な言葉で表現し返すことで、自己理解を深める助けとなります。
問34
正解:3
選択肢1:不適切
グループの規模が大きくなると、一般的に各メンバーが発言や吟味に使える時間は減少します。大規模なグループでは、個々のメンバーの参加機会が制限される傾向があります。
選択肢2:不適切
セッション時間を一律に2時間以上と定めるのは適切ではありません。セッション時間は、グループの目的、参加者の特性、扱うテーマなどに応じて柔軟に設定されるべきです。
選択肢3:適切
グループアプローチの本質を正確に表現しています。メンバー間の率直な感情や理解の共有は、グループの効果を高める重要な要素です。この相互作用により、自己理解や他者理解が深まり、新たな気づきや成長が促進されます。
選択肢4:不適切
グループの初期段階では、通常メンバーはリーダーに依存する傾向があります。各メンバーの独自性が発揮されるのは、グループが成熟した後の段階です。
問35
正解:4
選択肢1:不適切
抵抗は参加者の自然な反応であり、指導者の未熟さだけが原因ではありません。
選択肢2:不適切
参加への抵抗は、文書での同意の有無に関わらず発生する可能性があります。
選択肢3:不適切
評価への抵抗は、単なる説明や説得だけでは十分に対応できない場合が多いです。
選択肢4:適切
変化への抵抗は、新しい行動や自己像に対する不安や恐れから生じるものです。これはグループワークにおける重要な概念で、参加者が慣れ親しんだ行動パターンや自己認識から離れることへの不安を表しています。
2級技能士 解説リンク集
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。