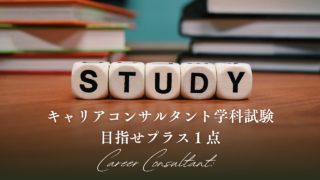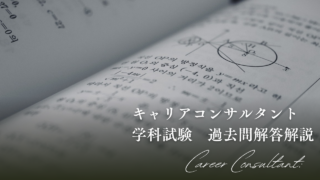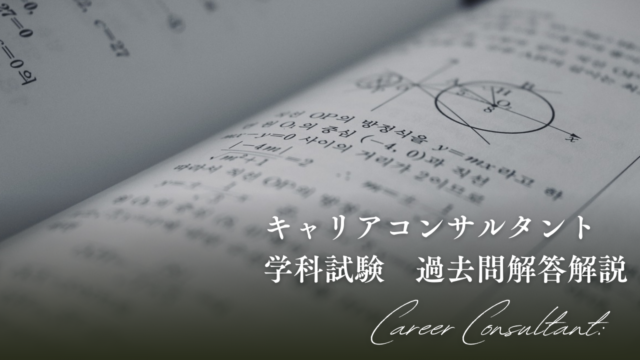第31回 キャリアコンサルティング技能検定 2級学科試験 解答(問26〜30)
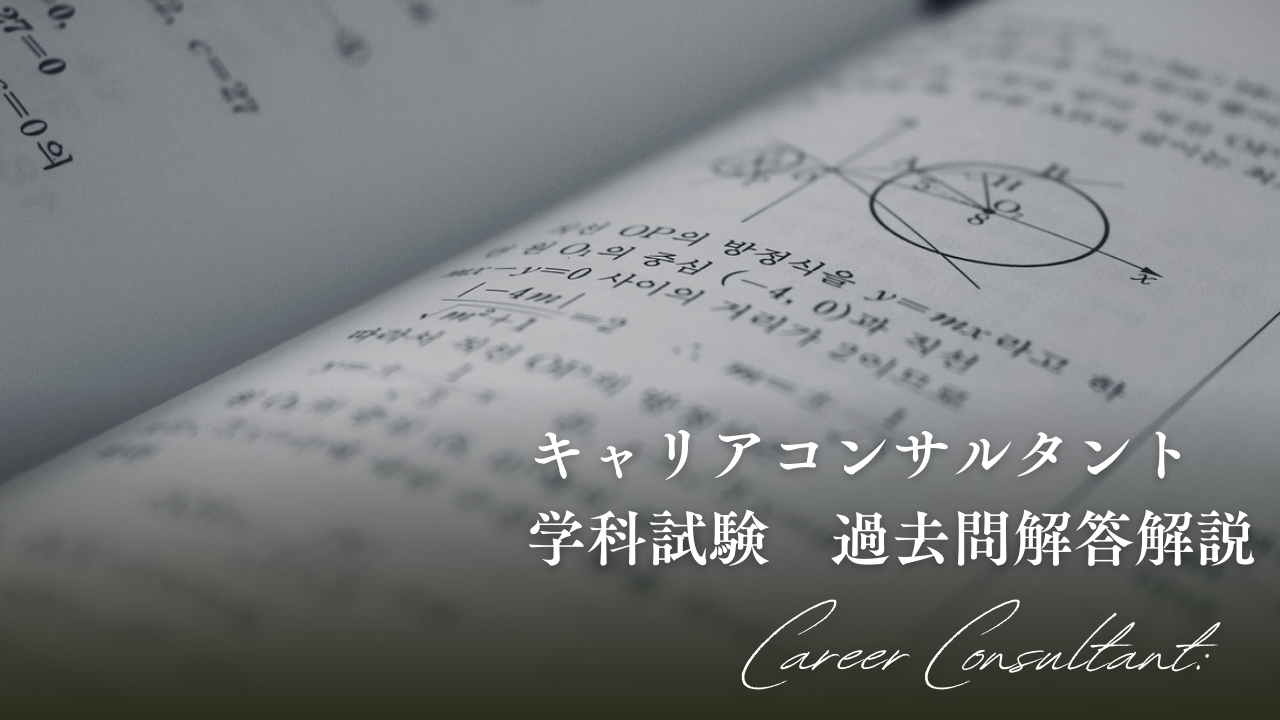
この記事について
第31回 キャリアコンサルティング技能検定 2級学科試験 回答解説を作成しました。
解答は出ていますが、解説がなかったので自分で解答解説作成しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしていこうと思います。
問26
正解:4
選択肢1:不適切
ユングが人生を4段階に分けたという記述は正しいですが、「人生の谷間」という概念はユングではなくレビンソンによるものです。ユングは40歳代を「人生の正午」と呼び、重要な転換期として位置づけました。
選択肢2:不適切
generativity(生殖性、世代継承性、次世代の育成力)はエリクソンの理論における中年期の発達課題であり、ユングの理論ではありません。
選択肢3:不適切
この記述はユングの理論に近いものですが、エリクソンの理論とは一致しません。
シャドウとは、個人の無意識に存在する人格の「否定的」側面を指します。
また、ユングは40代を「人生最大の危機」「自己や将来の生き方について深く考える時期」「人生の午前から午後への移行期」としています。
選択肢4:適切
エリクソンは、精神分析の生物学的発達論に対して、個人と社会との相互作用による「心理・社会的側面」を重視したライフ・サイクル論を展開しました。
つまり、個人の発達は単に生物的に成長するだけでなく、その人が属する社会や他者との関係性の中で生じる課題や役割の変化によっても左右されるとしています。
エリクソンは人生を8つの発達段階に分け、それぞれの段階で「心理社会的課題」(例えば、乳児期の「基本的信頼vs不信」、青年期の「自我同一性vs役割の拡散」など)があり、その課題に対処し乗り越えることが、人格の成長や社会的適応につながると説きました。つまり、個人の心理的発達は社会的経験や対人関係を通じて進行し、生涯を通じて発達課題を克服していくプロセスと捉えています
問27
正解:2
選択肢1:不適切
スーパーとサビカスの役割が逆になっています。
選択肢2:適切
この選択肢は正確に理論の発展を説明しています。スーパーがキャリア・アダプタビリティの概念を提示し、サビカスがそれをキャリア構築理論の中に取り入れました。
選択肢3:不適切
サビカスとスーパーの役割が逆になっており、また「ライフスパン」は正しい用語ではありません。
選択肢4:不適切
「ライフテーマ」と「連続的意思決定理論」は、この文脈では適切ではありません。
【プラス1点の知識】
キャリア・アダプタビリティの最初の提唱者はスーパー
キャリア・アダプタビリティと言えば「サビカス」が浮かんできますが、最初の提唱者はスーパーなので、引っかからないようにしましょう。
キャリア・アダプタビリティを最初に提唱したのは、アメリカの心理学者ドナルド・E・スーパーです。スーパーは、キャリア研究の第一人者として知られており、キャリアの基礎理論を多数発表し、多くの人に影響を与えました。
スーパーは1950年代にキャリア構築や職業選択を定義付けした独自の理論「キャリア発達理論」を打ち立て、その中でキャリアアダプタビリティの概念を提案しました。しかし、スーパー自身はこの概念を体系化する前に他界しました。
その後、アメリカの心理学者マーク・L・サビカスがスーパーの遺志を継ぎ、キャリアアダプタビリティの概念を発展させ、体系化しました。サビカスは「キャリア構築理論」を唱え、その中でキャリアアダプタビリティを重要な概念の一つとして位置づけました。
このように、キャリアアダプタビリティの概念は、スーパーによって提唱され、サビカスによって発展・確立されたものです。
問28
正解:1
選択肢1:適切
組織社会化の定義として適切です。組織社会化とは、個人が組織の一員となるために必要な知識や技術を習得し、組織に適応していくプロセスを指します。
選択肢2:不適切
組織社会化には新規参入者の主体的な関与も重要です。単に受動的な存在である必要はありません。
選択肢3:不適切
「プロアクティブ行動」は、新規参入者が主体的に行う行動を指し、組織側の働きかけではありません。これは、「社会化戦略」「社会化戦術」の説明です。
選択肢4:不適切
「社会化戦略」や「社会化戦術」は、組織が新規参入者の適応を促すために用いる方法を指し、個人の主体的な行動を指すものではありません。これは、「プロアクティブ行動」の説明です。
問29
正解:2
選択肢1:適切
シュロスバーグの理論では、「状況」は転機に対処する能力に影響を与える4つの要因(4S)の1つです。転機の原因や社会的な時宜性は、状況を吟味する上で重要な要素です。
選択肢2:不適切
シュロスバーグの理論では、「自己」には個人の内的特性だけでなく、年齢や社会的地位などの客観的な個人的特徴も含まれます。これらの外的な特徴も転機への対処能力に影響を与えると考えられています。
選択肢3:適切
「周囲の援助」は4Sの1つであり、転機を乗り越えるための支援や援助の有無、その範囲を吟味することは重要です。
選択肢4:適切
「戦略」も4Sの1つで、転機に対処するための行動や方法を指します。多様な戦略を用いることや、状況を変化させる行動を取ることは、転機への対処に有効とされています。
問30
正解:3
選択肢1:不適切
青年期に始まるひきこもりと思春期年代の不登校・ひきこもりには、共通の側面が存在する可能性があります。
選択肢2:不適切
思春期の主たる発達課題は、一般的に「自我同一性の確立」や「親からの心理的自立」などが挙げられます。「両親との愛着形成」は乳幼児期の課題です。
選択肢3:適切
同性仲間集団への適応における失敗は、子どもに強い挫折感と恥の感覚を経験させ、その結果として仲間関係や学校生活を回避し、家にとどまる原因となる可能性があります。これは、ひきこもりの一因となり得る重要な要因です。
選択肢4:不適切
家族を揺さぶる問題が生じている場合、思春期の子どもが家庭にしばりつけられる可能性はあります。家庭内の問題から逃れられず、外部との接触を避けるようになることもあります。
2級技能士 解説リンク集
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。