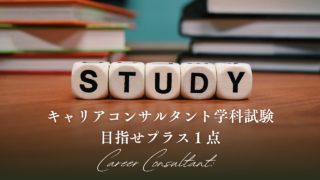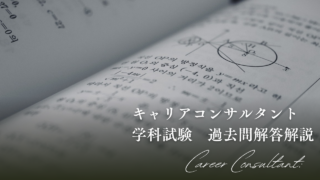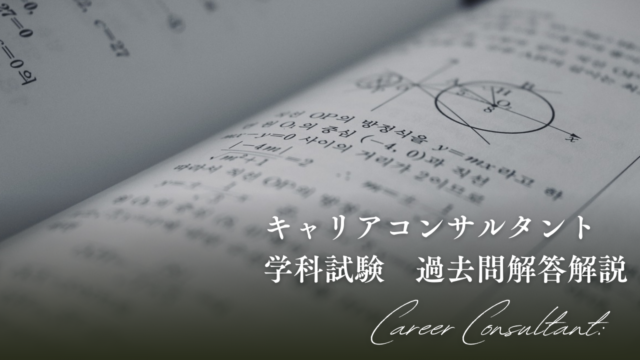第31回 キャリアコンサルティング技能検定 2級学科試験 解答(問11〜15)
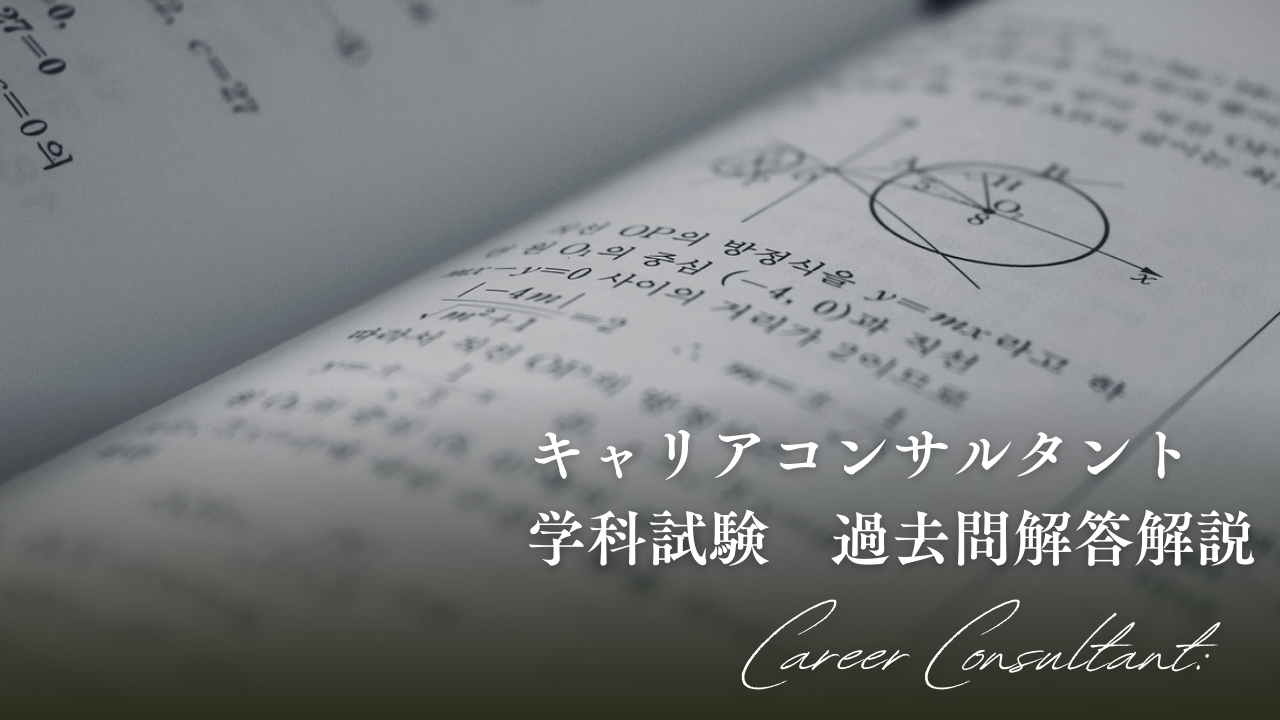
この記事について
第31回 キャリアコンサルティング技能検定 2級学科試験 回答解説を作成しました。
解答は出ていますが、解説がなかったので自分で解答解説作成しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしていこうと思います。
問11
正解:4
選択肢1:不適切
実際は逆で、「公共職業訓練」は主に雇用保険受給者を対象とし、「求職者支援訓練」は主に雇用保険を受給できない求職者を対象としています。
選択肢2:不適切
ひきこもり地域支援センターは、ひきこもりに特化した第一次相談窓口として機能していますが、必ずしもひきこもり経験のあるキャリアコンサルタントが支援コーディネーターとして相談支援を行うわけではありません。
選択肢3:不適切
地域若者サポートステーション(サポステ)の対象年齢は、15歳から49歳までです。25歳以下に限定されているわけではありません。
選択肢4:適切
セルフ・キャリアドックは、企業と従業員の双方の視点を考慮し、従業員の主体的なキャリア開発を支援する仕組みです。これは、組織の成長と個人の成長を両立させることを目指しています。
問12
正解:3
選択肢1:不適切
日本の企業内人材開発は、一般的にOJT(On-the-Job Training)を重視してきたことで知られており、これが現場力の高さにつながってきました。
選択肢2:不適切
ガイドラインでは、労働者の自律的・主体的な学び・学び直しを重視しつつも、企業と労働者の協働が必要であることを強調しています。
選択肢3:適切
ガイドラインでは、学び・学び直し後の能力・スキルの発揮機会の提供や適切な評価の重要性が強調されています。
選択肢4:不適切
ガイドラインでは、現場のリーダーの役割の重要性が強調されており、特に学び・学び直しの方向性・目標の擦り合わせにおいて、現場のリーダーが重要な役割を果たすことが示されています。
問13
正解:4
選択肢1:不適切
出向の場合、出向元との雇用関係を維持しつつ、出向先とも新たな雇用関係を結ぶ複雑な労働形態です。
選択肢2:不適切
派遣労働者の部分は正確ですが、請負労働者は請負会社とのみ雇用契約を結び、発注者(委託会社)とは雇用契約を結びません。
選択肢3:不適切
社内FA制度は、社員が自身の意思で異動や転籍を叶える人事制度のことを指します。新しい事業計画の募集とは異なります。
選択肢4:適切
社内公募制度は、新たに人材を確保したい各部署がオープンに人材を募集し、新たなキャリア構築に挑戦したい社員が自発的に応募できるようにする制度です。
問14
正解:1
選択肢1:適切
「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(厚生労働省、令和3年3月)では、実際にテレワークを「労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務」と定義しています。
選択肢2:不適切
テレワークの形態は、ガイドラインによると3つに分類されています。①在宅勤務、②サテライトオフィス勤務、③モバイル勤務です。
選択肢3:不適切
「令和4年度テレワーク人口実態調査」(国土交通省)の結果によれば、雇用型就業者のテレワーカーの割合は全国で26.1%であり、半数を超えていません。
選択肢4:不適切
「令和4年度テレワーク人口実態調査」の結果によれば、雇用型就業者のテレワーカーの割合は、通勤時間が長くなるほど高くなっています。特に通勤時間が「1時間30分以上」の場合、テレワーカーの割合が54.3%と最も高くなっています。
- 通勤時間30分未満:13.5%
- 通勤時間30分~1時間未満:27.4%
- 通勤時間1時間~1時間30分未満:45.0%
- 通勤時間1時間30分以上:54.3%
問15
正解:1
選択肢1:適切
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、2022年7月に改定され、副業・兼業を希望する労働者が安心して取り組めるよう、労働時間管理や健康管理等について示しています。このガイドラインは、副業・兼業の場合における労働時間管理や健康管理のルールを明確化し、労働者の希望に応じた副業・兼業が可能な労働環境を整備することを目的としています。
選択肢2:不適切
「副業者の就労に関する調査」によると、副業者の本業の就業形態は、「非正社員」が41.0%で最も多く、次いで「正社員」が38.1%、「非雇用者」が20.9%となっています。
選択肢3:不適切
「副業者の就労に関する調査」の結果によると、副業者の主な副業の職種について、最も多いのは「サービス職業」ではなく、「専門的・技術的職業」です。
選択肢4:不適切
副業・兼業に関する裁判例では、労働時間以外の時間の使い方は基本的に労働者の自由であるとしていますが、一切の制限を許さないとまでは言っていません。企業は安全配慮義務や秘密保持義務、競業避止義務に留意しながら、副業・兼業を許容する方向で検討することが求められています。
2級技能士 解説リンク集
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。