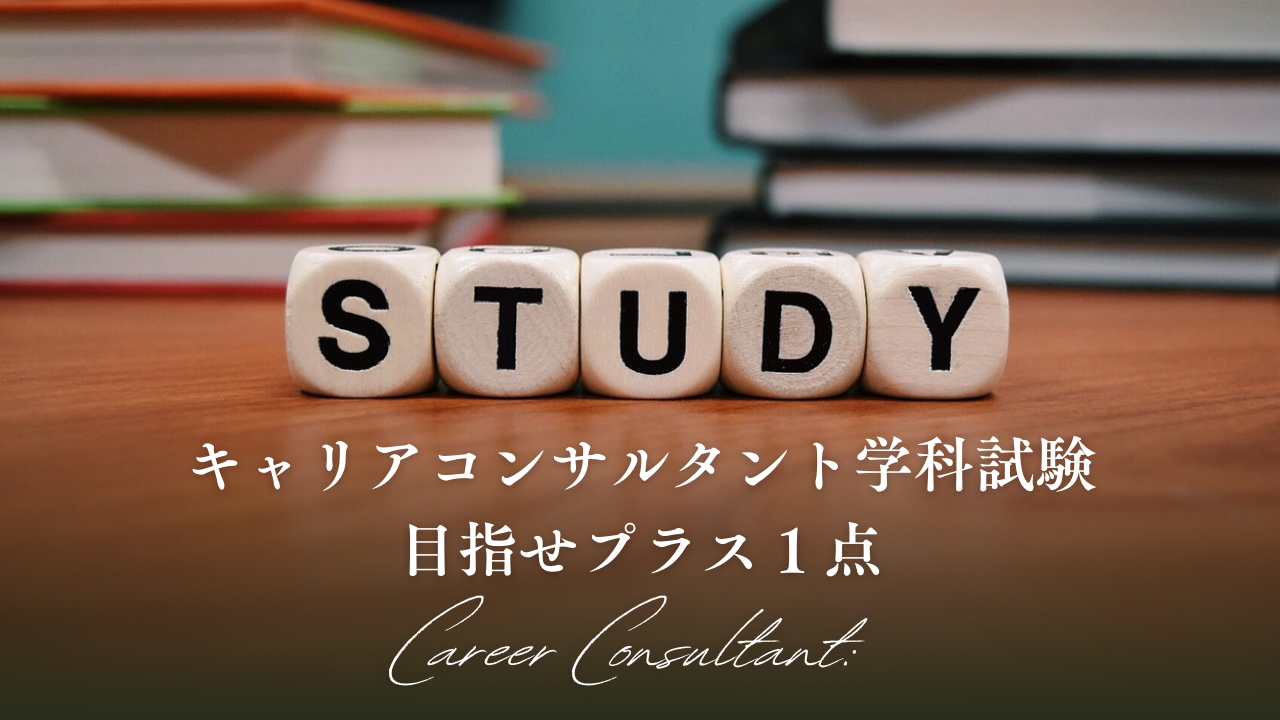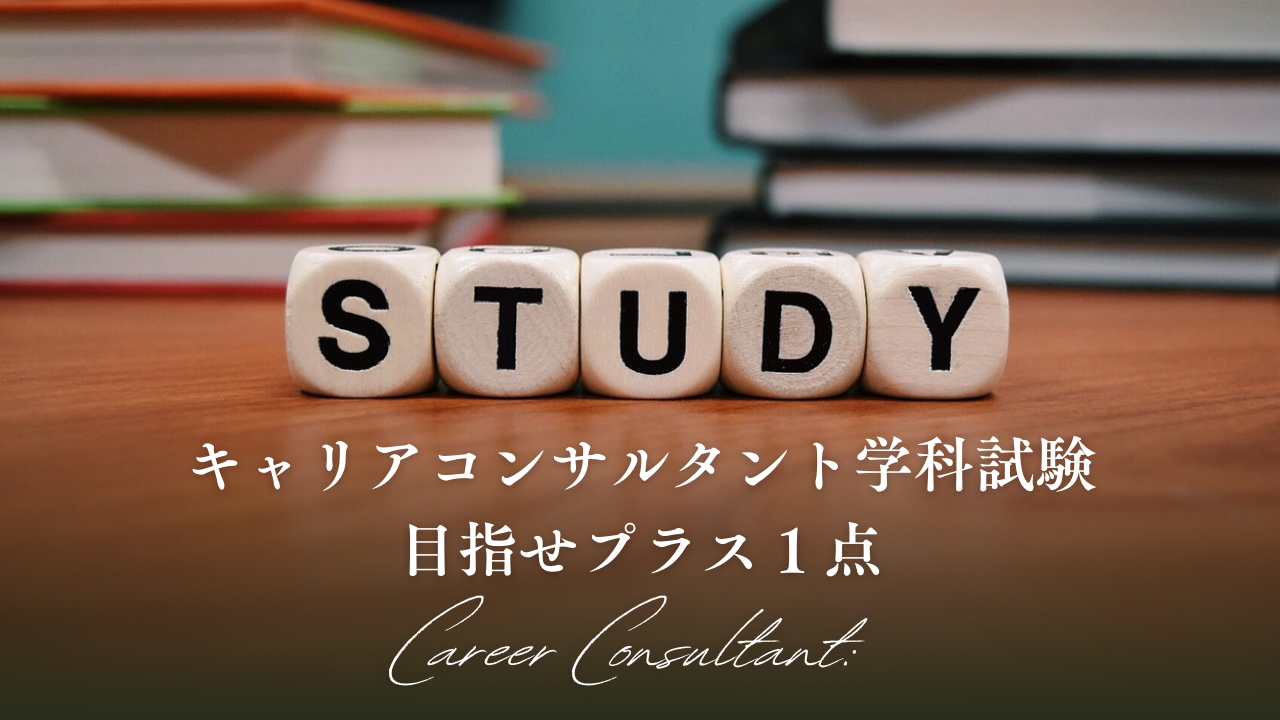心理検査の信頼性と妥当性は、心理学的評価の質を保証する重要な基準となっています。
ここでは両概念について詳しく解説し、代表的な検査方法もまとめます。
信頼性について
信頼性(reliability)とは、心理検査の結果が一貫していて安定しているか、つまり「同じ条件で受検した際に、ほぼ同じ結果が得られるか」を示す指標です。
- 主な種類
- 内的一貫性:複数の質問項目が一貫した結果を示しているかどうか。
- 再検査信頼性:同じ人が一定期間後に検査を受けた際、結果が類似しているかどうか。
- 平行検査信頼性:似た内容の別バージョンでも結果が一致するかどうか。
- 評定者間信頼性:複数評価者による一貫性があるかどうか。
妥当性について
妥当性(validity)は、「検査が本当に測りたい特性を的確に測定しているか」を示す指標です。「何を測っているか」が重要ポイントとなります。
- 主な種類
- 内容的妥当性:質問内容が測定目標に一致しているか。
- 基準関連妥当性:他の基準となる指標との関係性による妥当性。
- 構成概念妥当性:理論的な構成概念をどれだけ反映しているか。
代表的な心理検査法
心理検査には多数の種類が存在し、目的や評価したい項目によって方法が選ばれます。
- 質問紙法
- Y-G性格検査
- MMPI
- ビッグファイブ性格検査(5因子性格)
- 投影法
- ロールシャッハ・テスト
- SCT(文章完成法)
- TAT(絵画統覚検査)
- 描画テスト
- バウムテスト(樹木画テスト)
- HTPPテスト(家・樹木・人物描画法)
- 人物画テスト
- 作業検査法
- 内田クレペリン精神作業検査
- ベンダー・ゲシュタルトテスト
- 知能・発達検査
- WAIS(成人用知能検査)
- WISC(児童用知能検査)
- 発達障害検査(AQなど)
まとめ
心理検査の質を保証するためには、信頼性(安定して再現性のある結果)と妥当性(本当に測りたいものを測定できていること)の両方が不可欠です。
代表的な心理検査は目的ごとに多様ですが、診断や支援のためには信頼性と妥当性を確認して選定することが重要です。