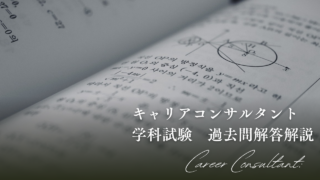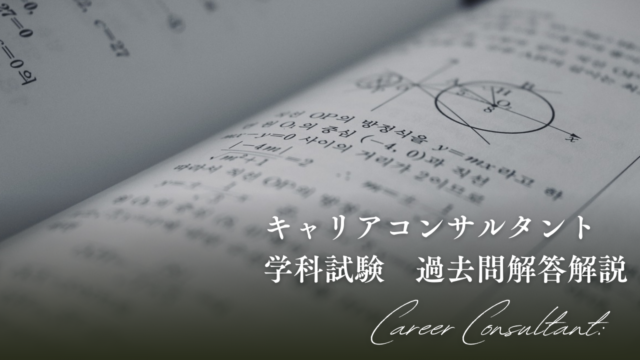第28回 国家資格キャリアコンルタント試験 学科試験 解答解説(問41〜45)
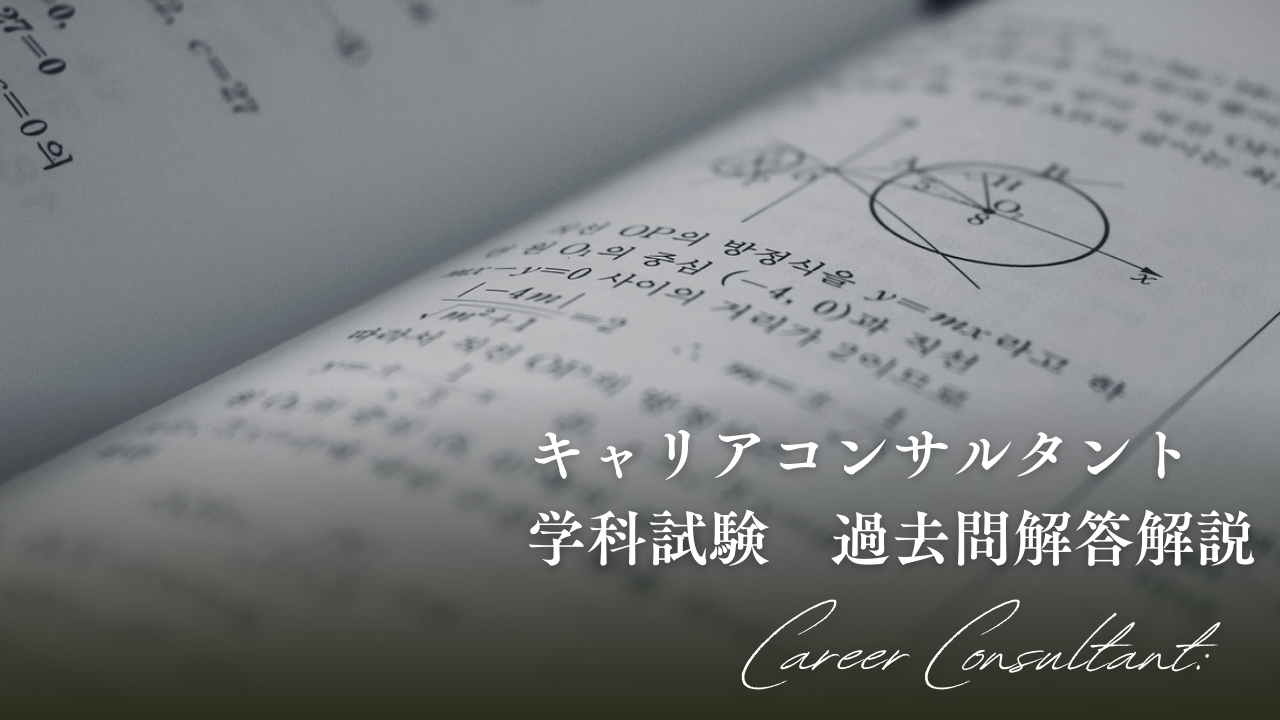
この記事について
令和6年3月実施
第28回 国家資格キャリアコンサルタント試験 解説を作成しました。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしています。
問41
正解:2
選択肢1:適切
選択肢2:不適切
職業分類において職業とは、個人が行う仕事で、報酬を伴うか又は報酬を目的とするものをいう。
ただし、自分が属する世帯の家業に従事している家族従業者が行う仕事は、報酬を受けているかどうかにかかわらず、一定時間(例えば、一日平均2時間、あるいは通常の就業者の就業時間の3分の1以上の時間等)当該仕事に従事している場合には、その仕事を職業とみなす。
選択肢3:適切
選択肢4:適切
問42
正解:3
選択肢1:適切
選択肢2:適切
選択肢3:不適切
職業体験は主に若者や就職未経験者を対象にし、定年退職者に対する職業意識の向上や働く意義の理解の促進は職業体験の主な目的ではありません。定年退職者は既に長年の職業経験を持つことが多く、職業体験の必要性は若者と異なります。
選択肢4:適切
問43
正解:1
選択肢1:不適切
ラポール(信頼関係)の構築はキャリアコンサルティングの初期段階で非常に重要です。心理的な関係を確立することでクライエントが安心して自己開示できるようになり、その後の問題把握や目標設定が円滑に進むため、ラポール形成を軽視することは望ましくありません。
選択肢2:適切
選択肢3:適切
選択肢4:適切
問44
正解:3
選択肢1:不適切
このアプローチは短期的には学業に集中できるかもしれませんが、長期的な目標の具体化を先送りにすることは不適切です。目標達成のための計画を立てることが重要です。
選択肢2:不適切
キャリアコンサルタントが情報を提供することは有益ですが、クライエントの自主性を尊重し、自分で情報を収集し判断する能力を育てることも重要です。クライエントが主体的に情報を集め、選択するプロセスを支援することが望ましいです。
選択肢3:適切
目標を具体的かつ段階的に設定し、達成基準を明確にすることで、クライエントは現実的な計画を立て、進捗を確認しながら目標に向かって進むことができます。
選択肢4:不適切
クライエントの意欲を尊重することは重要ですが、現実的に実行が難しい行動を推進することは適切ではありません。現実的な課題とその解決策を一緒に検討し、実行可能な計画を立てることが必要です。
問45
正解:4
選択肢1:不適切
応用行動分析(ABA)に基づくアプローチでは、「仕事を探す気が起きない」と訴える求職者に対して、感情に焦点を当てるのではなく、行動の「きっかけ」と「結果」に注目することが一般的です。具体的には、以下のような方法が考えられます。
行動の「きっかけ」にアプローチする
- 行動のきっかけを提示する
- 求職活動を促すための具体的なきっかけを提供します。
- 例えば、求職活動のための環境を整えることや、具体的な目標設定を支援することなどです。
行動の「結果」にアプローチする
- 行動の結果に「いいこと」を提示する(=強化)
- 求職活動を行った際に、肯定的なフィードバックやインセンティブを提供することで、行動を維持・増やすことを目指します。
- 例えば、職業カウンセラーによるサポートや、成功体験を共有する機会を提供するなどです。
選択肢2:不適切
クライエント中心療法では、クライエント自身の視点や感情を尊重し、クライエントが自分のニーズや価値観に基づいて選択することを支援することが重要です。
クライエント中心療法のアプローチ
クライエントの希望を理解する
- 求職者が「事務職を希望する」という言葉の背後にある理由やイメージを深く理解するために、オープンな質問を行います。
- 例えば、「事務職」というのはどのようなイメージを持たれているのか、具体的にどのような仕事が求められているのかを探ります。
クライエントと共に探求する
- 求職者と一緒に、どのような特徴を持つ事務職が自分に合っているかを探り、選択肢を広げるのではなく、求職者自身が自分の価値観やニーズに基づいて選択できるように支援します。
選択肢3:不適切
精神分析理論に基づくアプローチでは、「上司がどうしても好きになれない」と訴える求職者に対して、過去の経験を分析することが重要です。
精神分析では、過去の経験や無意識の感情が現在の行動や感情に影響を与えていると考えられています。したがって、過去の経験を探求し、その影響を理解することで、求職者が自分の感情や行動をより深く理解できるようになります。
ただし、未来のありたい姿に向けて検討することも重要です。精神分析では、過去の経験を理解した上で、現在と未来についての新たな視点や選択肢を模索することが求められます。
精神分析理論に基づくアプローチ
- 過去の経験を分析する
- 求職者が「上司が好きになれない」と感じる理由を探り、過去の経験や無意識の感情が影響している可能性を考察します。
選択肢4:適切
正しい説明です。自動思考を明確にし、適切な思考を検討させることで、大学生の不安を軽減し、自信を高めることが可能です。
自動思考の明確化
- 自動思考の特定
- 大学生が「社会人としてやっていけるか不安である」と感じる際に、どのような自動思考が働いているかを特定します。例えば、「自分は社会人として失敗する」というようなネガティブな思考が存在するかもしれません。
適切な思考の検討
- 認知再構成
- 自動思考を認識した後、認知再構成を通じて、より適切でバランスの取れた思考に置き換えます。例えば、「自分は社会人として失敗する」という思考を「自分は学び続け、成長できる」というように再構成します。
行動実験
- 新たな思考が実際に機能するかを確認するために、行動実験を行います。例えば、社会人としての役割を模したシミュレーションを行い、成功体験を積むことで自信を高めます。
国家試験 第28回 解説リンク集
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。