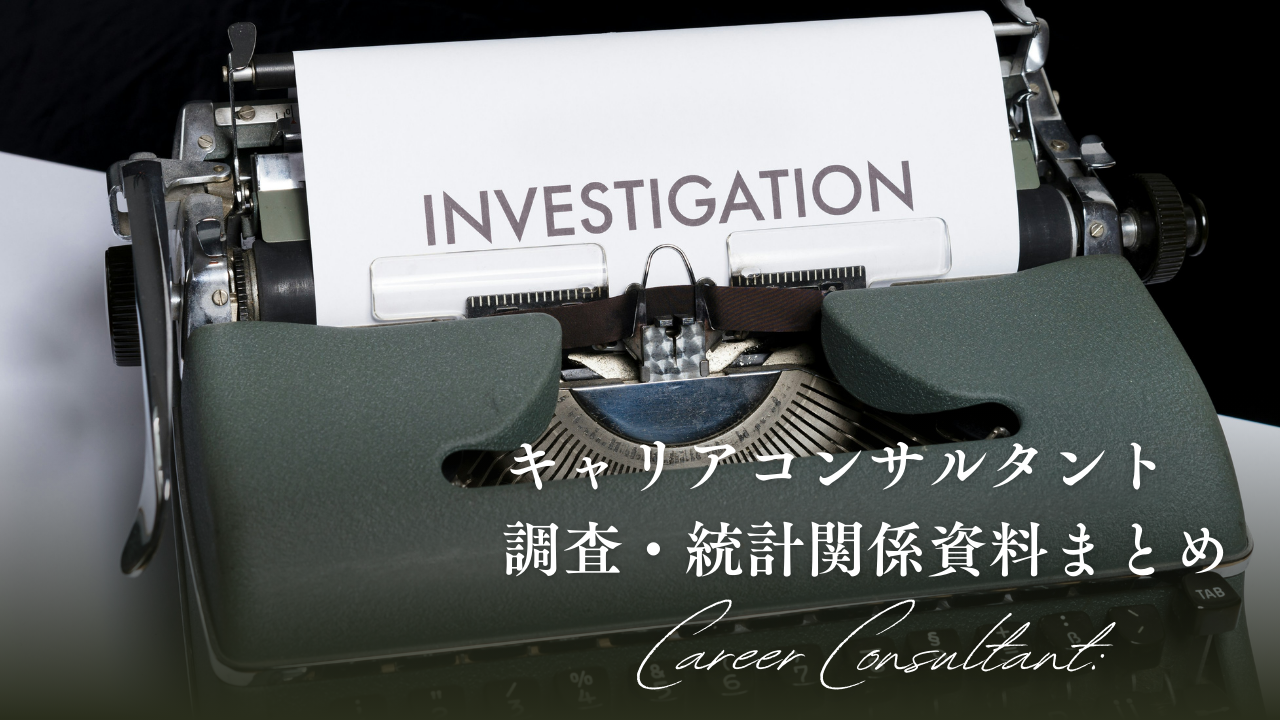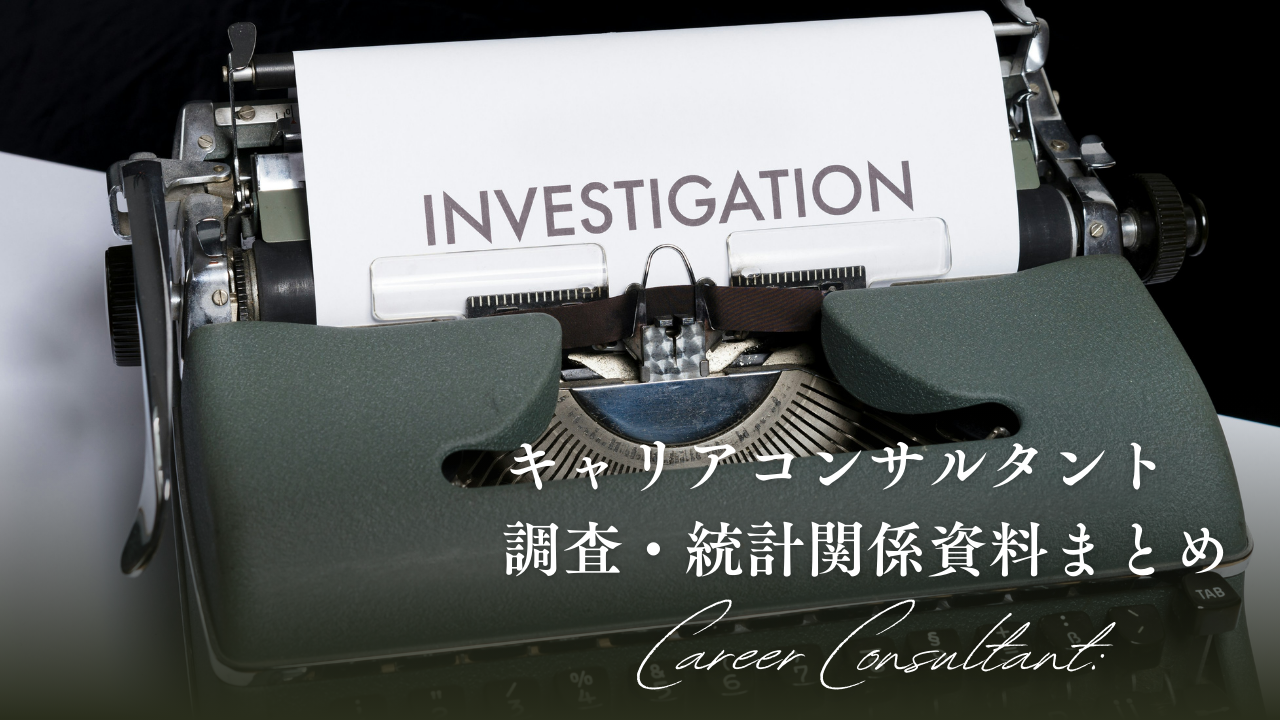この記事について
令和6年労働経済の分析で「労働需給ギャップのプラス幅は縮小傾向かマイナスで推移」と書かれていますが、自分の中で理解できなかったので整理します。
プラスだの、マイナスだの、ギャップだの、混乱するので、わかりやすく整理します。
労働需給ギャップのプラス幅が「縮小傾向」とは
労働需給ギャップのプラス幅が「縮小傾向」とは、もともと人手不足(需要が供給を上回る状態)があったが、その差が徐々に小さくなっている、つまり人手不足の度合いが少し和らいできていることを意味します。
「マイナスで推移」とは
一方、「マイナスで推移」とは、労働力供給が需要を上回っている状態、つまり人手過剰や失業気味の状態が続いていることを指します。
日本の2025年時点の需給ギャップ
日本の2025年時点の需給ギャップでは、日銀の試算でマイナス幅が20四半期連続(5年以上連続)で続いており、人手過剰や需要不足の状態が続いているとされています。
ただし、内閣府の試算などでは需給状況が変動し、一部ではプラスへ向かう見通しもあるため、状況は複雑です。
まとめ
- プラス幅縮小:もともと需給ギャップがプラス(人手不足)だったのが、だんだん差が小さくなっているという状態。
- マイナスで推移:需給ギャップがマイナスの状態が続き、供給過多で労働力が余っている状態。
両方の表現は、異なる期間や指標の見方によるもので、需給バランスの変化や時間軸の違いによって使い分けられていることが多いです。