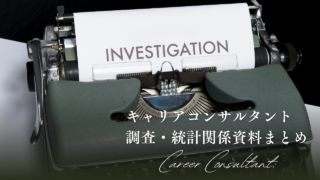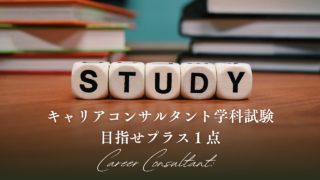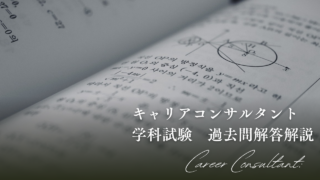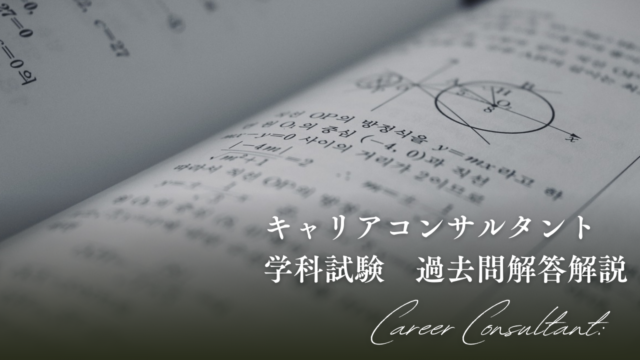第29回 国家資格キャリアコンルタント試験 学科試験 解答(問11〜15)
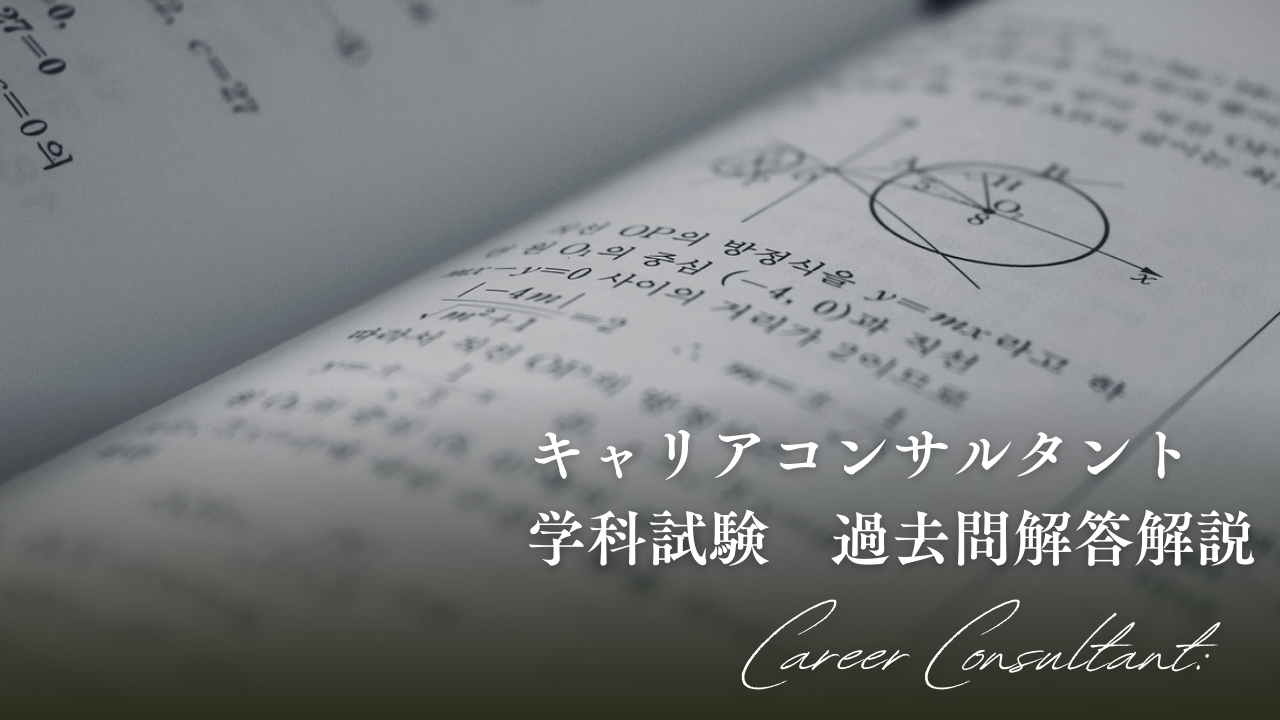
この記事について
第29回 国家資格キャリアコンサルタント試験 解説を作成しました。
過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしていこうと思います。
問11
正解:4
選択肢1:不適切
患者の気づきであり転移の効果に近いが逆転移ではない。
選択肢2:不適切
患者の感情が分析者に移される「転移」にあたる。
選択肢3:不適切
分析者が患者の無意識を理解する過程であり逆転移の定義ではない。
選択肢4:適切
精神分析の「逆転移」とは、患者が分析者に感情を向ける「転移」に対し、分析者(カウンセラーやセラピスト)が患者に対して無意識に生じる感情や反応を指します。具体的には、分析者が患者からの感情や態度に影響されて、自身の無意識的な感情反応を抱くことを意味します。
問12
正解:4
選択肢1:不適切
指定を行うのは「厚生労働大臣」です
選択肢2:不適切
給付率は、講座の種類や条件によって20%、40%、50%、さらに条件達成時に70%~80%にもなります。たとえば一般教育訓練(20%)、特定一般教育訓練(40%)、専門実践教育訓練(50%~70%、80%)などで、最大で80%となります。
選択肢3:不適切
専門職大学院やビジネススクールなどの大学院課程でも対象となるものがあります。大学院課程の一部は専門実践教育訓練に指定されています。
選択肢4:適切
失業中で初めて専門実践教育訓練(通信制・夜間制を除く)を受講し、かつ45歳未満などの要件を満たすと、「教育訓練給付金」に加えて「教育訓練支援給付金」が支給されます
問13
正解:4
選択肢1:不適切
セルフ・キャリアドックは年齢や昇進などキャリアの節目ごとに行われ、新入社員だけでなく中堅社員やベテラン社員、管理職など幅広く対象となります。特定の層だけでなく、すべての従業員の主体的なキャリア形成を支援する制度です
選択肢2:不適切
制度の本来の目的は、従業員が「長期的に」主体的なキャリア形成を行うための支援であり、キャリア形成の習慣や目標づくりをサポートするものです。短期的な業績アップだけを重視する趣旨ではありません。
選択肢3:不適切
人事評価が主目的ではなく、従業員本人がキャリアを見直し主体性を持った職業生活設計を進めるための支援制度です。企業の評価制度や昇進判定とは異なるものです。
選択肢4:適切
セルフ・キャリアドックとは「企業が従業員に対してキャリアコンサルティングと多様なキャリア研修等を定期的に実施し、労働者の主体的なキャリア形成を支援する仕組み」を指します。働く人が自分のキャリアを振り返り、必要なサポートを企業が提供することで従業員の成長と働きがいの向上を図る典型的な制度です。
問14
正解:2
選択肢1:適切
ガイドラインは「自律的・主体的かつ継続的な学び・学び直し」および「労使の協働の必要性」を明確に強調しています。
選択肢2:不適切
ガイドラインは、企業による研修のみならず「労働者の自律的・主体的な学び直し」の重要性を何度も説いており、「企業研修だけで十分」とはまったく言っていません。「主体的な学び直し」が不可欠です。
選択肢3:適切
ガイドライン・別冊ともに、職務に必要なスキルの明確化や教育プログラムの提供など、企業が果たすべき役割の具体例として記載されています。
選択肢4:適切
別冊や厚生労働省の特設サイト等では、「職業能力評価基準」「ジョブ・カード」などの公的な支援策の活用が具体的に列挙されています。
問15
正解:1
選択肢1:不適切
第11次職業能力開発基本計画では「業界横断的」あるいは「業界・職種ごとに共通した職業能力評価基準(=共通基準)」の整備や、それを活かした客観的評価の推進が打ち出されています。企業独自の評価基準の重視は、むしろ時流に逆行する内容です。実際の計画では業界共通の評価基準や職業能力証明制度(ジョブカード等)の活用が明記されています。
選択肢2:適切
IT人材、デジタル技術活用人材の育成強化は計画の最重要テーマの一つとして明記されています。
選択肢3:適切
人生100年時代や産業構造変化への対応として「リスキリング」「主体的キャリア形成支援」などの文言が何度も強調されています。
選択肢4:適切
全員参加型社会の実現を掲げており、非正規雇用・女性・高齢者・障害者・外国人など多様な人材への支援が打ち出されています。
国家試験 第29回 解説リンク集
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。