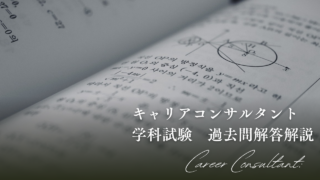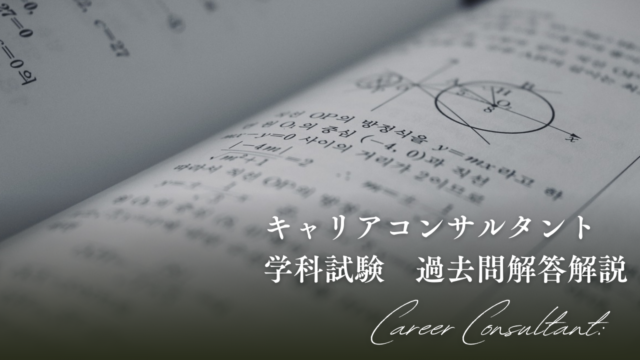第27回 国家資格キャリアコンルタント試験 学科試験 解答解説(問31〜35)
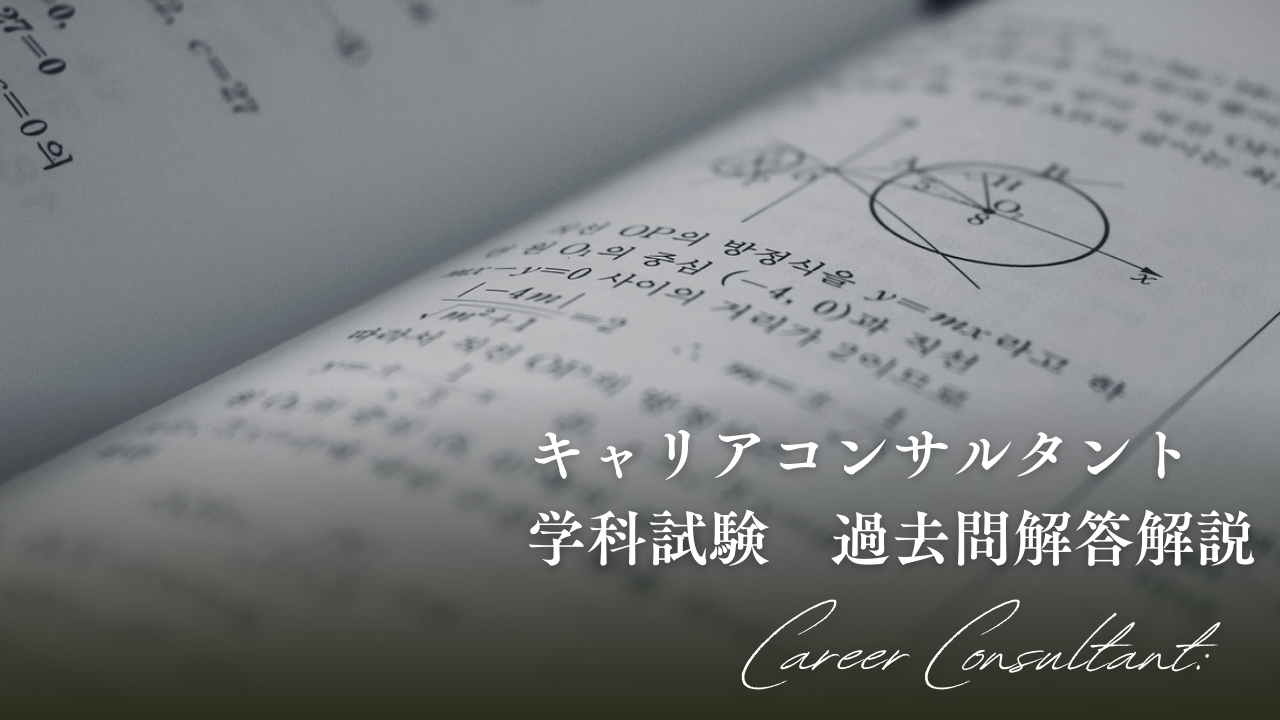
この記事について
第27回 国家資格キャリアコンサルタント試験 解説を作成しました。
過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしています。
問:31
正解:1
選択肢1:不適切
労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施義務は、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に課されています。85名であれば実施義務がある。
選択肢2:適切
ストレスチェックの結果、高ストレス者で面接指導が必要と認められ、かつ労働者から申出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施する義務があります。
選択肢3:適切
面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要に応じて就業場所や労働時間の変更等の就業上の措置を講じることは、事業者の義務です。
選択肢4:適切
ストレスチェックの集団分析結果を活用して職場環境の改善を図ることは、制度の主旨に沿った推奨される取り組みです。
問:32
正解:2
選択肢1:不適切
多文化キャリアカウンセリングの基礎は、クライエントではなくカウンセラー自身のバイアスの自覚にある。
選択肢2:適切
多文化キャリアカウンセリングでは、カウンセラー自身の文化的な価値観や無意識のバイアスを十分に自覚し、それがクライエントとの関わりにどのような影響を及ぼすかを認識することが基礎となる。
ナンシー・アーサーやSueらの理論でも、まずカウンセラー自身のバイアスの自覚が重要とされている。
選択肢3:不適切
カウンセラーは自らのバイアスや無意識の偏見を認識することが求められている。
選択肢4:不適切
クライエントのバイアスを意識させるかどうかは多文化キャリアカウンセリングの基礎ではなく、カウンセラー自身のバイアスの自覚が重要である。
問:33
正解:1
選択肢1:不適切
ひきこもりはDSM-IV(アメリカ精神医学会の診断基準)で定義された病名ではなく、厚生労働省のガイドラインでも「疾病」や「診断名」ではなく、社会的参加を回避し6か月以上家庭にとどまる現象概念とされています。
選択肢2:適切
厚生労働省ガイドラインによると、ひきこもりは「社会的参加(就学、就労、交友など)を回避し、原則6か月以上家庭にとどまり続けている状態」と定義されています。
選択肢3:適切
ひきこもりの原因は複合的であり、いじめや家族関係、病気など様々な要因が絡み合って生じることが多いとされています。
選択肢4:適切
ひきこもりが長期化すると社会経験の機会が失われるため、復帰には再チャレンジの支援体制や支援者の存在が重要であるとガイドラインでも述べられています。
問:34
正解:1
選択肢1:適切
「○○について話してくれませんか」という問いかけは、相手に自由な回答を促す典型的な開かれた質問(オープンクエスチョン)である。
選択肢2:不適切
開かれた質問は、相手が自由に考えたり感じたことを話すことができる質問であり、クライエントに自由な発言を促すものである。
選択肢3:不適切
開かれた質問は、答えが一つに定まらず自由度が高いため、答え始めるまでに時間がかかることがある。
選択肢4:不適切
開かれた質問であっても、相手に質問の意図が明確に伝わるようにすることは重要である。
問:35
正解:4
選択肢1:適切
カウンセラーの自己開示とは、自分の体験や感情をクライエントに伝えることを指し、マイクロカウンセリングにおける技法の一つである。
選択肢2:適切
カウンセラーがその場で感じたことを適切に表明することで、クライエントの心が開かれやすくなる効果があるとされている。
選択肢3:適切
自己開示は、カウンセラーが共感的にクライエントと関わり、対等な立場で問題解決に取り組む姿勢の表明ともいえる。
選択肢4:不適切
自己開示は、クライエントの利益やカウンセリングの目的に沿って適切に行う必要があり、恥ずかしいことや道徳的に疑問のある体験まで全てを包み隠さず開示するのは不適切である。
国家試験 第27回 解説リンク集
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。