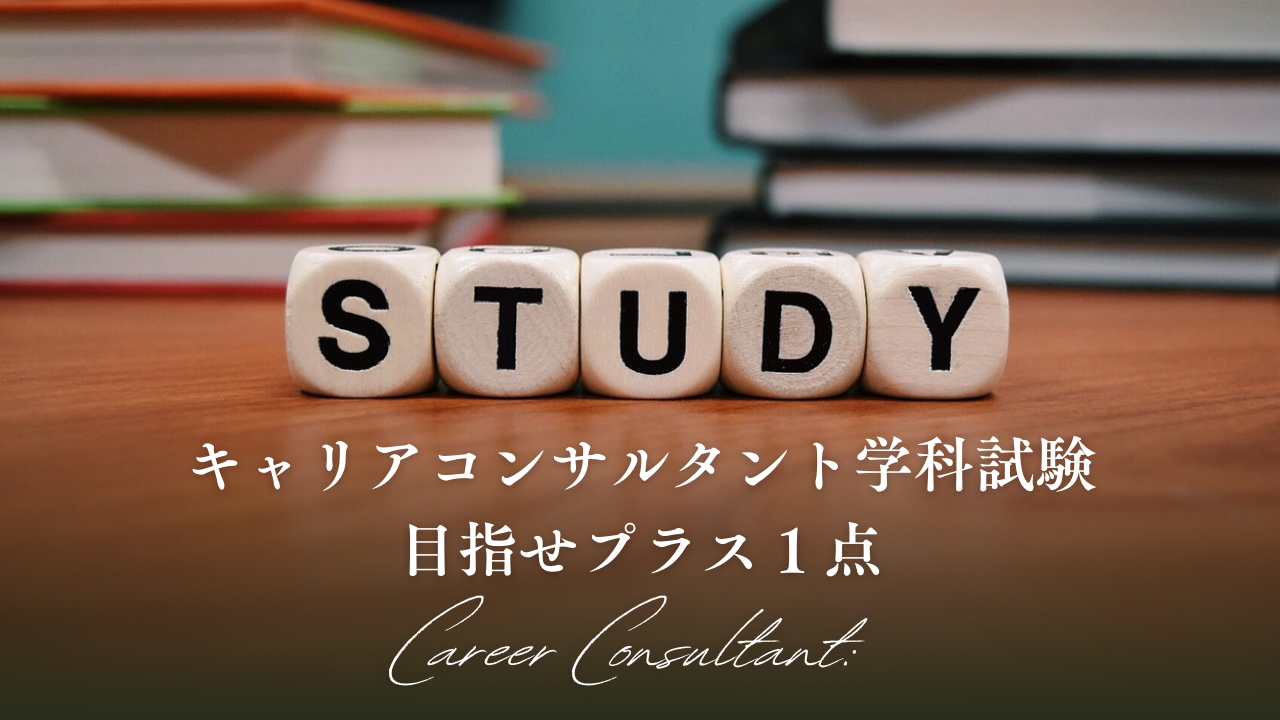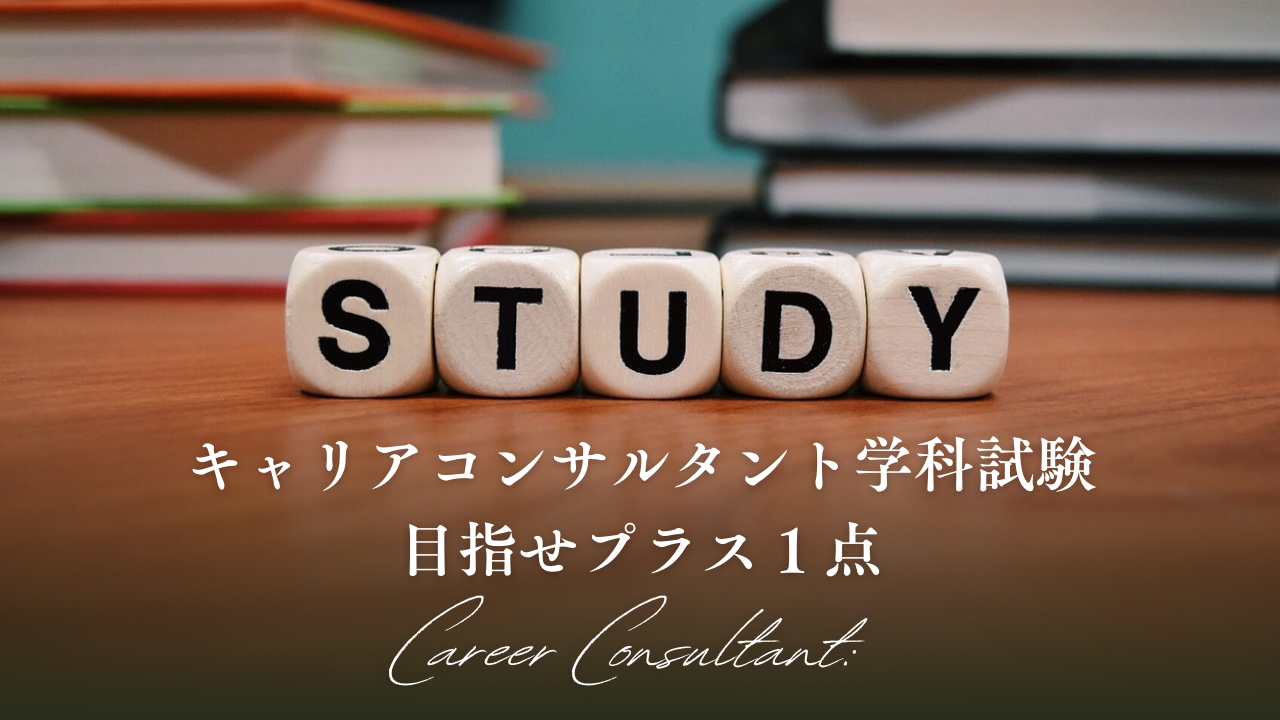アサーショントレーニングとレスポンデント条件付けの関係
アサーショントレーニングがレスポンデント条件付け(古典的条件付け)に基づくとされる理由は、「不安や緊張を引き起こす対人状況」に対して、新たな主張的行動(アサーティブな反応)を結びつけることで、従来の不安反応を減弱・消去するという学習理論に立脚しているためです。
アサーショントレーニングは、もともと対人恐怖や不安を感じやすい状況(例:人前で意見を言う場面)で、従来は「緊張」や「不安」といった反応(R1)が自動的に生じていたところに、訓練を通じて「自己主張的行動(アサーション)」という新しい反応(R2)を結びつけます。
これは「拮抗条件付け」や「逆制止」と呼ばれる手法で、刺激(対人場面)に対して本来の不安反応に代わって、主張的行動やリラックス反応が生じるようにするものです。
この過程は、パブロフの犬の実験に代表される「レスポンデント条件付け(古典的条件付け)」の原理に基づいています。
すなわち、ある刺激に対して自動的に生じていた情動反応(不安・緊張)を、別の新しい反応(アサーション)に置き換えることを目指します。
「自己主張的であるときには、同時に臆病にはならないという、逆抑止の考え方が根幹にあります。以前に不安を引き起こした状況で自己主張的行動がとれるように訓練し、不安に関連する反応を低減させることを目的とします。」
したがって、アサーショントレーニングは「不安や緊張を呼び起こす刺激」に対して「主張的行動(アサーション)」という新しい反応を条件付けることで、不安や緊張を減らし、適応的な行動を促進する技法であり、これがレスポンデント条件付けに基づくとされる理由です。
補足
アサーショントレーニングは古典的条件付けだけでなく、ロールプレイや行動リハーサルといったオペラント条件付け的要素も取り入れられることが多いですが、基本的な理論的枠組みはレスポンデント条件付けです。