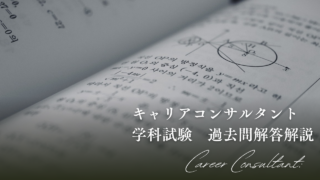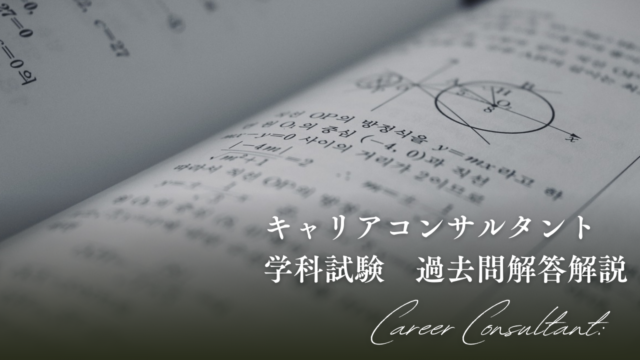第31回 キャリアコンサルティング技能検定 2級学科試験 解答(問16〜20)
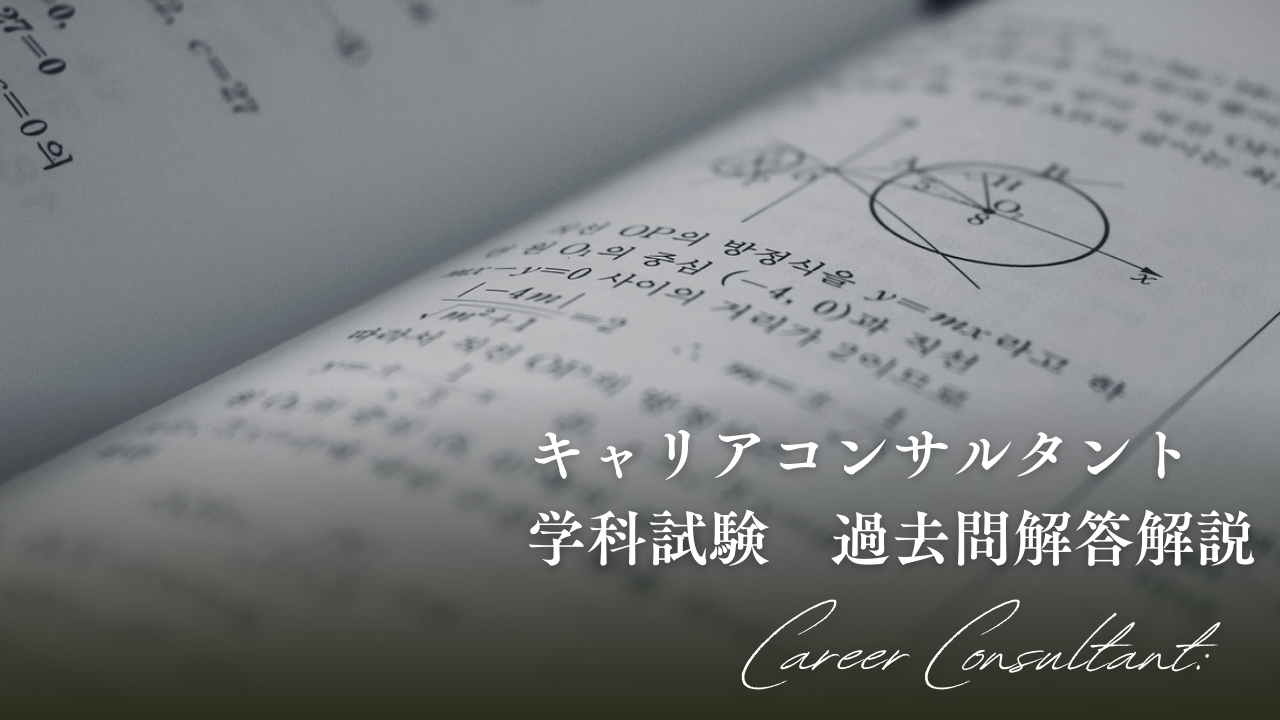
この記事について
第31回 キャリアコンサルティング技能検定 2級学科試験 回答解説を作成しました。
解答は出ていますが、解説がなかったので自分で解答解説作成しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしていこうと思います。
問16
正解:2
選択肢1:不適切
2022年の統計によると、男性の失業率の方が女性よりも高くなっています。具体的には、2022年の平均失業率は男性が2.6%、女性が2.3%でした。このデータから、2022年において男性の失業率の方が女性よりも0.3ポイント高かったことがわかります。
選択肢2:適切
2022年の有効求人倍率は1.28で、2021年から0.15ポイント上昇しました。これは4年ぶりの上昇であり、新型コロナウイルスパンデミックによる経済活動の停滞からの回復を反映しています。
選択肢3:不適切
2023年3月の職業別有効求人倍率(常用(含パート))は、一般事務の職業が0.51倍、自動車運転の職業が2.15倍となっています。一般事務の職業は1を下回っており、求職者数が求人数を上回っている状況です。一方、自動車運転の職業は2倍以上の求人があり、人手不足の状況が続いていることがわかります。
選択肢4:不適切
週60時間以上の長時間労働をしている男性の割合は、どの年齢層においても、2005年以降おおむね減少傾向にあります。
問17
正解:2
令和3年「労働安全衛生調査(実態調査) 」の概況
令和5年「労働安全衛生調査(実態調査) 」の概況(事業所)
令和5年「労働安全衛生調査(実態調査) 」の概況(個人)
選択肢1:不適切
メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業または退職した労働者がいた事業所割合は、事業所規模計で10.1%となっており、9割を超えるという記述は誤りです。(P3)
選択肢2:適切
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の取組内容として、「ストレスチェックの実施」が65.2%で最も多くなっています。(P4)
選択肢3:不適切
現在の仕事や職業生活に関することで強い不安やストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は53.3%となっており、1割程度という記述は誤りです。(P13)
選択肢4:不適切
ストレスとなっていると感じる事柄がある労働者について、その内容(主なもの3つ以内)をみると、「仕事の量」が43.2%[同42.5%]と最も多く、次いで「仕事の失敗、責任の発生等」が33.7%[同35.0%]、「仕事の質」が33.6%[同30.9%]となっている。(P13)
注意!!
令和5年度は、「仕事の失敗、責任の発生等」が39.7%で一番多く、次で仕事の量が39.4%と続いている。
令和6年度は、「仕事の量」、「仕事の失敗、責任の発生等」、「仕事の質」の順となっている。
問18
正解:1
選択肢1:適切
育児・介護休業法では、子が1歳に達した時点で保育所に入所できない等の場合、最長2歳まで育児休業を延長できることが定められています。
選択肢2:不適切
配偶者の就業の有無にかかわらず、労働者は育児休業を取得する権利があります。
選択肢3:不適切
「産後パパ休暇」(出生時育児休業)は、原則として子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる育児休業制度ですが、主に男性労働者を対象としています。ただし、養子の場合など特定の条件を満たせば、女性労働者も取得可能です。つまり、一般的な出産後の女性は産後休業中のため対象外ですが、養子を迎えた場合などは女性もこの休暇を取得できる例外があります。
選択肢4:不適切
育児休業は原則として1年以上継続して雇用された労働者が取得できますが、一定の要件を満たせば勤続1年未満の労働者も取得できます。
問19
正解:1
選択肢1:不適切
雇用保険の保険料は、会社と労働者が半々で負担するのではありません。実際には、労働者と事業主がそれぞれ負担する割合が定められています。
選択肢2:適切
労働者災害補償保険(労災保険)の保険料は、全額事業主(会社)が負担します。
選択肢3:適切
健康保険の保険料は、原則として事業主と被保険者(労働者)が折半で負担します。
選択肢4:適切
厚生年金保険の保険料は、事業主と被保険者(労働者)が折半で負担します。
問20
正解:1
選択肢1:適切
法定休日に労働をさせた後に代休日を与える事後の振替を行う場合、使用者は法定休日の割増賃金を支払う義務が生じます。
選択肢2:不適切
あらかじめ振替休日の日を指定した上で特定の法定休日を労働日とする事前の休日振替を適切に行った場合、法定休日の割増賃金の支払いは不要です。
選択肢3:不適切
労働基準法は、毎週少なくとも1回の休日を与えることを定めていますが、必ずしも決まった曜日である必要はありません。
選択肢4:不適切
労働基準法上の労働時間規制が適用除外となる管理監督者については、法定休日に関する規定も適用されません。
2級技能士 解説リンク集
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。