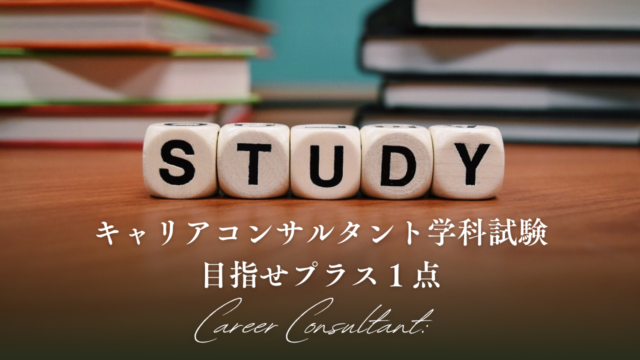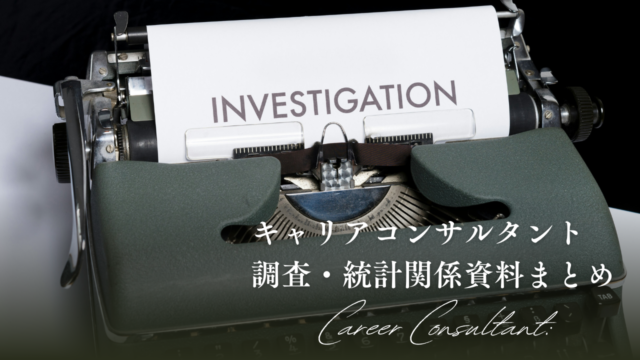【キャリコン】多文化・社会正義視点の理論 ワッツ/ゴッドフレッドソン/フアド/ナンシー・アーサー/ブルースティン/レヴィン/レオン

Contents
この記事について
キャリアコンサルタントの学科試験には、数多くの理論とその提唱者が出題されています。
この記事では、多文化・社会正義の視点からのキャリア理論とその提唱者をまとめました。
トニー・ワッツ
社会正義のキャリア支援論のパイオニアとして知られています。
彼の理論の中心的な概念は「キャリアガイダンスの4つのイデオロギー」で、1976年に提唱されました。
ワッツが来たら「4つのイデオロギー」が出てくるようにしましょう。
キャリアガイダンスの4つのイデオロギー
ワッツは、キャリア支援を「社会に焦点がある/個人に焦点がある」と「変革を目指す/現状維持を目指す」の二軸で分類し、4つのアプローチを定義しました。
コンサバティブ(社会統制)
- 社会に焦点を当て、現状維持を目指すアプローチ。
- 社会のニーズに合わせて人材を適材適所に配置する。
リベラル(非指示型)
- 個人の自由を尊重し、自己実現を支援するアプローチ(現状維持)。
- 1950年代の自己実現論をベースにしている。
プログレッシブ(個人的変化)
- 個人の変革の可能性を重視するアプローチ。
- 現状に満足せず、個人の成長を追求する。
ラディカル(社会変革)
- 社会そのものの変革を目指すアプローチ。
- 個人ではなく社会に働きかけ、問題解決を図る。
| 現状維持 | 変革 | |
|---|---|---|
| 社会に焦点 | コンサバティブ(社会統制) 社会のニーズに合わせて人材を適材適所に配置する社会統制的アプローチ | ラディカル(社会変革) 社会そのものの変革を目指し、制度や構造に働きかけるアプローチ |
| 個人に焦点 | リベラル(非指示型) 個人の自由や自己実現を支援するアプローチ | プログレッシブ(個人的変化) 個人の成長や変革の可能性を重視するアプローチ |
ラディカル(社会変革)アプローチの重要性
ワッツは特にラディカルアプローチを重視しました。
このアプローチは、キャリア支援において個人だけでなく社会全体の変革を目指す考え方です。
ラディカル(社会変革)アプローチは、個人のキャリア支援を通じて社会全体を少しずつ変革していくという側面を持ち、現代の不安定な社会において重要な視点となっています。
このアプローチを採用することで、キャリアコンサルタントは単なる個人支援にとどまらず、社会変革のリーダーとしての役割を担うことが期待されています。
現代社会におけるワッツ理論の意義
- 個人の問題だけでなく、社会の問題にフォーカスする必要性を強調。
- キャリアコンサルタントの役割を、個人支援から社会変革の担い手へと拡大。
- 非正規雇用や少子高齢化などの社会問題に対して、制度改革や政策提言を通じたアプローチを提案。
ワッツの理論は、これらの点で、現代の不安定な社会において再評価されています。
キャリア支援を通じて社会全体を変革する可能性を示唆し、現代のキャリアコンサルティングの重要な基盤となっています。
リンダ・ゴットフレッドソン
リンダ・ゴットフレッドソンの「限界と妥協理論」は、キャリア選択のプロセスを説明する重要な理論です。
この理論は、キャリアカウンセリングや若者のキャリア発達支援において重要な示唆を与えており、「やりたいこと」だけでなく、現実的な制約や社会的要因を考慮したアプローチの必要性を示唆しています。
リンダ・ゴッドフレッドソンが出てきたら「限界と妥協」が出てくるように。
理論の基本概念
ゴットフレッドソンは、キャリア選択が「限界と妥協」の過程で行われると主張しました。
この理論によると、個人は社会的なステレオタイプや個人的な制約に基づいて職業選択の範囲を狭め、現実的な選択を行います。
4つの主要段階
- 限界設定 性別や社会的地位に基づいて職業選択の範囲を設定する段階。
- 妥協 現実的な制約を考慮して職業選択を修正する段階。
- 探索 自分の興味や能力に基づいて職業選択を具体化する段階。
- 確立 選択した職業においてキャリアを確立する段階。
「排除」原則
ゴットフレッドソンの理論の特徴的な点は、子供のキャリア発達における「排除」原則です。
- 子供は「やりたいこと」ではなく、「やりたくないこと」を排除する形で職業を考える傾向がある。
- この排除のプロセスは「制限(circumscription)」と呼ばれ、発達段階に応じて進行する。
発達段階と排除の基準
- 6〜8歳(小学校低学年): 性別に基づく排除
- 9〜13歳(小学校高学年〜中学生): 職業威信(社会的地位)に基づく排除
- 14歳以降: 職業興味に基づく排除
排除原則の特徴
- 一度排除された選択肢は復活しにくい
- 青年期に自己を追求する時期には、多くの選択肢がすでに排除されている
- 排除された選択肢は視野に入ることすらなくなる
排除原則の背景
- 将来の職業を考えることは子供にとって認知的負荷が高い課題である
- 人間には物事を単純化して捉えようとする認知傾向がある
理論の意義
- 職業に伴う不平等が発達過程で内面化される仕組みを説明している
- キャリア選択における現実的な制約とその影響を強調している
ゴットフレッドソンの排除原則は、子供や若者のキャリア発達プロセスを理解し、適切な支援を行うための重要な視点を提供しています。
フアド
フアド(Nadya A. Fouad)は、異文化キャリアアセスメント論を提唱した職業心理学者です。
この理論は、キャリアカウンセリングにおいて文化的多様性を考慮することの必要性を強調し、より包括的なアプローチを促進しています。
フアドと言えば、「白人中心のキャリア支援に対する批判」
理論の特徴
異文化キャリアアセスメントは、従来のキャリアアセスメントが白人中心主義的であったことへの批判から生まれました。この理論は、多様な文化背景を持つ個人のキャリア発達を適切に理解し支援するために、文化的要因を考慮に入れる必要性を強調しています。
白人中心主義的アプローチの問題点
- アメリカの白人男性を基準としたキャリア発達理論
- 多様な文化背景を持つ人々のニーズや価値観の軽視
- 文化的バイアスを含むアセスメントツールの使用
フアドの主な貢献
- 文化的に適切なキャリアカウンセリング
フアドは、文化的に適切なキャリアカウンセリングの重要性を強調し、カウンセラーが文化的要因を考慮に入れる必要性を主張しました。 - 多文化的コンピテンシー
キャリアカウンセラーが多文化的コンピテンシーを身につけることの重要性を強調しました。 - アセスメントツールの批判的検討
既存のキャリアアセスメントツールの文化的バイアスを指摘し、より包括的なアプローチの必要性を主張しました。 - 社会正義の視点
キャリアカウンセリングにおける社会正義の重要性を強調し、マイノリティグループのキャリア発達支援に焦点を当てました。
フアドの研究は、異文化キャリアアセスメントの発展に大きく貢献し、白人中心主義的なアプローチの限界を克服するための新しい視点を提供しました。
ナンシー・アーサー
キャリア支援における文化的配慮の重要性を強調した理論家です。
文化を取り入れたキャリアカウンセリングモデル(Culture-Infused Career Counseling: CICC)を提唱しました。
ナンシーの理論は、グローバル化が進む現代社会において、異文化間のキャリア支援や、マイノリティのキャリア発達支援に重要な視点を提供しています。
アーサーの研究は、キャリアカウンセリングの分野に文化的視点を導入し、より効果的で公平なキャリア支援の実現に貢献しています。
ナンシー・アーサーが出てきたら、「文化を取り入れたキャリアカウンセリング」が出てくるようにしましょう。
理論の特徴
このモデルは4つの重要な領域から構成されています。
- 自分の文化的アイデンティティを知る
- 他者の文化的アイデンティティを知る
- 作業同盟(カウンセリング関係の構築)に対する文化的な影響を理解する
- 文化的に対応した社会的に公平なキャリア支援を行う
アーサーの理論は、キャリアカウンセリングにおいて文化と社会的公正さを関連づける重要性を強調しています。
ブルースティン
ブルースティンの理論は、キャリア支援における社会正義の重要性を強調しています。
ブルースティンの理論は、従来のキャリア支援が主に「アメリカ白人男性ホワイトカラー」を中心に行われてきたことへの批判から発展し、より包括的で社会正義を重視したアプローチを提唱しています。
「忘れられた半分の声」というワードが出たら、ブルースティン。
理論の特徴
社会階層の重視
キャリア支援において最も重要な要因は「社会階層」であると主張しています。
「忘れられた半分の声」
労働者階級や貧困層など、従来のキャリア理論で見過ごされてきた層に焦点を当てています。
階層による職業意識の違い
- 上位階層:自己実現や能力に合った仕事を重視
- 下位階層:経済的理由が仕事の主な動機
具体的な支援方法
- スキル開発
特に貧困層のクライアントに重要 - 構造化されたグループ支援
孤独感や孤立感の軽減 - メンタルヘルスとキャリアの統合
- 批判的意識の育成
クライアントの自覚と自立性の向上 - 社会的・文化的影響の認識
個人のキャリア形成は、生まれ育った環境や社会階層に深く影響されるという視点。
クルト・レヴィン
レヴィンは「マージナルマン」が有名ですが、この背景には、レヴィン自身のユダヤ人としての経験や、文化的な境界線上にある人々の観察から生まれました。
マージナルマンの概念は、青年期の不安定さや、文化的・社会的な境界線上にある人々の経験を理解する上で重要な視点を提供しています。
また、レヴィンの理論は、多文化共生社会の実現に向けて、異なる文化背景を持つ人々の相互理解と協働を促進する上で重要な示唆を提供しています。
彼のアプローチは、半世紀以上経った現在でも、組織変革や多文化共生の実践において有効性を保っています
レヴィンが出てきた「マージナルマン」が出てくるようにしましょう!
マージナルマン
クルト・レヴィンが提唱したマージナルマン(境界人・周辺人)の概念は、以下のとおりです。
定義
マージナルマンとは、「2つの集団の境界上に立ち止まり、両方の集団に関係していながら、実はどちらにも所属していない人」を指します。
青年期との関連
レヴィンは、この概念を青年期の特徴を示す言葉として心理学に導入しました。青年期を子どもと大人の間にある過渡期と捉え、「子どもと大人の重なり合いのうえに立つ青年」をマージナルマンと呼びました。
特徴
- 社会的に不安定な存在
- 複数の集団や文化の境界線上に位置する
- どの集団にも完全には所属していない
レヴィンの見解
レヴィンは、マージナルマンの状態を否定的に捉えており、「本当の危険はしっかりと足を踏まえる場所のないこと、つまりマージナルマンであり、永遠の青年であることにある」と述べています。
レオン
レオン(Leong, F. T. L.)は、キャリア理論において「多文化キャリアカウンセリング論(Multicultural Career Counseling)」を提唱したことで知られています。
レオンの理論は、キャリア支援において多文化的な視点を重視し、文化や価値観の違いがキャリア選択や発達に与える影響を明らかにしたものです。
多様性を尊重し、個人の文化的背景に即したキャリアカウンセリングの必要性を提唱しています。
レオンと言えば、「欧米人とアジア人ではキャリア観が異なる」という主張をしたということを覚えておきましょう。
理論のポイント
レオンは、「欧米人とアジア人ではキャリア観が異なる」と主張しました。
欧米系は個人主義的な価値観、アジア系は集団主義的な価値観を持つため、キャリアの捉え方や問題認識が異なると述べています。
アジア系はキャリアの問題を単なる個人の問題と考えず、社会や集団との関係性も重視する傾向があると指摘しています。
そのため、キャリア支援やカウンセリングにおいては、各文化の価値観や背景を考慮したアプローチが必要であるとしています。
理論の意義
多文化キャリアカウンセリング論は、従来のキャリア理論がアメリカ白人の主流文化を前提としていたことへの批判から生まれました。
多様な人種・民族・文化的背景を持つクライエントに対して、文化的特性を踏まえた支援の重要性を強調しています。
まとめ
多文化・社会正義の論点については、現在の多文化共生という背景において、非常に重要なものです。
過去問でも頻繁に出題されているので、理論家と理論をセットで覚えておきましょう。
この記事が良いと思ったら
↓❤️のクリックをお願いします。ブログ運営の励みになります。