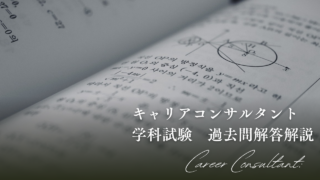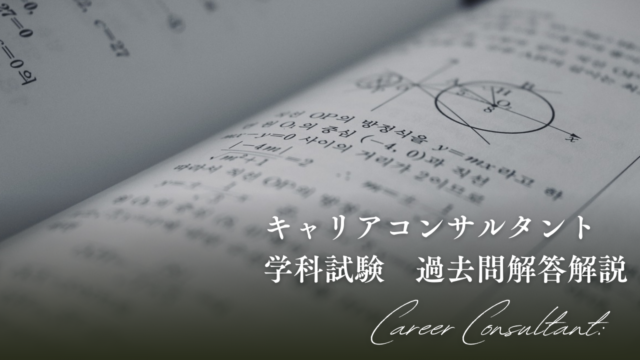第29回 国家資格キャリアコンルタント試験 学科試験 解答(問31〜35)
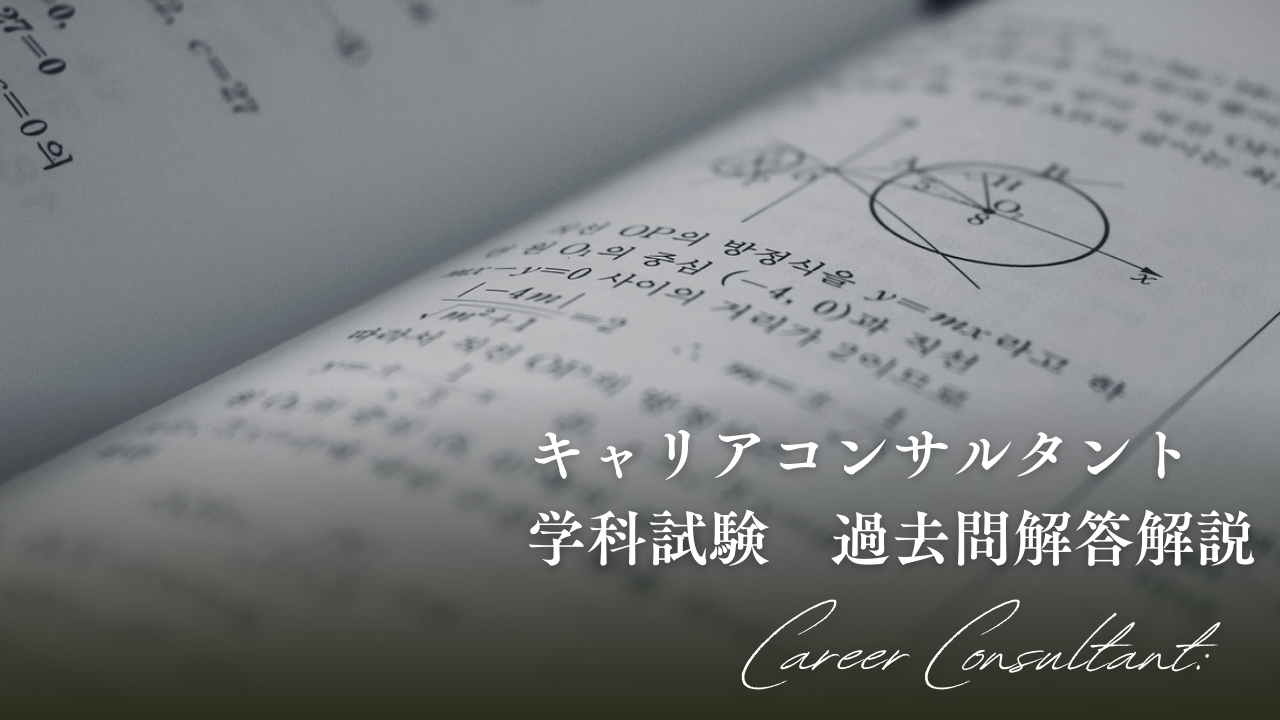
この記事について
第29回 国家資格キャリアコンサルタント試験 解説を作成しました。
過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしていこうと思います。
問31
正解:4
選択肢1:適切
シュロスバーグは、人生の転機を乗り越えるために「4つのS(4つの資源)」—Situation(状況)、Self(自己)、Support(支援)、Strategies(戦略)—を評価し、活用することが重要だと説いています。
選択肢2:適切
スーパーのキャリア発達理論では、成長、探索、確立、維持、解放の5段階のライフステージがあり、その段階間に暦年齢とゆるやかに関連する移行期(トランジション)が存在するとしています。
選択肢3:適切
ブリッジズのトランジション理論は、転機における心理的プロセスとして、まず「終焉(何かが終わる)」、次に混乱や心理的調整が続く「中立圏(ニュートラルゾーン)」、そして新たなスタートを切る「開始」の3段階で構成されると説明しています。
選択肢4:不適切
ジェラットは意思決定理論を提唱し、意思決定過程の中で未来への不確実性や予測可能性に焦点を当てていますが、「過渡期(トランジション)」が職業発達に与える影響を論じたとはされていません。過渡期の概念は主にシュロスバーグやブリッジズなどの理論で使われる用語であり、ジェラットの理論の中心的な枠組みには含まれません。
問32
正解:4
選択肢1:適切
ガイドラインでは、疾病を抱える労働者が就労によって病状を悪化させないように、就業場所の変更、労働時間の短縮、作業内容の調整、深夜業の回数減少等の措置を講じることが基本とされています。これらの措置や配慮なしに就業を継続させることは認められていません。
選択肢2:適切
労働者本人の積極的な治療継続や服薬の遵守、生活習慣の改善といった努力も両立支援の重要な要素として位置づけられています。
選択肢3:適切
個人情報保護の観点から、疾病の症状や治療状況といった機微な個人情報は、本人の同意なしに事業者が取得することは原則として禁止されています。健康診断により把握された情報のみ、明確な法的根拠に基づき取得可能とされています。
選択肢4:不適切
ガイドラインでは、両立支援は労働者本人からの申出を契機に進めることが基本ですが、事業主としては組織全体で両立支援に取り組むためのルール作りや環境整備、啓発活動を行うことが求められています。労働者の申出がない場合でも、両立支援の体制を整える努力義務があり、総じて無対応でよいということはありません。
問33
正解:3
選択肢1:適切
ハローワークでは「精神・発達障害者雇用サポーター」と呼ばれる専門知識を有する職員が配置されており、精神障害のある求職者に対して障害特性に配慮した専門的な相談や支援をきめ細かく実施しています。
選択肢2:適切
発達障害者に対しても同じく「精神・発達障害者雇用サポーター」が配置され、障害特性を理解し、個別に強みや課題に応じた支援を提供しています。
選択肢3:不適切
精神福祉保健センターとハローワークの連携による就労支援は、障害者手帳の有無にかかわらず行われています。精神障害のある人が必ずしも障害者手帳を持っているとは限らず、手帳がなくても支援を受けられる体制が整えられています。
精神障害のある人が障害者手帳を持っていなくても、精神福祉保健センターとハローワークの連携による就労支援を受けられる体制が整備されています。
選択肢4:適切
トライアル雇用助成金において、テレワーク勤務の場合は原則3ヶ月のトライアル期間が最長6ヶ月まで延長可能となっています。ただし、精神障害者は最大12ヶ月まで延長可能であり、この拡充は障害の特性に応じた柔軟な支援を目的としています。
問34
正解:1
選択肢1:適切
「はげまし(encouragement)」の技法の正しい説明です。はげましは、相づちや、うなずきなどの非言語的な反応や、話し手が発した重要なキーワードを繰り返すことでクライエントの話を促し、話しやすい雰囲気を作る技法です。相手の話を続けさせる目的で使われます。
選択肢2:不適切
これは「言い換え(paraphrasing)」に該当する技法の説明です。
選択肢3:不適切
これは「要約(summarizing)」の技法の説明です。
選択肢4:不適切
これは「感情の反映(reflection of feeling)」に該当する技法の説明です。
問35
正解:3
選択肢1:適切
クライエント中心療法の中心概念である実現傾向は、人間が自己の可能性を最大限に発揮し、成長しようとする内在的な力を指します。
選択肢2:適切
クライエント中心療法では、共感的理解が重要であり、カウンセラーの感情への注意と適切な応答がクライエントの安心感や満足感につながります。
選択肢3:不適切
クライエント中心療法は自己決定と自己の成長を尊重し、カウンセラーがクライエントの判断を「正しい方向」に導くという教示的・指導的態度は否定されます。カウンセラーは援助的態度でクライエントの自己理解を促進する役割を担います。
選択肢4:適切
カール・ロジャーズの理論で、「十分に機能する人間」は自己実現し、柔軟で開かれた存在として表され、クライエント中心療法の目標とされます。
国家試験 第29回 解説リンク集
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。