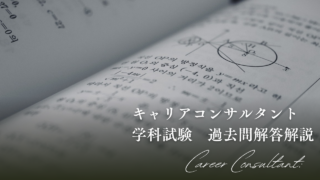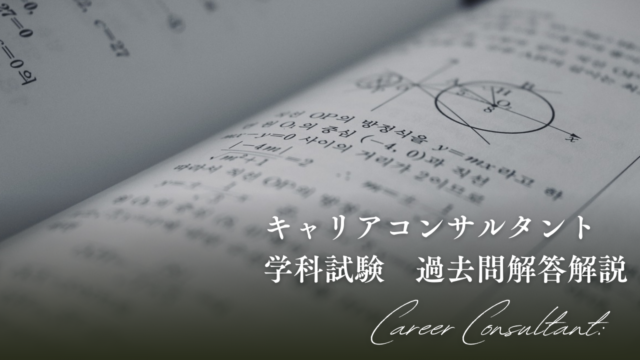第25回 国家資格キャリアコンルタント試験 学科試験 解答解説(問16〜20)
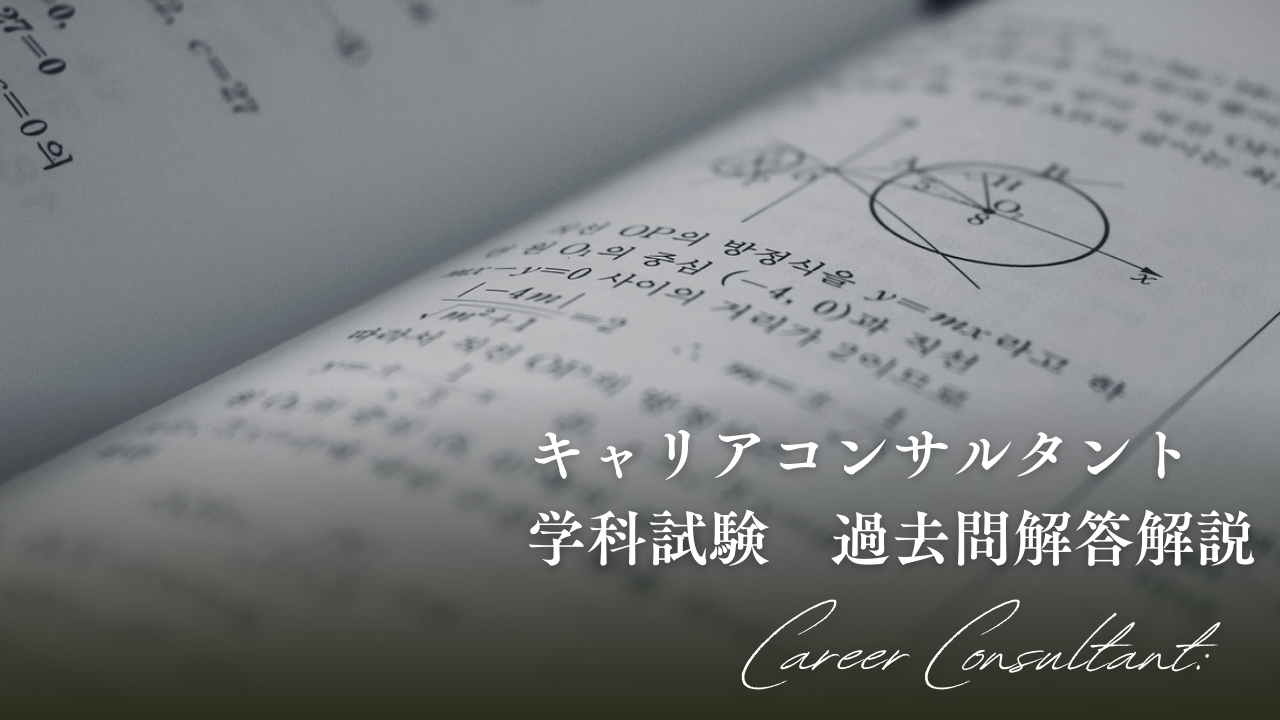
この記事について
第25回 国家資格キャリアコンサルタント試験解説を作成しました。
過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしています。
問16
正解:2
厚生労働省チラシ(職業能力開発推進者)
「職業能力開発促進法」第11条、第12条において、事業主は、雇用する労働者の職業能力の 開発・向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、「事業内職業能力開発計画」 を作成するとともに、その実施に関する業務を行う「職業能力開発推進者」を選任するよう努めることと規定されています。
選択肢1:不適切
平成30年7月の職業能力開発促進法施行規則等の改正によって、 職業能力開発推進者を「キャリアコンサルタント等の職業能力開発 推進者の業務を担当するための必要な能力を有する者」から選任 するものと規定されたが、キャリアコンサルタントに限定しているわけではない。
選択肢2:適切
<職業能力開発推進者の役割>
● 事業所単位の職業能力開発計画の作成・実施
● 企業内外の職業訓練を受け、又職業能力検定を受ける労働者に対する相談・指導
● 雇用型訓練を受ける労働者に対する相談・指導
● 労働者へのキャリアコンサルティング
● 労働者が職業能力開発を受けるための労務管理上の配慮に係る相談・指導
選択肢3:不適切
上記のとおり、努力義務とされている。
選択肢4:不適切
教育訓練給付金ではなく、人材開発支援助成金の支給要件となっている。
人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース) の利用にあたっては、職業能力開発推進者の選任が要件となっている。
問17
正解:4
選択肢1:不適切
2020年8月をピークにその人数は減少してい
選択肢2:不適切
航空運輸業を含む運 輸業・郵便業や製造業、宿泊業・飲食サービス業といった業種を中心に、幅広い業種におい て、同業種・異業種問わず、在籍型出向を実施している。
選択肢3:不適切
男女ともに若年層ほど実施率が高く、特に29歳以下の女性では、2017年から感染拡大前の2019年にかけて、副業・兼業実施率が5%ポイント程度上昇している。
選択肢4:適切
29歳以下が他より圧倒的に高い
問18
正解:1
労働経済学における「ミスマッチ」の概念の整理
労働経済学において、「ミスマッチ」という概念は多義的に用いられており、大きく2つに分けられる。
一つ目の意味のミスマッチ
労働市場全体からみたとき、産業や職業ごと、または地域間で分割されている複数の労働市場間で労働者が適切に分配されていないことを表す。 すなわち、ある労働市場では労働力供給が過剰で失業が発生しているにもかかわらず、別の労働市場では労働力が不足している状態が、労働市場全体からみたときにミスマッチの生じている状態と呼ばれる。
こうしたミスマッチが生じている場合、職業紹介を通じた労働力需給の調整や、職業訓練等を通じたスキルの付与等により、労働市場間で労働力の再分配を行うことが、労働市場政策として支持される。
二つ目の意味のミスマッチ
個別の企業と労働者の属性間に相性の不一致が生じている状態である。
企業と労働者が雇用契約を結ぶ際、企業が労働者のスキル、能力、選好などを完全に把握することや、労働者が企業や職務内容との相性、職場の雰囲気などを入職前に完全に把握することは困難であり、こうした情報の非対称性から生じる齟齬により企業の生産性や労働者の能力発揮などに悪影響が及ぼされている状態がミスマッチと呼ばれる。
こうしたミスマッチを解消するためには、転職などの際の情報の非対称性の緩和(企業情報の開示など)を通じて、外部労働市場を活用しやすくすることで、より自らに合う企業で労 働者が能力発揮できるよう支援すること等が労働市場政策として支持されることとなる。
選択肢1:不適切
上記のとおり、職業紹介を通じた労働力需給の調整や、職業訓練等を通じたスキルの付与等により、労働市場間で労働力の再分配を行うことが、労働市場政策として支持される。
選択肢2:適切
転職などの際の情報の非対称性の緩和(企業情報の開示など)を通じて、外部労働市場を活用しやすくすることで、より自らに合う企業で労 働者が能力発揮できるよう支援すること等が労働市場政策として支持されることとなる。
選択肢3:適切
ありえる。
選択肢4:適切
職種別の労働力需給の動向からは、感染症の感染拡大以前から、事務職では求職者超過、介護・福祉職では求人超過が続いているなど、構造的な労働力需給のミスマッチ が起きている兆候がみられる。
問19
正解:2
選択肢1:不適切
完全失業者は、以下の3つを満たす者
- 仕事がなくて調査週間に少しも仕事をしなかった者
- 仕事があればすぐに就くことができた者
- 調査週間に仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた者
選択肢2:適切
労働力人口比率は、15歳以上の人口に占める労働力人口(就業者と完全失業者)の割合を示します
選択肢3:不適切
完全失業率は、労働力人口(就業者と完全失業者)に占める完全失業者の割合を示します。
選択肢4:不適切
非労働力人口は、15歳以上の人口のうち、就業者や完全失業者以外の者を指します。具体的には、学生、専業主婦、高齢者などが含まれます。
問20
正解:3
選択肢1:適切
1日の所定労働時間
- 1企業平均7時間 48 分
- 労働者1人平均7時間 47 分
週所定労働時間
- 1企業平均 39 時間 20 分
産業別
- 「金融業,保険業」38 時間 02 分(最短)
- 「宿泊業、飲食サービス業」及び「生活 関連サービス業,娯楽業」が39 時間 35 分(最長)
労働者1人平均の週所定労働時間
- 39 時間 04 分
選択肢2:適切
企業が付与した年次有給休暇日数をみると、労働者 1 人平均は 17.6 日、このうち労働者が取得した日数は 10.9 日で、取得率は 62.1%となっており、昭和59 年以降過去最高となっている。
取得率を産業別にみると、「複合サービス事業」が 74.8%と最も高く、「宿泊業,飲食サービス業」が 49.1%と最も低くなっている。
選択肢3:不適切
変形労働時間制を採用している企業割合は 59.3%となっており、これを企業規模別にみると、「1,000 人以上」が77.3%、「300~999 人」が68.6%、「100~299 人」 が67.9%、「30~99 人」が 55.3%となっている。
また、変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1年単位の変形労働時間制」が31.5%、「1か月単位の変形労働時間制」が24.0%、「フレックスタイム制」が6.8%となっている。
選択肢4:適切
勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」が 6.0%、「導入を予定又は検討している」が11.8%、「導入予定はなく、検討もしていない」が81.5%となっている。
国家試験 第25回 問1〜50解説リンク集
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。