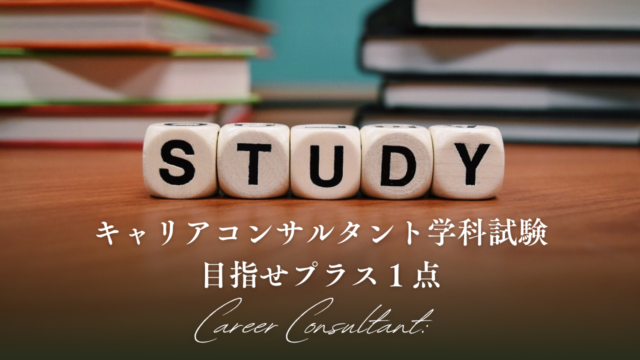雇用保険 まとめ
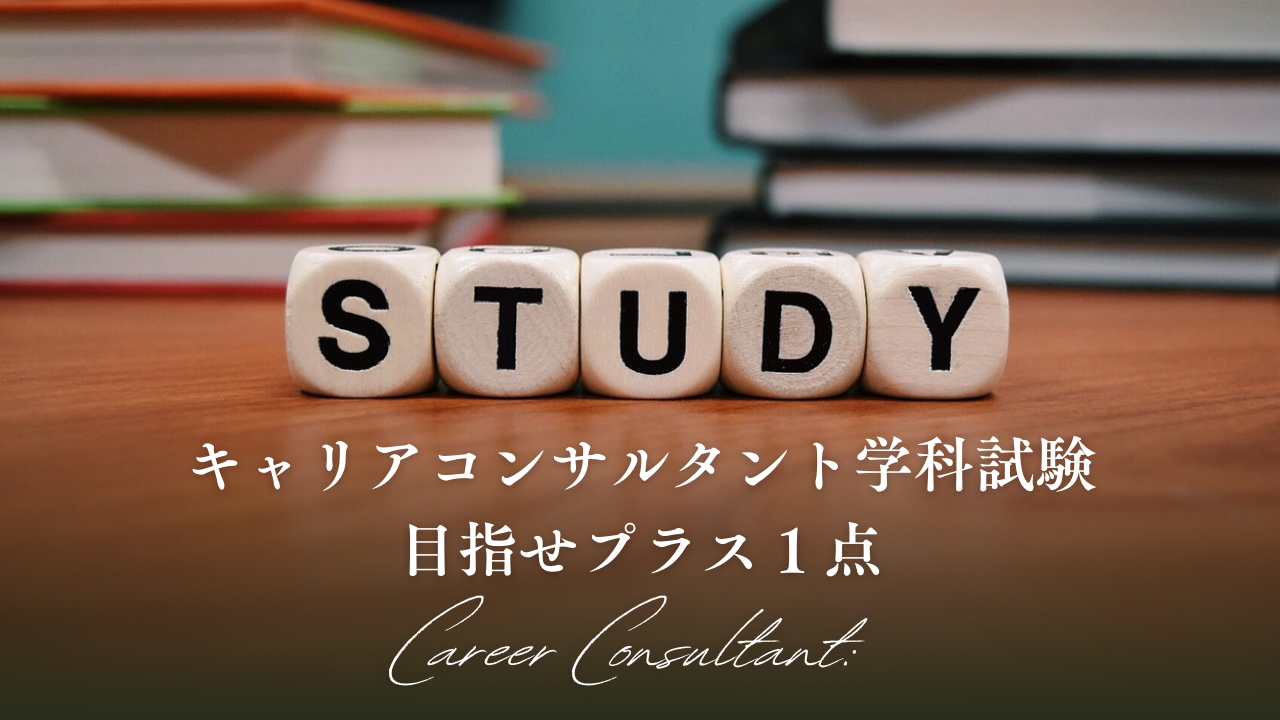
Contents
雇用保険
失業等給付(求職者・就職促進・教育訓練・雇用継続)
失業等給付の4つの給付
求職者給付(失業給付)
失業したときに、再就職活動に専念できるよう一時的にお金(基本手当)を支給する給付です。収入がなくても生活を支えるための支援です。
就職促進給付
再就職しやすくするための支援金で、早期就職者に支給されるほか、再就職後の生活を安定させる為の手当などが含まれます。
教育訓練給付
職業訓練やスキルアップのための教育を受ける際に支給される給付で、学び直しをサポートして再就職率の向上を目指します。
雇用継続給付
育児や介護などの理由で働き続けるのが難しい人に対して支給される給付金で、高年齢雇用継続給付のほか、介護休業給付が含まれる。
求職者支援事業
求職者支援事業とは、雇用保険の失業等給付を受けられない求職者を対象に、無料の職業訓練と生活支援給付(最大月10万円)を提供し、再就職やスキルアップをサポートする国の制度です。
主なポイント
- 失業保険を受給できない人が対象(離職者や自営業廃業者、受給終了者など)。
- ITや事務など様々な分野の職業訓練を無料で受けられる。
- 収入や資産など一定条件を満たせば、訓練期間中は月最大10万円の生活支援給付金も受給可能。
- ハローワークを通じて訓練申込や就職活動支援を受けられる。
育児休業等給付
2024年雇用保険制度改正で元々は、失業等給付の一部であった育児休業給付が「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」が創設されたことにより、それらとまとめられ、「育児休業等給付」として独立することとなりました。
育児休業等給付は、仕事と育児の両立を支援するため、育児期間中の収入減少をカバーする雇用保険の給付制度です。2025年施行改正で、3つの主要な給付に整理・拡充されました。
育児休業給付
育児休業給付とは、育児休業中に賃金が減ったときに雇用保険から支給されるお金のことです。2025年4月の改正で、より手厚くなっています。
育児休業給付金
- 休業前の賃金の67%(180日以降は50%)を支給。
- 受給には過去2年で12ヶ月以上の雇用保険加入が必要。
- 社会保険料免除や非課税で実質手取り減少を抑制。
出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
- 子の出生日から8週間以内の期間に取得する育児休業(最大4週間=28日以下)に対して支給される給付金。
- 産後パパ育休の場合は出生時育児休業給付金として休業開始時賃金月額の67%相当が支給される。
(支 給 額 = 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%) - 被保険者本人が産後間もない子の養育のために取得し、最大2回に分割取得可能。
- 休業前賃金の一定割合が支給され、父親の育休取得促進が目的。
- 産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であることが支給要件
出生後休業支援給付(2025年新設)
子の出生直後、両親が一定期間育児休業を取得すると、賃金の13%(最大28日間)を追加給付。
育児休業給付金と併せて手取り実質100%相当(給付率80%)に強化され、父親の育休取得を特に後押しします。
育児時短就業給付(2025年新設)
2歳未満の子を育てる従業員が時短勤務を選択した場合、賃金低下分の10%相当額を給付。育児と仕事の両立、働き続ける柔軟な環境づくりを目的としています.
雇用保険二事業
雇用保険二事業は、失業給付などの直接給付とは別に、労働者の雇用安定と能力開発を支援するための事業で、大きく2つに分かれます。
雇用安定事業
- 失業の予防や雇用機会の拡大を目指し、事業主に対する助成金支給や各種就職支援を行います。
- 中高年齢者や障害者の雇用促進、育児・介護との両立支援、雇用調整助成金なども含まれます。
- ハローワークの運営もこの雇用安定事業の一環として位置づけられ、職業紹介や再就職支援の場を提供し、地域の労働市場の安定を支えています。
能力開発事業
- 在職者や離職者の職業訓練支援に焦点を当てています。
- 事業主が行う職業教育訓練の助成や職業能力開発施設の設置、ジョブ・カード制度の整備などにより、労働者の技能向上を促進します。