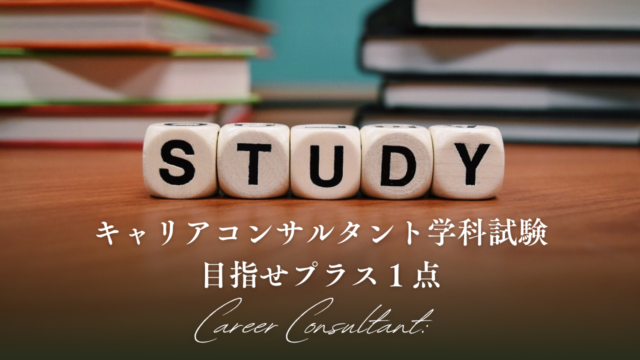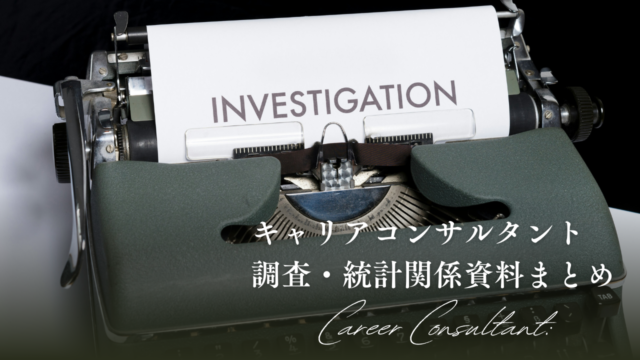「コンサルテーション」「コラボレーション」「コーディネーション」
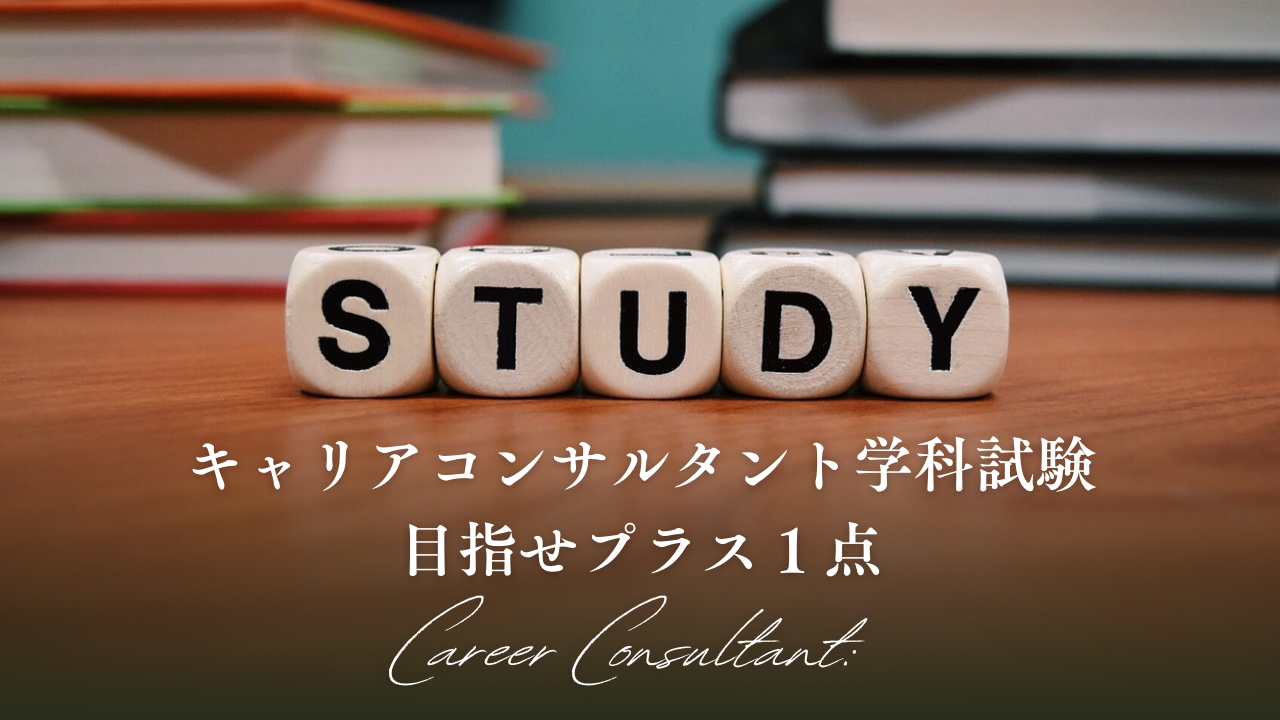
Contents
この記事について
毎回、「コンサルテーション」「コラボレーション」「コーディネーション」の違いがわからなくて選択肢を選ぶのに困るので整理しました。
「コンサルテーション」「コラボレーション」「コーディネーション」の違い
相談過程のマネジメントでは、複数の専門家や関係者が関与する場面が多く、それぞれの役割や関わり方に応じて「コンサルテーション」「コラボレーション」「コーディネーション」といった異なるアプローチが用いられます。
以下に、それぞれの違いを整理します。
コンサルテーション(Consultation)
定義
専門家が他の専門家や関係者に対して、問題解決のための助言や指導を行うプロセス
特徴
主に「助言」や「意見交換」が中心。
相談を受ける側(例:現場の担当者や他の専門職)が自らの業務の中で直面する課題について、専門家にアドバイスや指導を求める。
コンサルタント自身が直接実行するのではなく、助言を通じて支援する。
例:キャリアコンサルタントが、他の専門職(例:人事担当者や医療スタッフ)に対して、クライエント支援の方法について助言する。
コラボレーション(Collaboration)
定義
複数の専門家や関係者が、役割を分担しながら協力して共通の目標達成や課題解決に取り組むこと。
特徴
「協働」や「共同作業」がキーワード。
各専門家が対等な立場で、積極的な相互交流・対話を重ね、情報や資源を共有しながら新たな解決策を模索する。
必要に応じて新しい社会資源やシステムを開発することもある。
例:キャリアコンサルタント、産業医、福祉職などがチームを組み、クライエントの就労支援に協働で取り組む。
コーディネーション(Coordination)
定義
複数の関係者や専門機関の間で情報を交換し、作業や支援の計画を調整すること。
特徴
「調整」や「連携」が主な役割。
クライエントのニーズに応じて、関係機関や専門家の持つ情報や資源を適切に組み合わせ、支援が円滑に進むように調整する。
ケースマネジメントの場面で特に重要視され、必要な社会資源の確保やサービスの調整が中心となる。
例:ケースマネジャーが、福祉サービス、医療機関、就労支援機関などと連携し、クライエントの生活全体を支援するために各サービスを調整する。
比較表
| 項目 | コンサルテーション | コラボレーション | コーディネーション |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 助言・指導 | 協働・共同作業 | 調整・連携 |
| 関わり方 | 助言を求められる側が主役 | 対等な立場で共同作業 | 調整役が中心 |
| 参加者の関係性 | 専門家⇔他の専門家・関係者 | 複数の専門家・関係者が対等 | 専門家・関係者間の調整 |
| 具体的な活動内容 | アドバイス、指導、意見交換 | 共同作業、情報共有、資源開発 | サービス調整、情報交換、計画立案 |
| 例 | 他職種への助言 | 多職種によるチーム支援 | サービス提供機関の調整 |
このように、相談過程のマネジメントでは「コンサルテーション=助言」「コラボレーション=協働」「コーディネーション=調整」とそれぞれ異なる役割と機能を持ちます。状況や目的に応じて、これらを使い分けることが重要です。
この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いします。ブログ運営の励みになります。