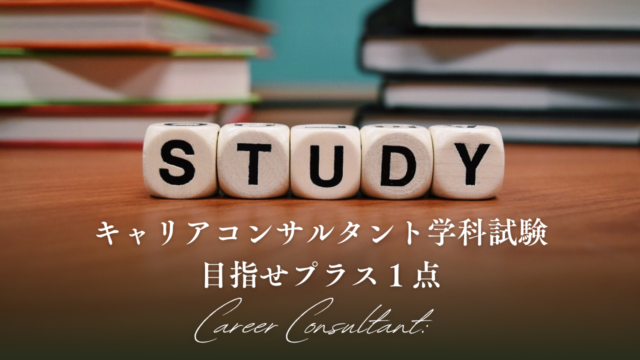社会構成主義
shasha
/

この記事について
サビカスのキャリア構築理論のところで出てくる社会構成主義について調べました。
キャリア構築理論は、社会構成主義に端を発しています。
社会構成主義(social constructionism)とは、社会に存在するさまざまな事象や現実が、客観的なものではなく、人々の相互作用やコミュニケーションを通じて構築されたものと捉える考え方です。
この理論は、1966年にピーター・L・バーガーとトーマス・ルックマンの著書『現実の社会的構成』によって広く知られるようになりました。
基本的な概念
- 現実の構築: 社会構成主義では、私たちが「現実」と認識しているものは、社会的な相互作用を通じて作られたものであり、固定的ではなく変化し続ける動的なプロセスとして捉えられます。
- 本質主義との対比: 社会構成主義は、「事象や属性には本質がある」とする本質主義に対立します。例えば、男女差を生物学的に固定されたものとみなすのが本質主義である一方、それを社会的に作られたものと考えるのが社会構成主義です。
- 言語と意味: 言語や会話が現実を構築する重要な要素とされ、個人の認識や意味づけが社会全体の中で共有されることで「現実」が形成されます。
応用分野
社会構成主義は、以下のような分野で幅広く応用されています。
- 心理学と教育: 学習や認知は他者との相互作用を通じて促進されるという視点から、教育理論やキャリアカウンセリングに取り入れられています。
- 組織開発と人材育成: 社内コミュニケーションや評価制度において、「思い込み」や「偏見」を排除し、多面的な視点で組織運営を行うための指針として活用されています。
- 社会学と文化研究: 社会現象や文化的慣習がどのように形成されるかを分析するための理論基盤となっています。
具体例
- ある社員が「仕事ができない」と評価される場合、その評価は実際の能力ではなく、周囲の印象や会話によって作られている可能性があります。このような状況を改善するために、社会構成主義的視点を取り入れることで偏見を排除し、公平な評価が可能になります。
社会構成主義とナラティブの共通点
- 現実の構築: 社会構成主義は、現実が客観的なものではなく、人々の相互作用や言語を通じて構築されると考えます。同様に、ナラティブも個人や集団が自らの経験を語ることで現実を意味づけし、再構築するプロセスと捉えられます。
- 言語の重要性: 社会構成主義では、言語が現実を形作る重要な要素とされます。ナラティブもまた、言語を通じて個人や集団のアイデンティティや価値観を表現・形成する手段です。
- 多様性と可変性: 社会構成主義は、現実や真実が一つではなく、多様で変化しうるものであることを強調します。同じように、ナラティブも固定されたものではなく、状況や文脈によって変化するものとされています。
ナラティブアプローチにおける社会構成主義の応用
ナラティブアプローチ(ナラティブセラピー)は、社会構成主義の考え方を基盤としており、以下のような特徴があります。
- 問題の外在化: クライエントが抱える問題を「自分自身」と切り離し、それを客観的に捉えることで新たな視点を得る技法です。これは社会構成主義的な「現実は交渉可能である」という考え方に基づいています。
- オルタナティブストーリーの構築: クライエントが持つ支配的な物語(ドミナントストーリー)とは異なる、新しい可能性や視点を含む物語(オルタナティブストーリー)を共に作り上げるプロセスです。これにより、個人が新たな意味づけや行動を選択できるようになります。
- 対等な関係性: ナラティブアプローチでは、セラピストとクライエントが対等な立場で対話し、「無知の姿勢」でクライエントの語りを尊重します。この姿勢は社会構成主義の「知識や真実は一方的に与えられるものではない」という考え方と一致します。
具体例
例えば、「自分は失敗者だ」という物語を持つ人がいる場合、その物語は過去の出来事や周囲からの評価によって形成されたものです。ナラティブアプローチでは、この物語を外在化し、新しい視点から「自分には集中力がある」「困難にも耐えてきた」といったオルタナティブストーリーを発見・再構築することを目指します[4][5]。
まとめ
社会構成主義は、現実や自己が他者との相互作用によって形成されるという視点を提供し、その考え方はナラティブアプローチに深く根付いています。
ナラティブは単なる個人の内面的な表現ではなく、社会的・文化的文脈との相互作用によって生まれるものであり、この両者は人間理解や支援において強力な理論的枠組みとなっています。