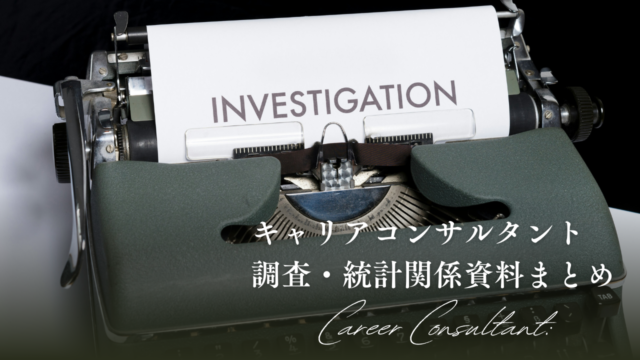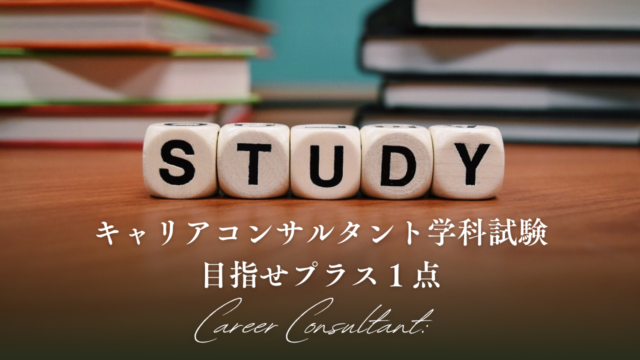第11次職業能力開発基本計画 第2部 職業能力開発をめぐる経済・社会環境の変化と課題 まとめ
shasha
/
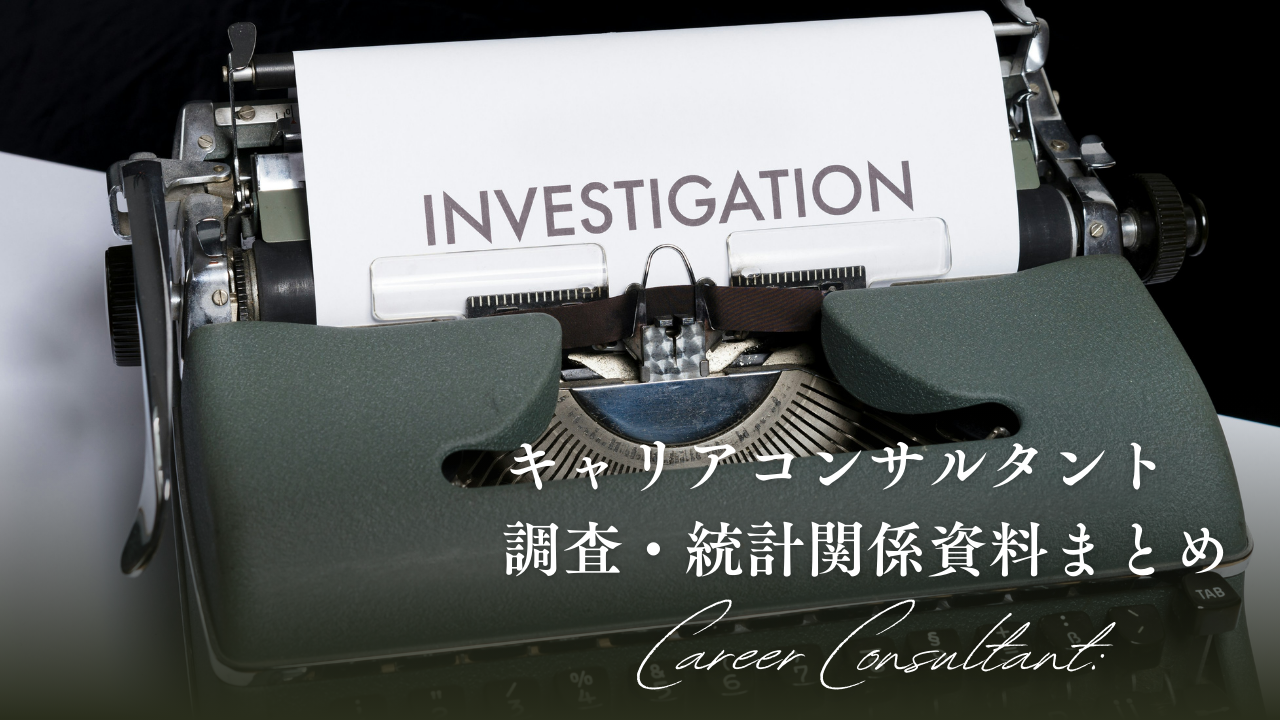
Contents
この記事について
第11次職業能力開発基本計画
第2部 職業能力開発をめぐる経済・社会環境の変化と課題
を簡単にまとめてみました。
この資料は、試験で多く出題される資料の1つですので、概要を掴んでおきましょう!
覚えること沢山で大変ですが、頑張りましょう!!
1 近年の労働市場の変化と課題
新型コロナウイルス感染症拡大前
- 雇用情勢は着実に改善していた
- 完全失業率は徐々に低下し、令和元年の年平均は2.4%
- 有効求人倍率は平成30年8月に1.63倍まで上昇したが、その後低下傾向
- 多くの産業で人手不足が課題、特に建設業、運輸業、医療・福祉、小売業、飲食サービス業等
新型コロナウイルス感染症拡大後(令和2年)
- 完全失業率は2.8%に上昇
- 有効求人倍率(年平均)は1.18倍に低下
- 求人が求職を上回って推移しているものの、求職者が引き続き増加傾向にあり雇用情勢は厳しさが続いている
今後の課題
新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響を注視する必要がある。
2 労働需要側の構造的な変化と課題
産業構造の変化
- 第1次・第2次産業から第3次産業(サービス業)へのシフト
- 医療・福祉分野の就業者割合が増加傾向
- 鉱業、建設業、卸売・小売業の就業者割合は減少見込み
技術進歩の影響
- 定型作業が多い職種の需要減少
- 技術に代替されない職種の需要増加
- 販売従事者・生産工程従事者の割合低下
- 専門的・技術的職業および事務従事者の割合上昇
IT人材の重要性
- 社会全体のDX加速に伴いIT人材の需要増加
- 幅広い業種でIT人材の確保が重要
人材育成の課題
- 日本の教育訓練費は主要国と比較して少ない
- 企業の教育訓練費割合は1990年代以降横ばいまたは低下傾向
- 非正規雇用労働者の能力開発機会が乏しい
今後の展望
- 新型コロナウイルス感染症の影響による構造変化の加速
- 「失業なき労働移動」実現のため、産業構造の変化に対応した能力開発が重要
3 日本の労働供給側の構造的変化と課題
人口動向と生産性
- 人口減少が続く中、一人当たりの労働生産性向上が重要
高齢者の就業
- 55-64歳の男性就業率が上昇
- 高齢者の就業意欲が国際的に高い
- 人生100年時代に向けた高齢者活躍の取組が必要
女性の労働参加
- 25-64歳の女性就業率が全年齢層で上昇傾向
- 潜在的な女性労働力の活用余地が大きい
- 現実の就業率と潜在的労働力率にギャップあり
雇用の動向
- 平均勤続年数は男女とも長期化傾向
- 転職者数は緩やかに増加、特に条件改善目的の転職が増加
- 非正規雇用労働者数が長期的に増加
若年層の課題
- フリーター数は減少傾向だが依然として一定数存在
- ニート数は横ばいから増加に転じ、きめ細かな支援が必要
自己啓発と能力開発
- 正規雇用労働者の自己啓発割合が相対的に高い
- 時間・費用の制約や適切なキャリアパスの不明確さが課題
- キャリアコンサルティング等の支援の重要性
新たな動向
- 若年層を中心に地方移住への関心高まる
- テレワークやオンライン会議の急速な普及
- スマートフォンの普及率がPCを上回る
まとめ
目を通さなければいけない資料が多いですが、とりあえず、雰囲気を掴む程度に、このまとめ記事を使ってください。
雰囲気を掴んだら、少しずつ肉付けをしていきましょう。
この記事が良いと思ったら
↓❤️をクリックお願いします。ブログ運営の励みになります。