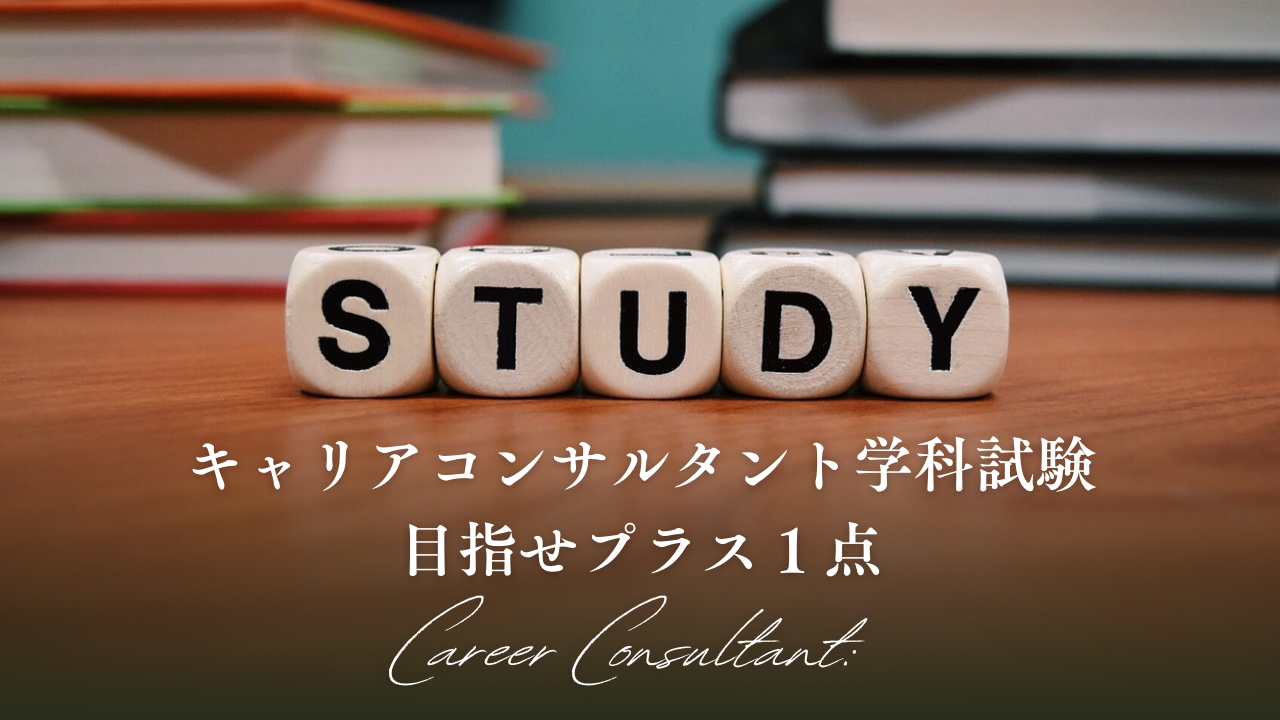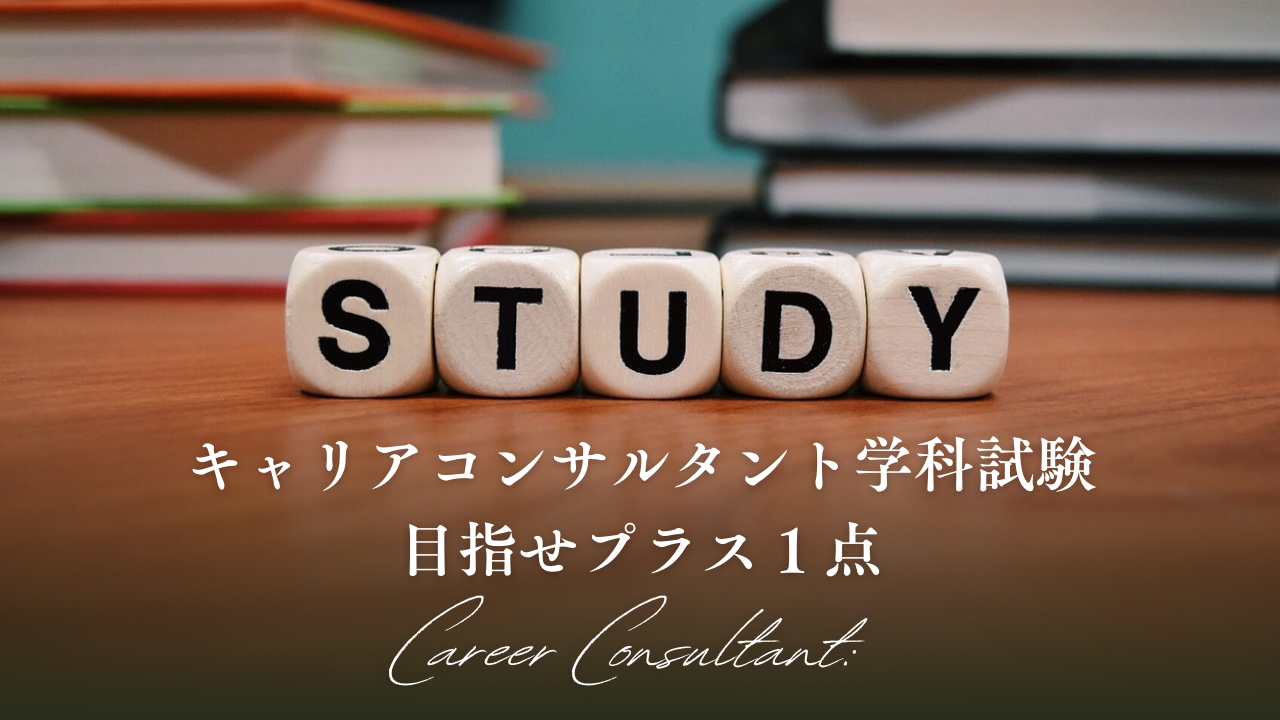自律訓練法は、1932年にドイツの精神科医ヨハネス・ハインリヒ・シュルツによって創始された自己催眠法およびリラクセーション技法です。
この方法は、自己暗示を用いて心身のリラックス状態を作り出し、自律神経のバランスを回復させることを目的としています。
自律訓練法の効果
自律訓練法には以下のような効果が期待されます:
- 疲労回復
- ストレス軽減
- 集中力の向上
- 身体的な痛みや精神的苦痛の緩和
- 睡眠の質の改善
- 衝動性の減少
自律訓練法の実践方法
自律訓練法は、背景公式と6つの公式からなる標準練習を段階的に行います:
- 背景公式:「気持ちが落ち着いている」
- 第1公式:「手足が重たい」
- 第2公式:「手足が温かい」
- 第3公式:「心臓が静かに打っている」
- 第4公式:「楽に呼吸している」
- 第5公式:「お腹が温かい」
- 第6公式:「額が心地よく涼しい」
各公式を1週間から10日ほど練習し、次の公式に進みます。練習時は受動的注意集中が重要です1。
実践上の注意点
- 第2公式までは自身で行えますが、第3公式以降は専門家の指導を受けることが推奨されます。
- 練習は1日3回、各3~4分程度行うのが効果的とされています。
- 練習後は必ず消去動作(手足を動かす、伸びをするなど)を行い、自己催眠状態から覚醒する必要があります。
- 心筋梗塞患者や低血糖状態の患者など、一部の疾患を持つ人には適さない場合があります。
- 実施前に医師に相談することが安全です。
自律訓練法は、継続的な練習によって効果が現れる方法です。個人差はありますが、多くの人が第2公式までで効果を実感できるとされています。
自律訓練法とリラクゼーショントレーニングの関係
共通点
- 目的:両方とも心身のリラックス状態を作り出し、ストレスを軽減することを目指します。
- 効果:不安や緊張の緩和、睡眠の質の改善、集中力の向上などの効果が期待できます。
- 自律神経系への影響:交感神経系を抑制し、副交感神経系を活性化させることで、心身のバランスを整えます。
自律訓練法の特徴
- 自己催眠的アプローチ:特定の言語公式を用いて、自己暗示により心身のリラックス状態を作り出します。
- 段階的な練習:背景公式と6つの標準公式を順番に習得していきます。
- 受動的注意集中:身体の感覚や変化に気づいていく受け身の姿勢が重要です。
リラクゼーショントレーニングとの関係
- 包括的概念:リラクゼーショントレーニングは、自律訓練法を含む様々なリラックス技法の総称です。
- 併用可能:自律訓練法は他のリラクゼーション法(呼吸法、瞑想、ヨガなど)と組み合わせて実践することができます。
- 選択肢の一つ:個人の好みや状況に応じて、最適なリラクゼーション技法を選択できます。